槍ヶ岳(百名山61座登頂) [日本百名山]
登山者憧れの山、「いつかは槍ヶ岳」と合言葉のように呟かれる山、その槍ヶ岳に遂に挑戦することになった。個人的には最長歩行距離、最高標高差、さらに国内最高地点へのチャレンジでもある。私は太股の痙攣(ピキキ現象)、膝の痛み、高山病という三大ハンディを有しており、そもそも登山が向いていない体質だ。加えて、もう還暦を迎えた。その私が槍ヶ岳に挑戦することになったのは、それを一日遅らせるとそれだけ不利になるだろうという切迫感からだ。
最近、単独行が多いが、槍ヶ岳は会社時代の友人と二人で行くことにした。この友人は、もうベテランの域に達しており、パートナーとしては大変心強い。しかも、彼は松本にアパートを借りているので、前泊、後泊を彼の家でさせてもらった。前回、下山後、一挙に帰るのは体力的に厳しかったこともあったので後泊させてもらうことは有り難い。
さて、登山ルートであるが、一日目は上高地バスターミナルからインし、槍沢コースで槍沢ロッジにて一泊。そして、二日目に槍ヶ岳山荘にて荷物を置き、槍ヶ岳にチャレンジ。その後、槍ヶ岳山荘にて泊まり、三日目は飛騨沢コースを下り、新穂高温泉にてアウトというものにした。そのため、友人の車と私の車とをそれぞれ出し、まずは友人の車を新穂高温泉の無料駐車場に駐め、私の車で二人であかんだな駐車場まで移動。私の車はあかんだな駐車場にて駐車し、そこからバスで上高地バスターミナルにまで移動した。あかんだな駐車場は8時20分発のバスに乗ることができ、8時50分に上高地バスターミナルに到着する。
登山開始は9時ちょうど。すぐ河童橋に着く。穂高の山々の展望が素晴らしい。そこからは、梓川に沿って気持ちのよいカラマツ林の中を歩いて行く。明神を通過するのは9時50分。梓川の灰色がかったエメラルド・グリーンの色が美しい。そして、徳沢に到着するのが11時。ここのミチクサ食堂で、昼食を取る。私が注文したのは、窯焼きのピザ。取り立てて美味しくはないが、大自然の中なので、その見えないスパイスで美味しく感じられるので、お店的には得である。

<河童橋の美しい景色を見ながら登山をスタートする>

<いきなり美しい森の中を歩いて行く>

<登山道は梓川に沿って設けられていて、気持ちがよい>

<ミチクサ食堂>

<ミチクサ食堂で注文したピザ>
さて、45分ぐらい休憩した後、また歩を進める。横尾山荘に到着したのは12時25分。ここはそのままスルーする。横尾まではほぼ平らな散歩道のようであったが、徐々に山道っぽくなってくる。槍ヶ岳が初めてその姿を現す槍見河原に到着したのは13時20分。そこから15分ぐらい歩くと一ノ沢に架かる木橋がある。この橋の麓でちょっと休憩をする。ここからは登りもだんだん増してくる。槍沢ロッジに到着したのは14時20分。一日目は登山道は極めて歩きやすく、ほどよい疲労感が溜まるぐらいであった。槍沢ロッジはなんと入浴ができる。15時から数時間だけだが、この入浴ができるというのは本当に有り難い。石鹸やシャンプーは使えないが、それでも疲れた筋肉をほぐすことができる。入浴後、夕食までに生ビールを飲む。生ビールは1000円と高額だが、溜まらなく美味い。生きていることが嬉しくなるような時間だ。夕食は17時からである。この宿はヘリコプターで物資が運ばれるので、夕食も豪華だ。唐揚げ、豆腐ハンバーグ、キャベツレタス、さつまいも、きんぴらゴボウ、ほうれん草と栄養のバランスも取れている。

<横尾山荘>

<槍見河原から槍ヶ岳を望む>

<谷に流れ込む瀬が登山者の目を楽しませる>

<一ノ沢>

<槍沢ロッジ>

<槍沢ロッジは清潔感のある山小屋。入浴もできるし、充電もできる>

<槍沢ロッジでの夕食>
この日は夕食を取ったらすぐ18時ぐらいに寝る。さて、ここで3時ぐらいに起きられればいいのだが、起きたら0時ちょっと過ぎであった。これはロッジが暑すぎたからである。流石に早すぎるので、ふとんの中でもんもんと過ごす。3時ぐらいになると、さすがに人々が動き始め、4時頃には床を出る。パッキングを終えて5時の朝食後、5時30分に出発する。ちなみに朝食も塩鮭や海苔などもあって豪華であった。槍沢ロッジも既に標高が1820メートルあるのだが、これから槍ヶ岳山頂の3180メートルを目指さなくてはならない。これはなかなかの標高差だ。ということでゆっくりと登っていく。しばらく歩くとババ平というテント場に着く。ここらへんはずっと槍沢沿いに深い谷を登っていく。水俣乗越は6時40分。天狗原分岐は7時30分頃。この頃になると、随分と下山する登山者と道を譲り、譲られで登っていくことになる。インバウンドの登山者も多いが、台湾から来たと思しき中年の女性カップルがいきなり登っている私にリュックでぶつかってきた。思わず「痛い!」と言うと、後続の仲間の女性が私を睨んできた。どうも「登り優先」という認識を持っていないようだ。台湾の若い男性はそこらへんがしっかりと対応できているので、まあ、例外的なケースなのかもしれないが、不快な思いをする。

<ババ平や槍沢ロッジから30分ぐらい歩いたところにある>
ジグザグのレキの坂道が続くが、それほど厳しくはない。ゆっくりと一歩一歩、確かめるように高度を上げていく。9時頃には目の前に槍ヶ岳が屹立するのが望め、登ろうという意思を強化させてくれる。坊主の岩には9時20分頃に到着。ちょっと休憩をして、山荘までの厳しい坂道を上がっていく。槍ヶ岳山荘に着いたのは11時10分。槍ヶ岳はもう目前に聳え立っている。この山荘からは、もう絶景をみることができる。

<ジグザグのレキ道を登っていく>

<槍ヶ岳が姿を現すと、スタミナ・ドリンクを飲んだように元気が出てくる>


<とはいえ、最後の小一時間は標高も高いこともあり相当、厳しい>
さて、いつもは1000メートルを登ると太股の筋肉が痙攣するのがほぼ習慣となっているのだが、今回はまったくピキキの「ピ」の字もないように上手く登っていくことができた。昨日、ロッジで入浴して筋肉をしっかりと解せたからかもしれない。
山荘に荷物を置き、昼食を取り(レトルトのカレーライス)、軽装になって山頂を目指す。カメラも持って行くのを止めて、携帯のカメラで撮るようにする。山荘から山頂までは98メートル。これはほぼ垂直という感じで、はしごと鎖場を登っていく。ただ、個人的にははしごと鎖場はむしろ楽で、それらがない時に、しっかりとどこに足場とするのかを判断する方が難しかった。見るからに登山経験が浅い若者のグループが先に登っていたのでやたら時間がかかった。これは、山頂の面積が狭いので頂上にいられる人の数が限られているからだ。しかし、天気がよいので、待っているのはそれほど苦痛ではなく、寒くもなかった。とはいえ、天気が悪かったら、このはしご待ちなどは厳しいだろう。さて、山頂には山荘を発って30分ほどで到着。その展望は素晴らしいに尽きる。ただ、携帯カメラは画面が暗すぎて、操作をすることができず、頂上の写真は友人の携帯カメラで撮影してもらった。

<槍ヶ岳山荘>

<槍ヶ岳山荘から常念岳を望む>

<岩にへばりついているように山頂を目指す登山者達>

<山頂での記念写真>
下りも前述した若者グループがぐずぐずしているので時間はかかった。まあ、しかし、他人のことはいえないが、登山経験が浅くて槍ヶ岳に来るのは無謀だと思う。今日のように天気がよければそれほど危険ではないかもしれないが、ちょっとでも条件が悪かったら結構、危ないと思う。
さて、山荘に戻ったのは13時30分頃であった。夕食は17時ということもあり、どっと疲れも出てきたので一眠りをしてしまった。これがいけなかった。というのは、起きたら頭痛がしたからだ。これは高山病か?と心配になる。どうも、高度に慣れないうちに寝てしまうのは高山病になるから、してはいけないことのようだ。そうでなくても高山病になりやすい質なのに愚かである。しかし、深呼吸をゆっくりと何回かしたら徐々に治ってきた。友人が麦酒でも呑もうか、と言ってちょっと躊躇したが、どうもおしゃべりは高山病にはいいらしいので、ゆっくりと生ビールを飲むことにする。これは結果的に大丈夫であった。そして、夕食を食べて、ちょっと談話室で時間を潰し20時頃に就寝する。とはいえ、この日も1時前に起きてしまった。なんか睡眠のリズムが今ひとつになっている。
4時頃に起床し、パッキングをして、明るくなってきた4時30分頃から日の出を見ようと外にでる。見事な朝焼けであるが、どうも槍ヶ岳が邪魔になってアングル的に日の出は見られないようだ。そばで立っているオジさんにそれを確認すると、「そればかりはしょうがない」と言われる。それで、山荘に戻ったのだが、実際は見られたようだ。こういう適当なことを言う輩には気をつけないといけない、ということを還暦になって再認識する。5時からは朝食。この山荘もヘリコプターで物資を運ぶだけあって贅沢だ。オクラ、焼き魚、ソーセージ、きんぴらゴボウ、卵焼き、お新香がつく。ここはご飯だけでなく、お味噌汁がお代わり自由なところが嬉しい。

<徐々に明るくなってくる空に映える槍ヶ岳>
5時40分には出発する。下りは飛騨沢コースを選んだ。常念岳や乗鞍、笠ヶ岳といった近場の山だけでなく、八ヶ岳や富士山までもを展望することができる。素晴らしい天気の中、標高を下げていく。キャンプ場の中を歩いて、少し行くと大喰岳と槍ヶ岳の鞍部にある飛騨乗越に着く。ここからは、レキの急坂をジグザグに下りていく。笠ヶ岳、さらには黒部五郎岳、白山を展望するという絶景の中をゆっくりと膝を痛めないように気をつけて下りていく。千丈沢乗越との分岐点は7時に通過する。そして、しばらく行くと飛騨沢が右手を流れ始める。その後は、樹林帯に入る。この樹林帯はずっと新穂高温泉まで続いていく。樹林帯の中は日影であり、その点ではとても有り難いが、展望も得られず、ひたすら歩いて行かなくてはならない。まあまあ、退屈である。とはいえ、集中を切らすと浮き石とかを踏んだり、濡れた岩で滑ったりするので油断はできない。

<槍ヶ岳山荘からは富士山をも展望できた>

<山荘からの笠ヶ岳の雄姿>

<飛騨乗越から八ヶ岳を望む>

<飛騨沢コースは途中から樹林帯をひたする歩くことになる>
槍平に到着したのは9時ちょうど。ここでゆっくりと休む。槍平小屋ではコーヒー・バッグではあるがコーヒーを呑めたりするのは嬉しい。ここの標高は1990メートル。1000メートルは下りたが、さらに900メートルは下りなくてはならない。うーむ、なかなか厳しい。

<槍平山荘>
とはいえ、結果的に槍平小屋から新穂高温泉までの下りはそれほど厳しいと感じるものではなかった。ただ、疲労から踏ん張りが効かなくなっているので、その点だけが辛かった。時折、沢を越える時は気をつけないといけないが、それ以外は敢えて危険箇所はなかった。そして13時には穂高平小屋に到着する。ここで中華麺を食べる。中華麺は本当、チャーシューとメンマと葱という非常にシンプルなものだが、炭水化物を欲している身体には嬉しい。穂高平小屋からは近道があったが、あまり管理がされていないということと、5分ぐらいしか短縮できないということで、遠回りではあるが林道を歩いて戻る。新穂高温泉に到着したのは13時30分頃であった。新穂高温泉に置いてあった友人の自動車に同乗し、そのままあかんだな駐車場に行く。そこで自分の自動車を拾い、松本へ。槍ヶ岳に登頂し、無事に下山できた満足感が身体を包む。登山の醍醐味である。

<幾つかの沢を越えて、新穂高温泉に向かう>

<穂高平小屋での中華麺>
さて、飛騨沢コースであるが、メリットとしては、槍沢コースに比べると標高差はあるが、距離は短い。また、バスに乗らずに自家用車のあるところまでそのまま下りることができるといった利点がある。加えて、槍沢コースに比べると登山者が圧倒的に少ない。これは、自分のペースで歩けるということだ。一方、デメリットとしては、槍沢コースに比べると圧倒的に歩きにくい。熊笹などの沿道の草木はある程度、手入れはされているが、それでもしょっちゅう身体に当たり、気になる。さらに景色は槍沢コースの方が圧倒的に優れている。水場も多く、歩いて楽しいのは圧倒的に槍沢コースの方だ。槍沢コースはしょっちゅう山小屋が出てくるのも嬉しい。ということで、特に登りは槍沢コースを行くのをお勧めする。ただ、下りは自家用車の駐車場に時間を気にしないでアプローチできるなど、状況に応じては選択肢に入れてもいいかもしれない。あと、登山ピーク時は槍沢コースの混み具合は相当、ストレスになるかもしれないので、こちらを選択肢に入れておいてもいいであろう。
<槍沢コース>
登山道整備度 ★★★★★ 素晴らしく歩きやすい。
岩場度 ★★★☆☆ 山荘直前ではなかなかの岩場を登らせられる。あと、槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳は岩場度は100%。
登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。
登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない
虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ 多少、虫はいる。
展望度 ★★★★★ 天気にもよるだろうが、素晴らしい展望が得られた。
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは素晴らしい・・・あかんだな駐車場。ただ、そこからバスに乗って上高地バスターミナルにまで移動しなくてはならない)
トイレ充実度 ★★★★★ (コース沿いに多くの山荘、テント場があり、トイレには困らない)
下山後の温泉充実度 N/A (このコースでは下山しなかった)
安全度 ★★★★☆ 登山道は非常に安全で怪我をするようなところはないが、登山客が多く、またマナーをあまり理解していない素人登山者が外国人を含めて多いので、その点は問題。
<飛騨沢コース>
登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は整備されているが、多少、歩きにくいところが数カ所散見される。
岩場度 ★★★★☆ 下山直後はなかなかの岩場を下らせられる。
登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ 樹林帯に入った後、多少ある。
登山道笹度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、熊笹が結構、生えており歩きにくい箇所が数カ所ある。
虫うっとうしい度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、虫が多少、鬱陶しい。虫除けスプレーを使った。
展望度 ★★★☆☆ 樹林帯に入るまでは素晴らしいが、樹林帯に入ると、展望はあまり得られなくなる。
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは文句なし。ただ、駐車場から登山口までは結構、距離がある)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (コース沿いに幾つかの山荘、テント場があり、これらでトイレを使えるが、そうでないところは多少、困るかもしれない)
下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (新穂高温泉の温泉は相当、いいのではと個人的には考えている)
安全度 ★★★☆☆ 危険箇所は特にはないが、浮き石、濡石などで足を掬われる可能性がある。
最近、単独行が多いが、槍ヶ岳は会社時代の友人と二人で行くことにした。この友人は、もうベテランの域に達しており、パートナーとしては大変心強い。しかも、彼は松本にアパートを借りているので、前泊、後泊を彼の家でさせてもらった。前回、下山後、一挙に帰るのは体力的に厳しかったこともあったので後泊させてもらうことは有り難い。
さて、登山ルートであるが、一日目は上高地バスターミナルからインし、槍沢コースで槍沢ロッジにて一泊。そして、二日目に槍ヶ岳山荘にて荷物を置き、槍ヶ岳にチャレンジ。その後、槍ヶ岳山荘にて泊まり、三日目は飛騨沢コースを下り、新穂高温泉にてアウトというものにした。そのため、友人の車と私の車とをそれぞれ出し、まずは友人の車を新穂高温泉の無料駐車場に駐め、私の車で二人であかんだな駐車場まで移動。私の車はあかんだな駐車場にて駐車し、そこからバスで上高地バスターミナルにまで移動した。あかんだな駐車場は8時20分発のバスに乗ることができ、8時50分に上高地バスターミナルに到着する。
登山開始は9時ちょうど。すぐ河童橋に着く。穂高の山々の展望が素晴らしい。そこからは、梓川に沿って気持ちのよいカラマツ林の中を歩いて行く。明神を通過するのは9時50分。梓川の灰色がかったエメラルド・グリーンの色が美しい。そして、徳沢に到着するのが11時。ここのミチクサ食堂で、昼食を取る。私が注文したのは、窯焼きのピザ。取り立てて美味しくはないが、大自然の中なので、その見えないスパイスで美味しく感じられるので、お店的には得である。

<河童橋の美しい景色を見ながら登山をスタートする>

<いきなり美しい森の中を歩いて行く>

<登山道は梓川に沿って設けられていて、気持ちがよい>

<ミチクサ食堂>

<ミチクサ食堂で注文したピザ>
さて、45分ぐらい休憩した後、また歩を進める。横尾山荘に到着したのは12時25分。ここはそのままスルーする。横尾まではほぼ平らな散歩道のようであったが、徐々に山道っぽくなってくる。槍ヶ岳が初めてその姿を現す槍見河原に到着したのは13時20分。そこから15分ぐらい歩くと一ノ沢に架かる木橋がある。この橋の麓でちょっと休憩をする。ここからは登りもだんだん増してくる。槍沢ロッジに到着したのは14時20分。一日目は登山道は極めて歩きやすく、ほどよい疲労感が溜まるぐらいであった。槍沢ロッジはなんと入浴ができる。15時から数時間だけだが、この入浴ができるというのは本当に有り難い。石鹸やシャンプーは使えないが、それでも疲れた筋肉をほぐすことができる。入浴後、夕食までに生ビールを飲む。生ビールは1000円と高額だが、溜まらなく美味い。生きていることが嬉しくなるような時間だ。夕食は17時からである。この宿はヘリコプターで物資が運ばれるので、夕食も豪華だ。唐揚げ、豆腐ハンバーグ、キャベツレタス、さつまいも、きんぴらゴボウ、ほうれん草と栄養のバランスも取れている。

<横尾山荘>

<槍見河原から槍ヶ岳を望む>

<谷に流れ込む瀬が登山者の目を楽しませる>

<一ノ沢>

<槍沢ロッジ>

<槍沢ロッジは清潔感のある山小屋。入浴もできるし、充電もできる>

<槍沢ロッジでの夕食>
この日は夕食を取ったらすぐ18時ぐらいに寝る。さて、ここで3時ぐらいに起きられればいいのだが、起きたら0時ちょっと過ぎであった。これはロッジが暑すぎたからである。流石に早すぎるので、ふとんの中でもんもんと過ごす。3時ぐらいになると、さすがに人々が動き始め、4時頃には床を出る。パッキングを終えて5時の朝食後、5時30分に出発する。ちなみに朝食も塩鮭や海苔などもあって豪華であった。槍沢ロッジも既に標高が1820メートルあるのだが、これから槍ヶ岳山頂の3180メートルを目指さなくてはならない。これはなかなかの標高差だ。ということでゆっくりと登っていく。しばらく歩くとババ平というテント場に着く。ここらへんはずっと槍沢沿いに深い谷を登っていく。水俣乗越は6時40分。天狗原分岐は7時30分頃。この頃になると、随分と下山する登山者と道を譲り、譲られで登っていくことになる。インバウンドの登山者も多いが、台湾から来たと思しき中年の女性カップルがいきなり登っている私にリュックでぶつかってきた。思わず「痛い!」と言うと、後続の仲間の女性が私を睨んできた。どうも「登り優先」という認識を持っていないようだ。台湾の若い男性はそこらへんがしっかりと対応できているので、まあ、例外的なケースなのかもしれないが、不快な思いをする。

<ババ平や槍沢ロッジから30分ぐらい歩いたところにある>
ジグザグのレキの坂道が続くが、それほど厳しくはない。ゆっくりと一歩一歩、確かめるように高度を上げていく。9時頃には目の前に槍ヶ岳が屹立するのが望め、登ろうという意思を強化させてくれる。坊主の岩には9時20分頃に到着。ちょっと休憩をして、山荘までの厳しい坂道を上がっていく。槍ヶ岳山荘に着いたのは11時10分。槍ヶ岳はもう目前に聳え立っている。この山荘からは、もう絶景をみることができる。

<ジグザグのレキ道を登っていく>

<槍ヶ岳が姿を現すと、スタミナ・ドリンクを飲んだように元気が出てくる>


<とはいえ、最後の小一時間は標高も高いこともあり相当、厳しい>
さて、いつもは1000メートルを登ると太股の筋肉が痙攣するのがほぼ習慣となっているのだが、今回はまったくピキキの「ピ」の字もないように上手く登っていくことができた。昨日、ロッジで入浴して筋肉をしっかりと解せたからかもしれない。
山荘に荷物を置き、昼食を取り(レトルトのカレーライス)、軽装になって山頂を目指す。カメラも持って行くのを止めて、携帯のカメラで撮るようにする。山荘から山頂までは98メートル。これはほぼ垂直という感じで、はしごと鎖場を登っていく。ただ、個人的にははしごと鎖場はむしろ楽で、それらがない時に、しっかりとどこに足場とするのかを判断する方が難しかった。見るからに登山経験が浅い若者のグループが先に登っていたのでやたら時間がかかった。これは、山頂の面積が狭いので頂上にいられる人の数が限られているからだ。しかし、天気がよいので、待っているのはそれほど苦痛ではなく、寒くもなかった。とはいえ、天気が悪かったら、このはしご待ちなどは厳しいだろう。さて、山頂には山荘を発って30分ほどで到着。その展望は素晴らしいに尽きる。ただ、携帯カメラは画面が暗すぎて、操作をすることができず、頂上の写真は友人の携帯カメラで撮影してもらった。

<槍ヶ岳山荘>

<槍ヶ岳山荘から常念岳を望む>

<岩にへばりついているように山頂を目指す登山者達>

<山頂での記念写真>
下りも前述した若者グループがぐずぐずしているので時間はかかった。まあ、しかし、他人のことはいえないが、登山経験が浅くて槍ヶ岳に来るのは無謀だと思う。今日のように天気がよければそれほど危険ではないかもしれないが、ちょっとでも条件が悪かったら結構、危ないと思う。
さて、山荘に戻ったのは13時30分頃であった。夕食は17時ということもあり、どっと疲れも出てきたので一眠りをしてしまった。これがいけなかった。というのは、起きたら頭痛がしたからだ。これは高山病か?と心配になる。どうも、高度に慣れないうちに寝てしまうのは高山病になるから、してはいけないことのようだ。そうでなくても高山病になりやすい質なのに愚かである。しかし、深呼吸をゆっくりと何回かしたら徐々に治ってきた。友人が麦酒でも呑もうか、と言ってちょっと躊躇したが、どうもおしゃべりは高山病にはいいらしいので、ゆっくりと生ビールを飲むことにする。これは結果的に大丈夫であった。そして、夕食を食べて、ちょっと談話室で時間を潰し20時頃に就寝する。とはいえ、この日も1時前に起きてしまった。なんか睡眠のリズムが今ひとつになっている。
4時頃に起床し、パッキングをして、明るくなってきた4時30分頃から日の出を見ようと外にでる。見事な朝焼けであるが、どうも槍ヶ岳が邪魔になってアングル的に日の出は見られないようだ。そばで立っているオジさんにそれを確認すると、「そればかりはしょうがない」と言われる。それで、山荘に戻ったのだが、実際は見られたようだ。こういう適当なことを言う輩には気をつけないといけない、ということを還暦になって再認識する。5時からは朝食。この山荘もヘリコプターで物資を運ぶだけあって贅沢だ。オクラ、焼き魚、ソーセージ、きんぴらゴボウ、卵焼き、お新香がつく。ここはご飯だけでなく、お味噌汁がお代わり自由なところが嬉しい。

<徐々に明るくなってくる空に映える槍ヶ岳>
5時40分には出発する。下りは飛騨沢コースを選んだ。常念岳や乗鞍、笠ヶ岳といった近場の山だけでなく、八ヶ岳や富士山までもを展望することができる。素晴らしい天気の中、標高を下げていく。キャンプ場の中を歩いて、少し行くと大喰岳と槍ヶ岳の鞍部にある飛騨乗越に着く。ここからは、レキの急坂をジグザグに下りていく。笠ヶ岳、さらには黒部五郎岳、白山を展望するという絶景の中をゆっくりと膝を痛めないように気をつけて下りていく。千丈沢乗越との分岐点は7時に通過する。そして、しばらく行くと飛騨沢が右手を流れ始める。その後は、樹林帯に入る。この樹林帯はずっと新穂高温泉まで続いていく。樹林帯の中は日影であり、その点ではとても有り難いが、展望も得られず、ひたすら歩いて行かなくてはならない。まあまあ、退屈である。とはいえ、集中を切らすと浮き石とかを踏んだり、濡れた岩で滑ったりするので油断はできない。

<槍ヶ岳山荘からは富士山をも展望できた>

<山荘からの笠ヶ岳の雄姿>

<飛騨乗越から八ヶ岳を望む>

<飛騨沢コースは途中から樹林帯をひたする歩くことになる>
槍平に到着したのは9時ちょうど。ここでゆっくりと休む。槍平小屋ではコーヒー・バッグではあるがコーヒーを呑めたりするのは嬉しい。ここの標高は1990メートル。1000メートルは下りたが、さらに900メートルは下りなくてはならない。うーむ、なかなか厳しい。

<槍平山荘>
とはいえ、結果的に槍平小屋から新穂高温泉までの下りはそれほど厳しいと感じるものではなかった。ただ、疲労から踏ん張りが効かなくなっているので、その点だけが辛かった。時折、沢を越える時は気をつけないといけないが、それ以外は敢えて危険箇所はなかった。そして13時には穂高平小屋に到着する。ここで中華麺を食べる。中華麺は本当、チャーシューとメンマと葱という非常にシンプルなものだが、炭水化物を欲している身体には嬉しい。穂高平小屋からは近道があったが、あまり管理がされていないということと、5分ぐらいしか短縮できないということで、遠回りではあるが林道を歩いて戻る。新穂高温泉に到着したのは13時30分頃であった。新穂高温泉に置いてあった友人の自動車に同乗し、そのままあかんだな駐車場に行く。そこで自分の自動車を拾い、松本へ。槍ヶ岳に登頂し、無事に下山できた満足感が身体を包む。登山の醍醐味である。

<幾つかの沢を越えて、新穂高温泉に向かう>

<穂高平小屋での中華麺>
さて、飛騨沢コースであるが、メリットとしては、槍沢コースに比べると標高差はあるが、距離は短い。また、バスに乗らずに自家用車のあるところまでそのまま下りることができるといった利点がある。加えて、槍沢コースに比べると登山者が圧倒的に少ない。これは、自分のペースで歩けるということだ。一方、デメリットとしては、槍沢コースに比べると圧倒的に歩きにくい。熊笹などの沿道の草木はある程度、手入れはされているが、それでもしょっちゅう身体に当たり、気になる。さらに景色は槍沢コースの方が圧倒的に優れている。水場も多く、歩いて楽しいのは圧倒的に槍沢コースの方だ。槍沢コースはしょっちゅう山小屋が出てくるのも嬉しい。ということで、特に登りは槍沢コースを行くのをお勧めする。ただ、下りは自家用車の駐車場に時間を気にしないでアプローチできるなど、状況に応じては選択肢に入れてもいいかもしれない。あと、登山ピーク時は槍沢コースの混み具合は相当、ストレスになるかもしれないので、こちらを選択肢に入れておいてもいいであろう。
<槍沢コース>
登山道整備度 ★★★★★ 素晴らしく歩きやすい。
岩場度 ★★★☆☆ 山荘直前ではなかなかの岩場を登らせられる。あと、槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳は岩場度は100%。
登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。
登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない
虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ 多少、虫はいる。
展望度 ★★★★★ 天気にもよるだろうが、素晴らしい展望が得られた。
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは素晴らしい・・・あかんだな駐車場。ただ、そこからバスに乗って上高地バスターミナルにまで移動しなくてはならない)
トイレ充実度 ★★★★★ (コース沿いに多くの山荘、テント場があり、トイレには困らない)
下山後の温泉充実度 N/A (このコースでは下山しなかった)
安全度 ★★★★☆ 登山道は非常に安全で怪我をするようなところはないが、登山客が多く、またマナーをあまり理解していない素人登山者が外国人を含めて多いので、その点は問題。
<飛騨沢コース>
登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は整備されているが、多少、歩きにくいところが数カ所散見される。
岩場度 ★★★★☆ 下山直後はなかなかの岩場を下らせられる。
登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ 樹林帯に入った後、多少ある。
登山道笹度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、熊笹が結構、生えており歩きにくい箇所が数カ所ある。
虫うっとうしい度 ★★★☆☆ 樹林帯に入った後は、虫が多少、鬱陶しい。虫除けスプレーを使った。
展望度 ★★★☆☆ 樹林帯に入るまでは素晴らしいが、樹林帯に入ると、展望はあまり得られなくなる。
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場へのアクセスは文句なし。ただ、駐車場から登山口までは結構、距離がある)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (コース沿いに幾つかの山荘、テント場があり、これらでトイレを使えるが、そうでないところは多少、困るかもしれない)
下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (新穂高温泉の温泉は相当、いいのではと個人的には考えている)
安全度 ★★★☆☆ 危険箇所は特にはないが、浮き石、濡石などで足を掬われる可能性がある。
鳳凰三山(百名山60座登頂) [日本百名山]
山梨県の南アルプスにある鳳凰三山に登る。前日の夜に韮崎まで行き、そこのシティ・ホテルに泊まる。東京から韮崎まで自動車で渋滞しなければ2時間で着く。2時間のためにわざわざ行くか、という指摘もあるかもしれないが、この2時間は結構、貴重である。それだけ早く登山を開始できるということもあるが、早朝に東京を出ることになると睡眠がどうしても不足する。この睡眠不足は登山のコンディショニングの悪化にも繋がるからだ。翌日、韮崎のホテルを発ったのは5時30分。そこから登山口である青木鉱泉にまで1時間ほどかかる。意外と遠い。途中、セブンイレブンにてお昼や水などを購入したこともあり、青木鉱泉の駐車場を出発したのは7時10分頃になってしまっていた。青木鉱泉の駐車場は有料で一日800円、一泊二日だと1600円ほどになる。

<青木鉱泉の駐車場から登山口へアプローチするところ>

<青木鉱泉・・敢えて入浴する価値はないかも>
採用したルートは上りがドンドコ沢コースで、下りが中道である。ドンドコ沢コースは渓谷沿いにカバの樹林帯を登っていき、とても気持ちがいい。丹沢の植林された杉林の中を歩くのとはまったく違い、爽快な気分で歩を進めていける。このドンドコ沢コース、途中で3つの落差のある滝を楽しめる。頑張って10分ほど横道に逸れて歩けば4つ(鳳凰の滝)目も見られるが、体力に自信のない自分はそれはやめてひたすら高度を稼いでいくことに専念する。とはいえ、下から順番に現れる南精進ヶ滝、白糸ノ滝、五色ノ滝は素晴らしく、これらの滝を見るためだけに登る価値があるとさえ思える。そして、これらの滝は苦しい上りを忘れさせてくれるご褒美のような効果があるのと同時に、ペース・コントロールにも役立つ。この登山道は素晴らしい。南精進ヶ滝は9時10分、白糸ノ滝は11時10分、五色ノ滝は12時頃に通過する。

<ドンドコ沢は沢沿いに登山道が整備されている>

<渓流沿いの登山道は涼しく、また水の流れが目を楽しませてくれるので飽きない>

<南精進ヶ滝>

<白糸ノ滝>

<五色ノ滝>
ただ、坂は厳しく、1000メートルほど登ったところぐらいで太股のピキキ状態が始まる。太股が攣ると不味いので、だましだまし登っていく。どうにかピキキ状態だけで、鳳凰山荘に着く。到着は13時10分。ほぼ青木鉱泉から鳳凰山荘まで6時間。なかなか古い感じの山小屋だ。ここで荷物を置き、軽装になった状態で鳳凰三山の一つ、地蔵岳にチャレンジする。地蔵岳までの道は途中から相当の急斜面の砂礫になる。私はストックを持っていたからよかったが、なかったらなかなか登ることさえ難しかったであろう。地蔵岳に着いたのは14時20分。ただ、残念ながらもうガスが発達していたので南アルプス側はほとんど何もみられない。どうもお昼ぐらいからガスが出るので、早朝に登るのが展望を得るためのポイントのようだ。上りと違って下りは、砂礫は楽だ。15時過ぎには山荘に戻る。夕食は17時過ぎ。カレーライス。お代わり自由ということで、お代わりをもらう。流石に体力は相当、なくなっている。18時には就寝する。

<山荘付近から地蔵岳を望む>

<地蔵岳までのアプローチは途中から砂礫。これを登るのは大変だ。ストックは必須であろう>

<地蔵岳の山頂>
2日目は1時には目が覚める。しばらく、布団の中でじっとしていたが、周りが起き始めた3時に起床。朝ご飯の代わりにもらったお弁当を布団の上で静かに食べて、出発する準備を整える。ただ、なかなか明るくならないので、じっと山小屋で出発を我慢する。どうやら、足下が見えるぐらい明るくなった4時15分に出発。観音岳に向かう。まだ太陽は出てないが、4時40分頃から太陽がのぼり始め、森が赤く染まっていく。写真を撮影したが、まるでフィルターをかけたかのような美しい色彩にちょっと神秘的なものさえ感じる。

<4時30分頃には朝焼けの空が明るんでいく>

<朝日の色で妖しいような赤味を帯びていく森の木々達>

<石楠花の花が咲き誇っている>
観音岳までの道のりもなかなか厳しい。山荘から450メートルは登らなくてはならない。ただ、雲一つない晴天のもとでの山行は爽快である。すがすがしい気持ちの中で歩いて行くと尾根の分岐点に着く。5時30分だ。地蔵岳、北岳、仙丈ヶ岳の勇壮なる山容が眼前に広がる。ここからは、薬師岳まで尾根を歩いて行く。尾根道は岩場の連続ではあるが、360度の雄大な展望を眺めつつ歩くのはなんともすがすがしい気持ちになる。登山のまさに醍醐味である。ある程度、歩くと甲斐駒ヶ岳の雄姿も展望できるようになる。そして、前方には富士山が姿を見せる。逆光でみる富士山はとても神々しい。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳、塩見岳、そして富士山という名だたる百名山の揃い踏みである。天気がよくて本当に有り難い。鳳凰三山、最高峰である観音岳に到着したのは6時20分。ここでちょっとお昼ご飯を食べて、薬師岳に向かう。薬師岳の到着時刻は7時20分。ここはあまり休まずに、そのまま中道を降りていく。中道はドンドコ沢とは違って森林の中を歩いて行く。木陰の中を歩いて行くのでそれなりに快適ではあるが、ドンドコ沢のようなドラマはない。ただ、急坂なのでくれぐれも膝に来ないように慎重にゆっくりと下りていく。御座石という巨石に到着したのは8時35分。さらに、なんか下山であるにも関わらず、へばってきたこともあり、休憩を頻繁に入れて下りていったら、登山口に着いたのが11時30分。ここから青木鉱泉までは道路を歩いて行く。幸い、自動車とはまったく出会わずに済んだ。この道路のルートも木陰が多く、渓流沿いであったためにそれなりに楽しみながら歩くことができた。そして、青木鉱泉の駐車場に到着したのが12時18分。いつものようにコースタイムより下山はちょっと時間がかかる。

<甲斐駒ヶ岳の雄姿。右に見えるのは地蔵岳>

<北岳と間ノ岳>

<仙丈ヶ岳>

<富士山>

<鳳凰三山の最高峰である観音岳>

<北岳と仙丈ヶ岳>

<薬師岳の山頂>

<御座石という巨石>

<中道登山口。ここからは車道を歩いて青木鉱泉に戻る>

<車道はしかし、それほど歩きにくくはなく、比較的快適であった>
青木鉱泉の事務所まで行き、未払いであった駐車場代を支払い、ついでに青木鉱泉に入浴した。ここは入浴料が1000円と高額であるにも関わらず、施設は老朽化しており、温泉のような身体を温めるような効能もなく、しかも手拭いも売っておらず、色々な意味で今ひとつであった。これは、今回の登山の唯一といっていいほどの残念な点であった。
登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、尾根道の岩のぼりは歩きにくい。
岩場度 ★★★☆☆ ドンドコ沢の鳳凰山荘手前、また観音岳の手前に岩場がある。鎖とかはなく、そういう意味で決して難しくはない。
登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。ただ、これはたまたま晴れの日が続いただけかもしれない。
登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない
虫うっとうしい度 ★★★☆☆ ドンドコ沢は少なく、ほとんど気にならない。むしろ鳳凰三山の尾根道は石楠花が咲いていたこともあり、アブ類が多く、鬱陶しかった。あと、中道はアブ、蜂らしきものに絡まれた。
展望度 ★★★★★ ガスが発達する前に登ったこともあり、鳳凰三山、特に観音岳からの展望は絶景。
駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (駐車場への道は未舗装で狭いところもあるが、危険ではない)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★☆☆☆☆ (青木鉱泉はあるが、ちょっと運転して他の温泉に行くことをお勧めする)
安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、個人的には体力的にハードであった

<青木鉱泉の駐車場から登山口へアプローチするところ>

<青木鉱泉・・敢えて入浴する価値はないかも>
採用したルートは上りがドンドコ沢コースで、下りが中道である。ドンドコ沢コースは渓谷沿いにカバの樹林帯を登っていき、とても気持ちがいい。丹沢の植林された杉林の中を歩くのとはまったく違い、爽快な気分で歩を進めていける。このドンドコ沢コース、途中で3つの落差のある滝を楽しめる。頑張って10分ほど横道に逸れて歩けば4つ(鳳凰の滝)目も見られるが、体力に自信のない自分はそれはやめてひたすら高度を稼いでいくことに専念する。とはいえ、下から順番に現れる南精進ヶ滝、白糸ノ滝、五色ノ滝は素晴らしく、これらの滝を見るためだけに登る価値があるとさえ思える。そして、これらの滝は苦しい上りを忘れさせてくれるご褒美のような効果があるのと同時に、ペース・コントロールにも役立つ。この登山道は素晴らしい。南精進ヶ滝は9時10分、白糸ノ滝は11時10分、五色ノ滝は12時頃に通過する。

<ドンドコ沢は沢沿いに登山道が整備されている>

<渓流沿いの登山道は涼しく、また水の流れが目を楽しませてくれるので飽きない>

<南精進ヶ滝>

<白糸ノ滝>

<五色ノ滝>
ただ、坂は厳しく、1000メートルほど登ったところぐらいで太股のピキキ状態が始まる。太股が攣ると不味いので、だましだまし登っていく。どうにかピキキ状態だけで、鳳凰山荘に着く。到着は13時10分。ほぼ青木鉱泉から鳳凰山荘まで6時間。なかなか古い感じの山小屋だ。ここで荷物を置き、軽装になった状態で鳳凰三山の一つ、地蔵岳にチャレンジする。地蔵岳までの道は途中から相当の急斜面の砂礫になる。私はストックを持っていたからよかったが、なかったらなかなか登ることさえ難しかったであろう。地蔵岳に着いたのは14時20分。ただ、残念ながらもうガスが発達していたので南アルプス側はほとんど何もみられない。どうもお昼ぐらいからガスが出るので、早朝に登るのが展望を得るためのポイントのようだ。上りと違って下りは、砂礫は楽だ。15時過ぎには山荘に戻る。夕食は17時過ぎ。カレーライス。お代わり自由ということで、お代わりをもらう。流石に体力は相当、なくなっている。18時には就寝する。

<山荘付近から地蔵岳を望む>

<地蔵岳までのアプローチは途中から砂礫。これを登るのは大変だ。ストックは必須であろう>

<地蔵岳の山頂>
2日目は1時には目が覚める。しばらく、布団の中でじっとしていたが、周りが起き始めた3時に起床。朝ご飯の代わりにもらったお弁当を布団の上で静かに食べて、出発する準備を整える。ただ、なかなか明るくならないので、じっと山小屋で出発を我慢する。どうやら、足下が見えるぐらい明るくなった4時15分に出発。観音岳に向かう。まだ太陽は出てないが、4時40分頃から太陽がのぼり始め、森が赤く染まっていく。写真を撮影したが、まるでフィルターをかけたかのような美しい色彩にちょっと神秘的なものさえ感じる。

<4時30分頃には朝焼けの空が明るんでいく>

<朝日の色で妖しいような赤味を帯びていく森の木々達>

<石楠花の花が咲き誇っている>
観音岳までの道のりもなかなか厳しい。山荘から450メートルは登らなくてはならない。ただ、雲一つない晴天のもとでの山行は爽快である。すがすがしい気持ちの中で歩いて行くと尾根の分岐点に着く。5時30分だ。地蔵岳、北岳、仙丈ヶ岳の勇壮なる山容が眼前に広がる。ここからは、薬師岳まで尾根を歩いて行く。尾根道は岩場の連続ではあるが、360度の雄大な展望を眺めつつ歩くのはなんともすがすがしい気持ちになる。登山のまさに醍醐味である。ある程度、歩くと甲斐駒ヶ岳の雄姿も展望できるようになる。そして、前方には富士山が姿を見せる。逆光でみる富士山はとても神々しい。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳、塩見岳、そして富士山という名だたる百名山の揃い踏みである。天気がよくて本当に有り難い。鳳凰三山、最高峰である観音岳に到着したのは6時20分。ここでちょっとお昼ご飯を食べて、薬師岳に向かう。薬師岳の到着時刻は7時20分。ここはあまり休まずに、そのまま中道を降りていく。中道はドンドコ沢とは違って森林の中を歩いて行く。木陰の中を歩いて行くのでそれなりに快適ではあるが、ドンドコ沢のようなドラマはない。ただ、急坂なのでくれぐれも膝に来ないように慎重にゆっくりと下りていく。御座石という巨石に到着したのは8時35分。さらに、なんか下山であるにも関わらず、へばってきたこともあり、休憩を頻繁に入れて下りていったら、登山口に着いたのが11時30分。ここから青木鉱泉までは道路を歩いて行く。幸い、自動車とはまったく出会わずに済んだ。この道路のルートも木陰が多く、渓流沿いであったためにそれなりに楽しみながら歩くことができた。そして、青木鉱泉の駐車場に到着したのが12時18分。いつものようにコースタイムより下山はちょっと時間がかかる。

<甲斐駒ヶ岳の雄姿。右に見えるのは地蔵岳>

<北岳と間ノ岳>

<仙丈ヶ岳>

<富士山>

<鳳凰三山の最高峰である観音岳>

<北岳と仙丈ヶ岳>

<薬師岳の山頂>

<御座石という巨石>

<中道登山口。ここからは車道を歩いて青木鉱泉に戻る>

<車道はしかし、それほど歩きにくくはなく、比較的快適であった>
青木鉱泉の事務所まで行き、未払いであった駐車場代を支払い、ついでに青木鉱泉に入浴した。ここは入浴料が1000円と高額であるにも関わらず、施設は老朽化しており、温泉のような身体を温めるような効能もなく、しかも手拭いも売っておらず、色々な意味で今ひとつであった。これは、今回の登山の唯一といっていいほどの残念な点であった。
登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、尾根道の岩のぼりは歩きにくい。
岩場度 ★★★☆☆ ドンドコ沢の鳳凰山荘手前、また観音岳の手前に岩場がある。鎖とかはなく、そういう意味で決して難しくはない。
登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。ただ、これはたまたま晴れの日が続いただけかもしれない。
登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない
虫うっとうしい度 ★★★☆☆ ドンドコ沢は少なく、ほとんど気にならない。むしろ鳳凰三山の尾根道は石楠花が咲いていたこともあり、アブ類が多く、鬱陶しかった。あと、中道はアブ、蜂らしきものに絡まれた。
展望度 ★★★★★ ガスが発達する前に登ったこともあり、鳳凰三山、特に観音岳からの展望は絶景。
駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (駐車場への道は未舗装で狭いところもあるが、危険ではない)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★☆☆☆☆ (青木鉱泉はあるが、ちょっと運転して他の温泉に行くことをお勧めする)
安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、個人的には体力的にハードであった
丹沢山への道のりは遠い [日本百名山]
休日の前日である11月22日、前日に天気予報がいいことを確認し、丹沢山への日帰り登山にチャレンジすることにした。ちょうど2年前にも丹沢山の日帰りにチャレンジした。2年前は菩提峠から表尾根で登ろうとして、塔の岳で挫折した。ということで、今回は最短距離である戸沢山荘から天神尾根で登ることにした。東名高速道路を走っている時は、晴天で富士山もはっきりと見える。これは、期待できる。
さて、しかし、朝、家を出たのが遅く、6時に登山口を出発したかったのに到着したのは7時30分に到着してしまった。この1時間30分はイタい。戸沢山荘からは1時間10分ぐらいで大倉尾根に着くのであるが、この道は厳しかった。まず、ルートが分かりにくい。そして、植林の杉の森は、地面も貧相でさらに急坂である。こんなにつまらない登山道も珍しい。ここは試練だと思い、我慢して登っていく。大倉尾根との合流点、茅場平に着いた時はコースタイムより20分ほど遅かった。茅場平の標高は1128メートルである。そこからも階段で登るような坂が続く。結構、腿に来る。花立山荘に到着したのは10時前。花立山荘での休みを挟み、塔の岳に向かう。塔の岳には10時30分に到着する。家を出た時は素晴らしい晴天で会ったのだが、塔の岳に着いた時には雲が出始め、富士山の展望も得られなかった。一昨年のまったく同じだ。ここから丹沢山の往復はコースタイムで3時間。今日は、コースタイムより時間がかかると考えると、戻ってくるのは14時。日が暮れるのが早いことを考えると最低でも15時30分までには駐車場に戻らないと行けないこと、さらには天気が悪いことで、ここはリスクを取らずに再び断念して塔の岳で帰路につくことにした。
帰りも最短距離ということで、つまらない天神尾根を下る。まあ、いろいろと文句は言ったが、それでも相模湾と大島の展望は素晴らしい。この展望は、丹沢山を登るときのご褒美である。
-18347.jpg)
<天神尾根は道は分かりにくく、急坂で、しかも杉林で登山していても楽しくない>

<天神尾根の説明!これは降りたくない>

<天神尾根を抜けても坂道は続く>

<二年前と同様に塔の岳から富士山は展望できなかった>

<霧の中に映える梅の桃色>

<丹沢からの相模湾の展望は素晴らしい>

<下山途中で現れた黒い雲。丹沢山を断念してよかったと思う>
さて、しかし、朝、家を出たのが遅く、6時に登山口を出発したかったのに到着したのは7時30分に到着してしまった。この1時間30分はイタい。戸沢山荘からは1時間10分ぐらいで大倉尾根に着くのであるが、この道は厳しかった。まず、ルートが分かりにくい。そして、植林の杉の森は、地面も貧相でさらに急坂である。こんなにつまらない登山道も珍しい。ここは試練だと思い、我慢して登っていく。大倉尾根との合流点、茅場平に着いた時はコースタイムより20分ほど遅かった。茅場平の標高は1128メートルである。そこからも階段で登るような坂が続く。結構、腿に来る。花立山荘に到着したのは10時前。花立山荘での休みを挟み、塔の岳に向かう。塔の岳には10時30分に到着する。家を出た時は素晴らしい晴天で会ったのだが、塔の岳に着いた時には雲が出始め、富士山の展望も得られなかった。一昨年のまったく同じだ。ここから丹沢山の往復はコースタイムで3時間。今日は、コースタイムより時間がかかると考えると、戻ってくるのは14時。日が暮れるのが早いことを考えると最低でも15時30分までには駐車場に戻らないと行けないこと、さらには天気が悪いことで、ここはリスクを取らずに再び断念して塔の岳で帰路につくことにした。
帰りも最短距離ということで、つまらない天神尾根を下る。まあ、いろいろと文句は言ったが、それでも相模湾と大島の展望は素晴らしい。この展望は、丹沢山を登るときのご褒美である。
-18347.jpg)
<天神尾根は道は分かりにくく、急坂で、しかも杉林で登山していても楽しくない>

<天神尾根の説明!これは降りたくない>

<天神尾根を抜けても坂道は続く>

<二年前と同様に塔の岳から富士山は展望できなかった>

<霧の中に映える梅の桃色>

<丹沢からの相模湾の展望は素晴らしい>

<下山途中で現れた黒い雲。丹沢山を断念してよかったと思う>
甲武信ヶ岳(百名山59座登頂) [日本百名山]
(1日目)
恵那山を下山した後、そのまま自動車で甲武信ヶ岳の麓の梓山まで行き、そこの民宿「白木屋旅館」に泊まる。旅館に着いたのは21時ちょっと前であった。前日は3時間も寝ないで登山をしたということもあり、チェックインをして風呂に入ったらすぐ爆睡した。目覚ましの音で目が覚め、身支度をして朝食として昨晩購入したおにぎりを一つだけ頬張り、チェックアウトしたのが7時。そして、車で毛木平の駐車場まで15分ぐらいかけて行き、準備を整え出発しようとして駐車場の写真を撮影しようとした時点で電池を民宿に忘れたことに気づく。慌てて取りに戻り、再び駐車場に行き、登山届を出して出発するときは既に8時を回っていた。
甲武信ヶ岳は私の知り合いなどは日帰りで登頂したりするが、私はとても無理。ということで甲武信小屋で一泊しての2日コースで山行を計画した。十文字小屋、三宝山経由で甲武信岳に登り、甲武信小屋で泊まり、下りは千曲川源流遊歩道を通るという周回コースである。毛木平駐車場からの道のりは、素晴らしいタケカンバの森で、また登山道もとても歩きやすい。朝日が森の木々を美しく照らし、地表は苔の絨毯のようで、その緑が気持ちを落ち着かせる。懐深い自然の中を一人、もくもくと歩いているのは、心が晴れやかになるだけでなく、頭も明晰になってくるようなリフレッシュ効果もあるということに気づく。森林浴としては最高だ。首都圏から比較的、近くにある山ではあるが、その静謐な雰囲気は早池峰山、大台ヶ原山などでしか感じられない自然の神々しさを感じる。百名山の多くの山は神体山であるが、昨日登った、神体山である恵那山などに比べても、はるかにこの甲武信ヶ岳の方が神々しく、神聖なものを感じる。神は自然に宿り、そこに神がいると指摘されればいる訳ではない、ということを理解するような神々しさである。

<神々しさを覚えるカラマツの森を歩いて行く>
十文字小屋までは2時間。森の中を歩き、展望はあまり得られないが、自然との対話をしているような行程は素晴らしい体験だ。十文字小屋の前に「きのこうどん」と書いた看板が立てられており、猛烈に「きのこうどん」を食べたくなり、小屋に入り、注文する。そもそも、当初の計画から、ここで遅い朝食を取ろうと思っていたのだが、「きのこうどん」があるとは知らなかったので嬉しい。小屋は、いかにも山小屋という感じのログハウスであり、雰囲気は抜群である。周辺には石楠花が群集している。小屋には、先客が一人、ご主人とお話をしていた。「きのこうどん」は700円であり、温かいものを胃に入れられるのは有り難い。うどんは当たり前であるがパックもので今ひとつである。これは山小屋だから致し方ない。何かを食べられるだけで感謝しないと。さて、キノコはいろいろな種類があり、味わい深い。しかし、変なキノコがあるな、と口に入れる前に見ると、なんとそれはムカデのような虫であった。ゲゲゲ。これは箸でお椀の外に出し、ご主人には何も言わずに残りのうどんを食べた。まあ、出汁になるかなとも思わなくもなかったが、ムカデのような虫を人類が食べないのはおそらく身体にもよくないからだろう、と思い、残念だが残りの汁は飲まずに残した。

<十文字小屋や昔ながらの雰囲気が残る山小屋>

<きのこうどん>
さて、小屋には30分ほど滞在して、再び登り始める。山の荘厳さは強まるばかりで、本当、この時間にこの場所にいることに感謝するような気持ちにさせられる。11時過ぎには大山の山頂前の鎖場を過ぎ、大山には11時20分に着く。ここからは素晴らしい絶景を楽しむことができる。紅葉で赤く染まった秩父の山々が素晴らしい。大山からは尾根道特有のアップダウンが続く。埼玉県と長野県の県境を行く。武信白岩岳を通過するのは12時30分。ただし、ここは山頂ではない。ここを少しのぼったところの展望が開ける岩場で昼食休憩。いつものようにカップヌードル。それほど寒くはないが、この時期では身体を温めることは重要かとも思う。ここを出発するのが13時。尻岩という奇岩を通過したのは13時30分。この岩は本当にお尻のように見えて愉快だ。さて、それからしばらく行くと埼玉県で最高峰の三宝山への登りになるのだが、なんと、結構、雪が積もっていた。今回、アイゼンは持ってきたのだが、車に置いてきたのだ。これは、恵那山とかもまったく雪が降っておらず、ここも大丈夫かと思ったからだったのだが、大失敗であった。後悔先に立たず、で何しろゆっくりと歩いて行く。三宝山に到着したのは14時30分。山頂からの展望はあまり良くない。ここから甲武信小屋までも1時間ぐらいはかかりそうなので、そそくさと山頂を後にする。一度、鞍部まで下り、最後に甲武信ヶ岳の登りに入る。ここも北側斜面ということもあり、雪が凍っていて注意を要する。登りは楽だが、明日の下りは結構心配だ。そして、甲武信ヶ岳の山頂に到着したのが15時30分。甲武信ヶ岳の名前の由来は甲州、武州、信州、すなわち山梨、埼玉、長野の3県の県境であることから来ている。甲武信ヶ岳より標高の高い山々が周辺にあるにも関わらず、ここが百名山に選ばれるというのがよく分かる、奥深い秩父の山々の最奥にどっしりと構えているその貫禄は、標高の相対的な低さなどを問わない存在感を有している。金峰山、瑞牆山(瑞牆山は見間違いない形状をしている)などの山々の見事な展望が得られたが、残念ながら富士山は見られず。結構、距離的には近いはずなのだが。ここから、甲武信小屋までは下りで20分。どうにか、16時前までにはチェックインできた。

<大山からも見事な展望>

<大山から川上村を展望する>

<大山から三宝山を望む>

<いつものように昼食はカップヌードル>

<尻岩は名前通り、お尻を思わせる形をしている>

<三宝山への登りはところどころアイスバーンになっており、アイゼンを持ってこなかったことを後悔する>

<甲武信ヶ岳山頂からの見事な展望。疲れが吹き飛ぶ>

<甲武信ヶ岳の山頂>
甲武信小屋はログハウス風でいかにも山小屋という風情を醸し出していた。昭和感がするような山小屋であり、雑魚寝である。夕ご飯はカレーで17時30分から。当たり前であるが美味しくはないが、こういう山で温かいご飯にありつけるのは本当、有り難い。18時には床に着いて就寝。

<甲武信小屋>
(2日目)
早く寝たのはいいのだが、目が覚めたらなんとまで22時30分であった。あちゃー。しかも頭が冴えてしまっている。これは、何たることだ、と思ったがそのまま布団の中でうとうとしていたら朝の5時になっていた。どれくらい脳味噌が休まったかは分からないが、5時30分から朝食の時間なのですぐ起床して準備をする。朝ご飯もお味噌汁とご飯とお漬物と海苔と茶碗蒸し。こういう時に海苔は有り難い。私の周りに座った人たちは、それぞれふりかけや煮卵などを取りだしていた。確かに、おかずは少ないので持参するのは賢明だ。今度、似たようなシチュエーションの時は持参しよう。
宿を出たのは6時。小屋周辺はアイスバーンのような状況になっており、横歩きで歩いて行く。どうも夜に雪が降ったようで、木々の枝は白くなっている。山頂まで再び登る。山頂に着いたのは6時25分。昨日と違ってガスが出ているので視界はほとんど得られない。そそくさと山頂を後にして下山を開始する。大弛峠との分岐点に着いたのは6時50分。ここからはジグザグの急坂を下りていくのだが、アイスバーンのような状況でアイゼンがないと相当、危険である。宿で隣に寝た人が、アイスバーンで捻挫をしていたこともあり、ここは慎重に慎重を期して、蟹の横ばいのように降りていく。ストックがなければ降りるのは無理であったろう。千曲川水源地の標識がある場所に着いたのは7時10分。ここからは千曲川の渓流沿いを歩いて行くのだが、その渓流美は特筆すべきものがある。英語のSereneという言葉が浮かぶ。十文字峠ルートとはまったく違う魅力であり、この周回ルートは、この甲武信ヶ岳の多彩な魅力を体験させてくれる素晴らしい登山ルートであると思う。滑滝という細長い滝に到着したのが8時30分。ここからは積雪もなく、歩きやすい道となる。途中、行き交った登山者が「こんなに平らだと退屈しちゃうよ」と不平を言ったのが驚きであった。個人的には、この見事な森林の中を歩いているだけで感動的に素晴らしい体験であると思っているのだが、そのように感じない人もいるのだな、という驚きである。まあ、登山者も十人十色ということだろうか。
十文字峠ルートと合流したのが10時05分。ここまでくれば毛木平まであと僅か。駐車場には10時10分に到着した。下りはほとんど休みも取らずにひたすら歩いたが、積雪のところをゆっくりと歩いたこともあって、時間的には結構、かかってしまった。とはいえ、10時過ぎに下山というのは、帰路の時間を考えるとなかなか理想的である。
甲武信ヶ岳に登ったことで秩父山塊の6つの百名山(両神山、雲取山、甲武信ヶ岳、金峰山、瑞牆山、大菩薩岳)を踏破したことになるが、甲武信ヶ岳はこの中では圧倒的に素晴らしかった。秩父という野球チームがあるとしたら、唯一オールスター・クラスの打率3割、ホームラン30本のバッターという四番打者のイメージである。まあ、そういうことを書くと金峯山(金峯山も打率2割8分ぐらいの凄さはあるかと思う)には怒られるかもしれないが、甲武信ヶ岳の凄みは山頂というよりかは、その山塊の生態系の素晴らしさである。特に森が素晴らしい。秩父という自然の素晴らしさを最も体現している山なのではないかと考える。とはいえ、百名山しか登っていないので、他の秩父の山の素晴らしさを知らない若輩者の無責任な意見として捉えていただければと思う。

<昨日とは違って、木々は雪化粧をしていた。おそらく夜に雪が降ったのであろう>

<千曲川源流の標識>

<千曲川源流ルートは、渓谷沿いの道で、十文字峠とは違った魅力を放つ>

<滑滝>

<十文字峠ルートとの合流点。あと5分ほど歩けば毛木平駐車場>
登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、どこもが登山道のようなところがたまにあり、道に迷う。ピンクのテープを目印として歩いて行かなくてはいけないところがある。
岩場度 ★★☆☆☆ 大平山、三宝山に登るところにちょっとした鎖の岩場はあるが、それほど大したものではない。
登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。千曲川源流ルートは季節によっては、多少ぬかるみができるかもしれない
登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない
虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)
展望度 ★★★★☆ 十文字峠は尾根道なので展望は素晴らしい。また山頂からの展望が優れているのは甲武信ヶ岳、そして大山。一方で、千曲川源流ルートは展望は期待できない。
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある。十文字小屋、甲武信小屋といったところでトイレに行くことができる)
下山後の温泉充実度 ☆☆☆☆☆ (川上村は基本、温泉はないようだ)
安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、ルートに迷う可能性がないわけではないので、その点は留意するといいであろう
恵那山を下山した後、そのまま自動車で甲武信ヶ岳の麓の梓山まで行き、そこの民宿「白木屋旅館」に泊まる。旅館に着いたのは21時ちょっと前であった。前日は3時間も寝ないで登山をしたということもあり、チェックインをして風呂に入ったらすぐ爆睡した。目覚ましの音で目が覚め、身支度をして朝食として昨晩購入したおにぎりを一つだけ頬張り、チェックアウトしたのが7時。そして、車で毛木平の駐車場まで15分ぐらいかけて行き、準備を整え出発しようとして駐車場の写真を撮影しようとした時点で電池を民宿に忘れたことに気づく。慌てて取りに戻り、再び駐車場に行き、登山届を出して出発するときは既に8時を回っていた。
甲武信ヶ岳は私の知り合いなどは日帰りで登頂したりするが、私はとても無理。ということで甲武信小屋で一泊しての2日コースで山行を計画した。十文字小屋、三宝山経由で甲武信岳に登り、甲武信小屋で泊まり、下りは千曲川源流遊歩道を通るという周回コースである。毛木平駐車場からの道のりは、素晴らしいタケカンバの森で、また登山道もとても歩きやすい。朝日が森の木々を美しく照らし、地表は苔の絨毯のようで、その緑が気持ちを落ち着かせる。懐深い自然の中を一人、もくもくと歩いているのは、心が晴れやかになるだけでなく、頭も明晰になってくるようなリフレッシュ効果もあるということに気づく。森林浴としては最高だ。首都圏から比較的、近くにある山ではあるが、その静謐な雰囲気は早池峰山、大台ヶ原山などでしか感じられない自然の神々しさを感じる。百名山の多くの山は神体山であるが、昨日登った、神体山である恵那山などに比べても、はるかにこの甲武信ヶ岳の方が神々しく、神聖なものを感じる。神は自然に宿り、そこに神がいると指摘されればいる訳ではない、ということを理解するような神々しさである。

<神々しさを覚えるカラマツの森を歩いて行く>
十文字小屋までは2時間。森の中を歩き、展望はあまり得られないが、自然との対話をしているような行程は素晴らしい体験だ。十文字小屋の前に「きのこうどん」と書いた看板が立てられており、猛烈に「きのこうどん」を食べたくなり、小屋に入り、注文する。そもそも、当初の計画から、ここで遅い朝食を取ろうと思っていたのだが、「きのこうどん」があるとは知らなかったので嬉しい。小屋は、いかにも山小屋という感じのログハウスであり、雰囲気は抜群である。周辺には石楠花が群集している。小屋には、先客が一人、ご主人とお話をしていた。「きのこうどん」は700円であり、温かいものを胃に入れられるのは有り難い。うどんは当たり前であるがパックもので今ひとつである。これは山小屋だから致し方ない。何かを食べられるだけで感謝しないと。さて、キノコはいろいろな種類があり、味わい深い。しかし、変なキノコがあるな、と口に入れる前に見ると、なんとそれはムカデのような虫であった。ゲゲゲ。これは箸でお椀の外に出し、ご主人には何も言わずに残りのうどんを食べた。まあ、出汁になるかなとも思わなくもなかったが、ムカデのような虫を人類が食べないのはおそらく身体にもよくないからだろう、と思い、残念だが残りの汁は飲まずに残した。

<十文字小屋や昔ながらの雰囲気が残る山小屋>

<きのこうどん>
さて、小屋には30分ほど滞在して、再び登り始める。山の荘厳さは強まるばかりで、本当、この時間にこの場所にいることに感謝するような気持ちにさせられる。11時過ぎには大山の山頂前の鎖場を過ぎ、大山には11時20分に着く。ここからは素晴らしい絶景を楽しむことができる。紅葉で赤く染まった秩父の山々が素晴らしい。大山からは尾根道特有のアップダウンが続く。埼玉県と長野県の県境を行く。武信白岩岳を通過するのは12時30分。ただし、ここは山頂ではない。ここを少しのぼったところの展望が開ける岩場で昼食休憩。いつものようにカップヌードル。それほど寒くはないが、この時期では身体を温めることは重要かとも思う。ここを出発するのが13時。尻岩という奇岩を通過したのは13時30分。この岩は本当にお尻のように見えて愉快だ。さて、それからしばらく行くと埼玉県で最高峰の三宝山への登りになるのだが、なんと、結構、雪が積もっていた。今回、アイゼンは持ってきたのだが、車に置いてきたのだ。これは、恵那山とかもまったく雪が降っておらず、ここも大丈夫かと思ったからだったのだが、大失敗であった。後悔先に立たず、で何しろゆっくりと歩いて行く。三宝山に到着したのは14時30分。山頂からの展望はあまり良くない。ここから甲武信小屋までも1時間ぐらいはかかりそうなので、そそくさと山頂を後にする。一度、鞍部まで下り、最後に甲武信ヶ岳の登りに入る。ここも北側斜面ということもあり、雪が凍っていて注意を要する。登りは楽だが、明日の下りは結構心配だ。そして、甲武信ヶ岳の山頂に到着したのが15時30分。甲武信ヶ岳の名前の由来は甲州、武州、信州、すなわち山梨、埼玉、長野の3県の県境であることから来ている。甲武信ヶ岳より標高の高い山々が周辺にあるにも関わらず、ここが百名山に選ばれるというのがよく分かる、奥深い秩父の山々の最奥にどっしりと構えているその貫禄は、標高の相対的な低さなどを問わない存在感を有している。金峰山、瑞牆山(瑞牆山は見間違いない形状をしている)などの山々の見事な展望が得られたが、残念ながら富士山は見られず。結構、距離的には近いはずなのだが。ここから、甲武信小屋までは下りで20分。どうにか、16時前までにはチェックインできた。

<大山からも見事な展望>

<大山から川上村を展望する>

<大山から三宝山を望む>

<いつものように昼食はカップヌードル>

<尻岩は名前通り、お尻を思わせる形をしている>

<三宝山への登りはところどころアイスバーンになっており、アイゼンを持ってこなかったことを後悔する>

<甲武信ヶ岳山頂からの見事な展望。疲れが吹き飛ぶ>

<甲武信ヶ岳の山頂>
甲武信小屋はログハウス風でいかにも山小屋という風情を醸し出していた。昭和感がするような山小屋であり、雑魚寝である。夕ご飯はカレーで17時30分から。当たり前であるが美味しくはないが、こういう山で温かいご飯にありつけるのは本当、有り難い。18時には床に着いて就寝。

<甲武信小屋>
(2日目)
早く寝たのはいいのだが、目が覚めたらなんとまで22時30分であった。あちゃー。しかも頭が冴えてしまっている。これは、何たることだ、と思ったがそのまま布団の中でうとうとしていたら朝の5時になっていた。どれくらい脳味噌が休まったかは分からないが、5時30分から朝食の時間なのですぐ起床して準備をする。朝ご飯もお味噌汁とご飯とお漬物と海苔と茶碗蒸し。こういう時に海苔は有り難い。私の周りに座った人たちは、それぞれふりかけや煮卵などを取りだしていた。確かに、おかずは少ないので持参するのは賢明だ。今度、似たようなシチュエーションの時は持参しよう。
宿を出たのは6時。小屋周辺はアイスバーンのような状況になっており、横歩きで歩いて行く。どうも夜に雪が降ったようで、木々の枝は白くなっている。山頂まで再び登る。山頂に着いたのは6時25分。昨日と違ってガスが出ているので視界はほとんど得られない。そそくさと山頂を後にして下山を開始する。大弛峠との分岐点に着いたのは6時50分。ここからはジグザグの急坂を下りていくのだが、アイスバーンのような状況でアイゼンがないと相当、危険である。宿で隣に寝た人が、アイスバーンで捻挫をしていたこともあり、ここは慎重に慎重を期して、蟹の横ばいのように降りていく。ストックがなければ降りるのは無理であったろう。千曲川水源地の標識がある場所に着いたのは7時10分。ここからは千曲川の渓流沿いを歩いて行くのだが、その渓流美は特筆すべきものがある。英語のSereneという言葉が浮かぶ。十文字峠ルートとはまったく違う魅力であり、この周回ルートは、この甲武信ヶ岳の多彩な魅力を体験させてくれる素晴らしい登山ルートであると思う。滑滝という細長い滝に到着したのが8時30分。ここからは積雪もなく、歩きやすい道となる。途中、行き交った登山者が「こんなに平らだと退屈しちゃうよ」と不平を言ったのが驚きであった。個人的には、この見事な森林の中を歩いているだけで感動的に素晴らしい体験であると思っているのだが、そのように感じない人もいるのだな、という驚きである。まあ、登山者も十人十色ということだろうか。
十文字峠ルートと合流したのが10時05分。ここまでくれば毛木平まであと僅か。駐車場には10時10分に到着した。下りはほとんど休みも取らずにひたすら歩いたが、積雪のところをゆっくりと歩いたこともあって、時間的には結構、かかってしまった。とはいえ、10時過ぎに下山というのは、帰路の時間を考えるとなかなか理想的である。
甲武信ヶ岳に登ったことで秩父山塊の6つの百名山(両神山、雲取山、甲武信ヶ岳、金峰山、瑞牆山、大菩薩岳)を踏破したことになるが、甲武信ヶ岳はこの中では圧倒的に素晴らしかった。秩父という野球チームがあるとしたら、唯一オールスター・クラスの打率3割、ホームラン30本のバッターという四番打者のイメージである。まあ、そういうことを書くと金峯山(金峯山も打率2割8分ぐらいの凄さはあるかと思う)には怒られるかもしれないが、甲武信ヶ岳の凄みは山頂というよりかは、その山塊の生態系の素晴らしさである。特に森が素晴らしい。秩父という自然の素晴らしさを最も体現している山なのではないかと考える。とはいえ、百名山しか登っていないので、他の秩父の山の素晴らしさを知らない若輩者の無責任な意見として捉えていただければと思う。

<昨日とは違って、木々は雪化粧をしていた。おそらく夜に雪が降ったのであろう>

<千曲川源流の標識>

<千曲川源流ルートは、渓谷沿いの道で、十文字峠とは違った魅力を放つ>

<滑滝>

<十文字峠ルートとの合流点。あと5分ほど歩けば毛木平駐車場>
登山道整備度 ★★★★☆ 素晴らしく歩きやすい。ただ、どこもが登山道のようなところがたまにあり、道に迷う。ピンクのテープを目印として歩いて行かなくてはいけないところがある。
岩場度 ★★☆☆☆ 大平山、三宝山に登るところにちょっとした鎖の岩場はあるが、それほど大したものではない。
登山道ぬかるみ度 ☆☆☆☆☆ まったくないと言ってよい。千曲川源流ルートは季節によっては、多少ぬかるみができるかもしれない
登山道笹度 ☆☆☆☆☆ まったくない
虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)
展望度 ★★★★☆ 十文字峠は尾根道なので展望は素晴らしい。また山頂からの展望が優れているのは甲武信ヶ岳、そして大山。一方で、千曲川源流ルートは展望は期待できない。
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある。十文字小屋、甲武信小屋といったところでトイレに行くことができる)
下山後の温泉充実度 ☆☆☆☆☆ (川上村は基本、温泉はないようだ)
安全度 ★★★★☆ 登山道はほぼ安全ではあるが、ルートに迷う可能性がないわけではないので、その点は留意するといいであろう
恵那山(百名山58座登頂) [日本百名山]
11月にチャレンジできる日本百名山はどこかと調べて、恵那山と甲武信ヶ岳に行くこととする。まず、最初にチャレンジしたのは恵那山である。恵那山には幾つかの登山道があるが、選択したのは最短距離の広河原ルートではなく、神坂峠ルートをとることにした。これは天気がいいので、展望がより得られるということと、アクセスがこちらの方が便利だと思ったからである。これは常に最短距離を選ぼうとする私としては、結構めずらしいことだ。
前泊したのは中津川ルートインホテルである。着いたのは22時頃だ。すぐ寝ようと思ったが、ゼミ生が販売している珈琲の売れ行きが悪く、三杯も飲んだせいか、なかなか寝付けない。結果、3時間も寝ていない状態で挑むことになる。ホテルを出たのは6時前だったが、登山口までは結構、遠く、駐車場に着いたのは6時45分。ただ、神坂峠駐車場は避けて、その手前の大櫓駐車場に停めることとする。神坂峠は標高が1535メートルに対して、大櫓駐車場からの追分登山口は標高が1320メートル。この200メートル差は大きいが、実は、この追分登山ルートは神坂峠ルートと鳥越峠で合流するのだが、神坂峠から鳥越峠に行くのに一度山を越えなくてはならない。これは、つまり、登山の最終ステージで登らなくてはいけない、ということだ。あと、追分登山ルートの方が鳥越峠に到達する距離も短く、時間も早い。ただ、標高差があるというのと、登山道が荒れているであろうと推測されるのがマイナスである。ただ、ここは標高差よりも時間と距離、そして登山の最後に登らなくてはならない、ということを避けて、こちらにした。これは、結果的にはプラスであったかと思う。というのは、登坂は急で厳しいが、恵那山、意外と時間がかかり、最後の30分の短縮は結構、有り難かったからである。
さて、大櫓駐車場からの追分登山口までは、神坂峠に向かって5分間ほど歩かなくてはならない。登山口は極めて分かりやすい。私は登り初めて、すぐにストックを忘れたことに気づき、駐車場に取りに行ったので、結局、登り始めたのは7時になってしまった。ただ、ストックは下山時には絶対的に必要だったので、これは10分を犠牲にしても取りに戻ったのは大正解であった。

<追分登山口は大櫓駐車場から神坂峠まで歩いて5分ぐらいのところにある>

<追分登山ルートはなかなかの急登である>

<追分登山ルートは熊笹にカバーされており、熊笹のところには崖だったりするので要注意だ>
さて、追分ルートは、相当の急坂ではあるが、ルートは分かりやすく、それほど厳しくはなかった。ただ、これは恵那山の神坂峠ルート全般に言えることだが、熊笹が登山道の両脇を覆っていて地面の様子が分かりにくい。場合によっては、急な崖であったりするところや岩とかがあっても分からないので、その点は要注意である。鳥越峠に着いたのは7時40分。ゆっくりと歩いて行ったので、コースタイムよりは大幅に時間がかかったが、それでも神坂峠からのコースタイムよりは短い。さて、ここからは熊笹を切り開いたかのような尾根道をひたすら歩いて行く。雲一つない快晴で、紅葉の山々が美しい。20分ほど歩くと御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山容が展望できる。うっすらと雪化粧をした峰々は素晴らしく美しい。右に御岳・乗鞍岳、左に南アルプスの山々をみて歩く尾根道は気持ちよいの一言である。とはいえ、両側が笹で見えないこの登山道、油断をすると崖に落ちるかもしれないので気は抜けない。大判山に到着したのは8時30分。ここからは恵那山がドーンと前方に聳え立つ。また、中央アルプスの展望が素晴らしい。ベンチもあり休憩には絶好のスポットなのだが、やたら声がでかい中年カップルがいてうざかったので、ここは通過する。大判山からはちょっと下りに入る。尾根ルートは展望が素晴らしいのはプラスだが、この上り、下りをさせられるところが辛い。さて、しばらく行くと急登が始まる。こだまエリアという休憩所に着いたのが9時10分。そして天狗ナギに9時30分頃に着く。これは山肌が大崩壊しているところで、その表情は荒々しく、自然の力のすさまじさを感じさせる。さて、ここからは相当の急登であり、途中で太股に来る。痙攣一歩手前というところをだましだまし登っていく。ここで随分と時間をかけたこともあり、分岐点に到着したのが10時40分。ここからはなだらかな稜線歩きで、右側に名古屋方面が展望できる。そこで出会った人が、今年で恵那山に登ったのは4回目だが、名古屋市内が展望できたのは初めてだ、と語っていた。それだけ、今日は視界に恵まれたということだろう。名古屋市内の方面は、伊吹山もしっかりとその姿を見せている。さて、しかし稜線歩きは、分岐点から山頂までのコースタイムでも20分で大したことがない筈だったが、私は苦労した。これは、遂に太股が限界近くに達していたこともあるのだが、一歩進めば、もう肉離れが起きるぐらいの状態にもなり、動けなくなって休んだりした。結果、山頂に着いたのは11時05分。さて、山頂はただ看板があるだけで、非常にしょぼい。というか、森の中なので、下手したら気づかない人もいるのではないだろうか。これまで登った百名山の中でも、最も地味というか控えめな山頂の看板である。展望もまったくない。ただ、そこから少し行くと避難小屋があり、避難小屋の裏側にある岩場からは南アルプスの絶景が見え、それらの山々の後ろに雪を被った富士山を見ることができた。これは、なかなかの感動的景観である。

<鳥越峠で神坂峠ルートと合流する>

<鳥越峠からは尾根沿いを歩いて行く。熊笹を切り開くような登山道である>

<右側には御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山々を展望できた>

<大判山にはベンチがあり、休憩するには好都合である>

<大判山から展望する恵那山>

<南アルプス側は雲海が広がっており、登山の疲れが吹き飛ぶような景色を見せてくれた>

<天狗ナギは岩肌が崩壊した荒々しい様子を見せてくれる>

<黒井沢ルートとの合流点。ここから山頂までは緩やかな尾根道>

<合流点から山頂までの尾根道から太平洋側を望む>

<合流点から山頂までの尾根道から名古屋市内を望む>

<山頂の看板。百名山でも最もしょぼい山頂と言えるのではないだろうか・・・まだすべてを登っていないので憶測だが、これまで私が登頂した山では最もしょぼい>

<避難小屋の裏側にある岩場から南アルプス側を展望する。富士山も姿を見せている>

<避難小屋の周辺はちょっと休憩して食事をとるにはうってつけの広場となっている>
ここでいつもの通り、カップヌードルの昼食を取る。私が愛読している塀内夏子の『なつこの百名山:百コ登ったどー』では恵那山の山頂は虫だらけで難儀だったというようなことを書いていたが、11月ということもあって虫類が現れることもなく、快適にご飯を食べることができた。
11時50分頃に下山を開始する。分岐点に到着したのが12時15分ぐらい。そこからは急坂を下っていく訳だが、寝不足もあってふらついてちょっと危ない。途中で少し、仮眠を取ろうかとも思ったが、恵那山の日の入りは16時25分ぐらい。ゆっくりすると暗くなってしまい、暗くなったら追分登山ルートは下るのが厳しいと考え、頑張って歩き続ける。上りではあまりチェックできなかった天狗ナギ、ウバナギが下りではよく観られ、その迫力をより一層感じることができた。大判山に着いたのが14時。ここまで来れば、もう大丈夫かなと思い、10分ほどベンチで横になる。鳥越峠に着いたのが14時50分。ここからの下りは、結構、岩が滑りやすく、上りに比べてずっと神経を使った。今回は得意の尻餅をせずに下山できるかな、と思っていたのだが、ゴールが見えた20メートルぐらい手前で滑ってしまった。最後まで緊張しろ、と心の中で自分を戒めていたのにこの様だ。ちょっと自己嫌悪である。
さて、恵那山は100名山登山でも今ひとつな山として語られることが多いが、天候に恵まれ、極めて快適な登山を楽しむことができた。改めて登山は天気と季節によって、その快適さ、満足度も大きく違うことを確認する。おそらく、恵那山の登山をするタイミングとしては、今年でも最もいいような日に登ることができたのではないだろうか。確かに展望が得られず、この長い急坂を登らされたらなかなか滅入るであろう。そういう意味では非常に恵まれた恵那山登山を楽しむことができた。

<往路では分からなかったが、復路ではその荒々しいウバナギを見ることができる>
登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は分かりやすいが尾根道は笹に覆われており、必ずしも歩きやすいとはいえない。また、追分登山ルートは荒れているとまでは言わないが、それほど整備がされていない。
岩場度 ★★☆☆☆ 天狗ナギから分岐点まではちょっとした岩場的な登りがある
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ この日は晴れていたので、それほど気にならなかったが、熊笹をかき分けるようなところはぬかるんでいる
登山道笹度 ★★★★★ 危険を感じるほど熊笹が生えている
虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)
展望度 ★★★★☆ 尾根道なので展望は相当、いいかと思われる。ただ、山頂からの展望がまったくないので、ちょっと減点をしている
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)
トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (山頂の避難小屋にはトイレがあるが、それ以外は特になかったような気がする)
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (麓の集落にクアリゾートがあり、温泉の代替として使える)
安全度 ★★★☆☆ 熊笹ルートは足を踏み外したり、こけたりする可能性が高く、それほど安全な登山道とはいえないと思われる
前泊したのは中津川ルートインホテルである。着いたのは22時頃だ。すぐ寝ようと思ったが、ゼミ生が販売している珈琲の売れ行きが悪く、三杯も飲んだせいか、なかなか寝付けない。結果、3時間も寝ていない状態で挑むことになる。ホテルを出たのは6時前だったが、登山口までは結構、遠く、駐車場に着いたのは6時45分。ただ、神坂峠駐車場は避けて、その手前の大櫓駐車場に停めることとする。神坂峠は標高が1535メートルに対して、大櫓駐車場からの追分登山口は標高が1320メートル。この200メートル差は大きいが、実は、この追分登山ルートは神坂峠ルートと鳥越峠で合流するのだが、神坂峠から鳥越峠に行くのに一度山を越えなくてはならない。これは、つまり、登山の最終ステージで登らなくてはいけない、ということだ。あと、追分登山ルートの方が鳥越峠に到達する距離も短く、時間も早い。ただ、標高差があるというのと、登山道が荒れているであろうと推測されるのがマイナスである。ただ、ここは標高差よりも時間と距離、そして登山の最後に登らなくてはならない、ということを避けて、こちらにした。これは、結果的にはプラスであったかと思う。というのは、登坂は急で厳しいが、恵那山、意外と時間がかかり、最後の30分の短縮は結構、有り難かったからである。
さて、大櫓駐車場からの追分登山口までは、神坂峠に向かって5分間ほど歩かなくてはならない。登山口は極めて分かりやすい。私は登り初めて、すぐにストックを忘れたことに気づき、駐車場に取りに行ったので、結局、登り始めたのは7時になってしまった。ただ、ストックは下山時には絶対的に必要だったので、これは10分を犠牲にしても取りに戻ったのは大正解であった。

<追分登山口は大櫓駐車場から神坂峠まで歩いて5分ぐらいのところにある>

<追分登山ルートはなかなかの急登である>

<追分登山ルートは熊笹にカバーされており、熊笹のところには崖だったりするので要注意だ>
さて、追分ルートは、相当の急坂ではあるが、ルートは分かりやすく、それほど厳しくはなかった。ただ、これは恵那山の神坂峠ルート全般に言えることだが、熊笹が登山道の両脇を覆っていて地面の様子が分かりにくい。場合によっては、急な崖であったりするところや岩とかがあっても分からないので、その点は要注意である。鳥越峠に着いたのは7時40分。ゆっくりと歩いて行ったので、コースタイムよりは大幅に時間がかかったが、それでも神坂峠からのコースタイムよりは短い。さて、ここからは熊笹を切り開いたかのような尾根道をひたすら歩いて行く。雲一つない快晴で、紅葉の山々が美しい。20分ほど歩くと御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山容が展望できる。うっすらと雪化粧をした峰々は素晴らしく美しい。右に御岳・乗鞍岳、左に南アルプスの山々をみて歩く尾根道は気持ちよいの一言である。とはいえ、両側が笹で見えないこの登山道、油断をすると崖に落ちるかもしれないので気は抜けない。大判山に到着したのは8時30分。ここからは恵那山がドーンと前方に聳え立つ。また、中央アルプスの展望が素晴らしい。ベンチもあり休憩には絶好のスポットなのだが、やたら声がでかい中年カップルがいてうざかったので、ここは通過する。大判山からはちょっと下りに入る。尾根ルートは展望が素晴らしいのはプラスだが、この上り、下りをさせられるところが辛い。さて、しばらく行くと急登が始まる。こだまエリアという休憩所に着いたのが9時10分。そして天狗ナギに9時30分頃に着く。これは山肌が大崩壊しているところで、その表情は荒々しく、自然の力のすさまじさを感じさせる。さて、ここからは相当の急登であり、途中で太股に来る。痙攣一歩手前というところをだましだまし登っていく。ここで随分と時間をかけたこともあり、分岐点に到着したのが10時40分。ここからはなだらかな稜線歩きで、右側に名古屋方面が展望できる。そこで出会った人が、今年で恵那山に登ったのは4回目だが、名古屋市内が展望できたのは初めてだ、と語っていた。それだけ、今日は視界に恵まれたということだろう。名古屋市内の方面は、伊吹山もしっかりとその姿を見せている。さて、しかし稜線歩きは、分岐点から山頂までのコースタイムでも20分で大したことがない筈だったが、私は苦労した。これは、遂に太股が限界近くに達していたこともあるのだが、一歩進めば、もう肉離れが起きるぐらいの状態にもなり、動けなくなって休んだりした。結果、山頂に着いたのは11時05分。さて、山頂はただ看板があるだけで、非常にしょぼい。というか、森の中なので、下手したら気づかない人もいるのではないだろうか。これまで登った百名山の中でも、最も地味というか控えめな山頂の看板である。展望もまったくない。ただ、そこから少し行くと避難小屋があり、避難小屋の裏側にある岩場からは南アルプスの絶景が見え、それらの山々の後ろに雪を被った富士山を見ることができた。これは、なかなかの感動的景観である。

<鳥越峠で神坂峠ルートと合流する>

<鳥越峠からは尾根沿いを歩いて行く。熊笹を切り開くような登山道である>

<右側には御岳、乗鞍岳、そして北アルプスの山々を展望できた>

<大判山にはベンチがあり、休憩するには好都合である>

<大判山から展望する恵那山>

<南アルプス側は雲海が広がっており、登山の疲れが吹き飛ぶような景色を見せてくれた>

<天狗ナギは岩肌が崩壊した荒々しい様子を見せてくれる>

<黒井沢ルートとの合流点。ここから山頂までは緩やかな尾根道>

<合流点から山頂までの尾根道から太平洋側を望む>

<合流点から山頂までの尾根道から名古屋市内を望む>

<山頂の看板。百名山でも最もしょぼい山頂と言えるのではないだろうか・・・まだすべてを登っていないので憶測だが、これまで私が登頂した山では最もしょぼい>

<避難小屋の裏側にある岩場から南アルプス側を展望する。富士山も姿を見せている>

<避難小屋の周辺はちょっと休憩して食事をとるにはうってつけの広場となっている>
ここでいつもの通り、カップヌードルの昼食を取る。私が愛読している塀内夏子の『なつこの百名山:百コ登ったどー』では恵那山の山頂は虫だらけで難儀だったというようなことを書いていたが、11月ということもあって虫類が現れることもなく、快適にご飯を食べることができた。
11時50分頃に下山を開始する。分岐点に到着したのが12時15分ぐらい。そこからは急坂を下っていく訳だが、寝不足もあってふらついてちょっと危ない。途中で少し、仮眠を取ろうかとも思ったが、恵那山の日の入りは16時25分ぐらい。ゆっくりすると暗くなってしまい、暗くなったら追分登山ルートは下るのが厳しいと考え、頑張って歩き続ける。上りではあまりチェックできなかった天狗ナギ、ウバナギが下りではよく観られ、その迫力をより一層感じることができた。大判山に着いたのが14時。ここまで来れば、もう大丈夫かなと思い、10分ほどベンチで横になる。鳥越峠に着いたのが14時50分。ここからの下りは、結構、岩が滑りやすく、上りに比べてずっと神経を使った。今回は得意の尻餅をせずに下山できるかな、と思っていたのだが、ゴールが見えた20メートルぐらい手前で滑ってしまった。最後まで緊張しろ、と心の中で自分を戒めていたのにこの様だ。ちょっと自己嫌悪である。
さて、恵那山は100名山登山でも今ひとつな山として語られることが多いが、天候に恵まれ、極めて快適な登山を楽しむことができた。改めて登山は天気と季節によって、その快適さ、満足度も大きく違うことを確認する。おそらく、恵那山の登山をするタイミングとしては、今年でも最もいいような日に登ることができたのではないだろうか。確かに展望が得られず、この長い急坂を登らされたらなかなか滅入るであろう。そういう意味では非常に恵まれた恵那山登山を楽しむことができた。

<往路では分からなかったが、復路ではその荒々しいウバナギを見ることができる>
登山道整備度 ★★★☆☆ 登山道は分かりやすいが尾根道は笹に覆われており、必ずしも歩きやすいとはいえない。また、追分登山ルートは荒れているとまでは言わないが、それほど整備がされていない。
岩場度 ★★☆☆☆ 天狗ナギから分岐点まではちょっとした岩場的な登りがある
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ この日は晴れていたので、それほど気にならなかったが、熊笹をかき分けるようなところはぬかるんでいる
登山道笹度 ★★★★★ 危険を感じるほど熊笹が生えている
虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (虫はいなかったが、これは季節的なことかもしれない)
展望度 ★★★★☆ 尾根道なので展望は相当、いいかと思われる。ただ、山頂からの展望がまったくないので、ちょっと減点をしている
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)
トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (山頂の避難小屋にはトイレがあるが、それ以外は特になかったような気がする)
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (麓の集落にクアリゾートがあり、温泉の代替として使える)
安全度 ★★★☆☆ 熊笹ルートは足を踏み外したり、こけたりする可能性が高く、それほど安全な登山道とはいえないと思われる
会津駒ヶ岳(百名山57座登頂) [日本百名山]
紅葉の最中、会津駒ヶ岳に挑戦した。前日に七入山荘に宿泊。本当は登山口の檜枝岐村の宿に泊まりたがったのだが、すべて満室。仕方なく、ちょっと距離のある七入山荘に泊まったのだが、この宿のサービスがとてもよかった。特に朝食のおにぎりが美味しかったことは有り難かった。まだ暗い中、4時50分頃に宿を出る。登山口は10分もしないで着く。
さて、会津駒ヶ岳は登山口に駐車場があるが、駐車場台数は20台ぐらいである。車中泊をする人が多く、5時頃でも結構、厳しいかもしれない。ここに駐車できないと、結構、歩くことになるので、ここに駐車できるかどうかで、中門岳まで行けるかどうかの判断に大きく影響を与えることとなる。登山口まではくねくね道の狭い道であるが、こういう登山道へのアクセス道路としては決して悪くない。路駐もできるスペースも幾つか見つけたので、仮に駐車できなくてもそれほどダメージもないかなとも思い、多少、安心する。
登山口の駐車場であるが、最後のスポットに運良く、駐車することができた。これは大きい。最初は懐中電灯をつけて歩き始めようかとも思っていたのだが、山間の谷は明るくなり始めると、すぐに周りも明るくなる。5時30分頃には、懐中電灯がなくても歩けるほどになったので出発する。駐車場からちょっと歩くと、登山口。そこからいきなり、階段となる。そして、階段を登り切った後も急登が続く。ただ、全体において急登が一番、きついのはこの登り初めだけであった。歩き始めであり、急く気持ちを抑えて、ゆっくりと一歩一歩進んでいく。登山の体験を通じて、序盤で調子こくと痛いしっぺ返しが来ることを、身をもって知ったので。

<登山口からいきなり階段>
さて、序盤戦の急登は厳しいものがあったが、徐々に斜度は緩やかになっていく。通常の山は山頂に近づくにつれ、斜度がきつくなるのとは逆だが、これは太股や膝には優しい。会津駒ヶ岳はブナの森が美しく、紅葉の色彩は見事の一言につきる。本当、日本の紅葉は世界に誇る美しさだと思う。しかし、これは山に登るから知ったことで、山に登らなかったら一生、知らずに過ぎてしまったかと思う。登山をしていてよかったと思うのは、こういう時だ。

<南会津の山々に雲海が広がる幻想的な風景>

<広葉樹の紅葉が美しく、目を楽しませてくれる>
広葉樹の森を歩き続けて3時間ぐらい経つと、視界が開けて会津駒ヶ岳が見える。周辺の紅葉した山々も見え、また、東側には雲海に覆われた山々が展望できる。今日は本当に素晴らしい登山日和だ。

<駒の小屋に近づくと展望が開け、足取りも軽くなる>

<駒の小屋周辺は湿原が発達しており、木道を歩くことになる>
さて、駒の小屋に到着したのが9時10分ぐらい。休憩時間を贅沢に取ったので、コースタイムよりは時間がかかっている。そこで荷物を置かしてもらい、会津駒ヶ岳に登る。登頂したのは9時30分。山頂には、記念写真を撮影する行列ができている。何しろ天気が素晴らしく、眺めも最高なので、中門岳にまで足を伸ばす。中門岳までのルートは木道で、ほぼ平ら。ただ、この木道は滑ることで有名。私は、そうじゃなくても滑りやすいので、十二分に注意をしながら歩を進める。中門岳の手前に中門大池がある。まるで鏡のように空模様を移している。会津駒ヶ岳から中門岳までは、ワイルドフラワーで有名らしいが、この紅葉の季節でも、周りの山々を展望しながら湿原を歩くのは、空中散歩のようで大変気持ちがよい。というか、このルートこそ会津駒ヶ岳登山のハイライトなのではないかと思ったぐらいだ。

<会津駒ヶ岳の山頂からは見事な燧ヶ岳を見ることができる>

<会津駒ヶ岳の山頂>

<山頂から中門岳への湿原を通る道は、空中散歩のようでとても爽快だ>

<中門大池>

<中門岳からは360度の見事な展望が得られる>

<中門岳と会津駒ヶ岳を結ぶ道から燧ヶ岳の素晴らしい山容を望む>

<この看板は怖い!しかし、無事に滑らずに往復することができた>

<駒の小屋周辺からの展望。紅葉が彩るランドスケープが美しい>

<駒の小屋のすぐそばの展望>
さて、12時には駒の小屋に戻り、そこで昼食。今回の昼食はみな、カップ麺系。そのために三人分の水を運んだので、結構、重かったがそれから解放されて、帰りはちょっと荷物が軽くなった。12時50分に小屋を発つ。その後、ほぼ休憩なしのピッチで下り、14時40分には登山口に到着する。天気がよくて、登山道もあまりすべらずに戻ることができたが、雨の後とかは相当、滑りやすそうな泥道なので、留意することが必要であろう。
その後、近くの温泉で汗を流し、16時頃に帰路につく。紅葉シーズンの晴天日の登山は、本当に素晴らしいことを再確認。足が動くうちは、一年に最低でも一回は観に行きたい。
登山道整備度 ★★★★☆(しっかりと整備されており、歩きやすい。ただ、雨が降った後などはぬかるみができるであろう。駒の小屋近くや、山頂付近は木道が整備されている)
岩場度 ☆☆☆☆☆(岩場はない)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (晴れていたので気にならなかったが、雨だと登山口からちょっと先まではぬかるみで歩きにくいかもしれない)
虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (10月中旬ということもあるが、虫はまったく気にならなかった)
展望度 ★★★★★ (会津駒ヶ岳山頂から中門岳までは空中散歩のよう)
駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (最後のスポットに駐められたのはラッキーだったが、駐められないと国道の駐車場に駐めることとなる)
トイレ充実度 ★★☆☆☆ (駒ヶ岳山荘にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★★★★★ (登山口のそばに温泉がある)
安全度 ★★★★☆ (一部、木道が滑りやすいが気をつけて歩けば大丈夫。特に危険なところはない)
さて、会津駒ヶ岳は登山口に駐車場があるが、駐車場台数は20台ぐらいである。車中泊をする人が多く、5時頃でも結構、厳しいかもしれない。ここに駐車できないと、結構、歩くことになるので、ここに駐車できるかどうかで、中門岳まで行けるかどうかの判断に大きく影響を与えることとなる。登山口まではくねくね道の狭い道であるが、こういう登山道へのアクセス道路としては決して悪くない。路駐もできるスペースも幾つか見つけたので、仮に駐車できなくてもそれほどダメージもないかなとも思い、多少、安心する。
登山口の駐車場であるが、最後のスポットに運良く、駐車することができた。これは大きい。最初は懐中電灯をつけて歩き始めようかとも思っていたのだが、山間の谷は明るくなり始めると、すぐに周りも明るくなる。5時30分頃には、懐中電灯がなくても歩けるほどになったので出発する。駐車場からちょっと歩くと、登山口。そこからいきなり、階段となる。そして、階段を登り切った後も急登が続く。ただ、全体において急登が一番、きついのはこの登り初めだけであった。歩き始めであり、急く気持ちを抑えて、ゆっくりと一歩一歩進んでいく。登山の体験を通じて、序盤で調子こくと痛いしっぺ返しが来ることを、身をもって知ったので。

<登山口からいきなり階段>
さて、序盤戦の急登は厳しいものがあったが、徐々に斜度は緩やかになっていく。通常の山は山頂に近づくにつれ、斜度がきつくなるのとは逆だが、これは太股や膝には優しい。会津駒ヶ岳はブナの森が美しく、紅葉の色彩は見事の一言につきる。本当、日本の紅葉は世界に誇る美しさだと思う。しかし、これは山に登るから知ったことで、山に登らなかったら一生、知らずに過ぎてしまったかと思う。登山をしていてよかったと思うのは、こういう時だ。

<南会津の山々に雲海が広がる幻想的な風景>

<広葉樹の紅葉が美しく、目を楽しませてくれる>
広葉樹の森を歩き続けて3時間ぐらい経つと、視界が開けて会津駒ヶ岳が見える。周辺の紅葉した山々も見え、また、東側には雲海に覆われた山々が展望できる。今日は本当に素晴らしい登山日和だ。

<駒の小屋に近づくと展望が開け、足取りも軽くなる>

<駒の小屋周辺は湿原が発達しており、木道を歩くことになる>
さて、駒の小屋に到着したのが9時10分ぐらい。休憩時間を贅沢に取ったので、コースタイムよりは時間がかかっている。そこで荷物を置かしてもらい、会津駒ヶ岳に登る。登頂したのは9時30分。山頂には、記念写真を撮影する行列ができている。何しろ天気が素晴らしく、眺めも最高なので、中門岳にまで足を伸ばす。中門岳までのルートは木道で、ほぼ平ら。ただ、この木道は滑ることで有名。私は、そうじゃなくても滑りやすいので、十二分に注意をしながら歩を進める。中門岳の手前に中門大池がある。まるで鏡のように空模様を移している。会津駒ヶ岳から中門岳までは、ワイルドフラワーで有名らしいが、この紅葉の季節でも、周りの山々を展望しながら湿原を歩くのは、空中散歩のようで大変気持ちがよい。というか、このルートこそ会津駒ヶ岳登山のハイライトなのではないかと思ったぐらいだ。

<会津駒ヶ岳の山頂からは見事な燧ヶ岳を見ることができる>

<会津駒ヶ岳の山頂>

<山頂から中門岳への湿原を通る道は、空中散歩のようでとても爽快だ>

<中門大池>

<中門岳からは360度の見事な展望が得られる>

<中門岳と会津駒ヶ岳を結ぶ道から燧ヶ岳の素晴らしい山容を望む>

<この看板は怖い!しかし、無事に滑らずに往復することができた>

<駒の小屋周辺からの展望。紅葉が彩るランドスケープが美しい>

<駒の小屋のすぐそばの展望>
さて、12時には駒の小屋に戻り、そこで昼食。今回の昼食はみな、カップ麺系。そのために三人分の水を運んだので、結構、重かったがそれから解放されて、帰りはちょっと荷物が軽くなった。12時50分に小屋を発つ。その後、ほぼ休憩なしのピッチで下り、14時40分には登山口に到着する。天気がよくて、登山道もあまりすべらずに戻ることができたが、雨の後とかは相当、滑りやすそうな泥道なので、留意することが必要であろう。
その後、近くの温泉で汗を流し、16時頃に帰路につく。紅葉シーズンの晴天日の登山は、本当に素晴らしいことを再確認。足が動くうちは、一年に最低でも一回は観に行きたい。
登山道整備度 ★★★★☆(しっかりと整備されており、歩きやすい。ただ、雨が降った後などはぬかるみができるであろう。駒の小屋近くや、山頂付近は木道が整備されている)
岩場度 ☆☆☆☆☆(岩場はない)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (晴れていたので気にならなかったが、雨だと登山口からちょっと先まではぬかるみで歩きにくいかもしれない)
虫うっとうしい度 ☆☆☆☆☆ (10月中旬ということもあるが、虫はまったく気にならなかった)
展望度 ★★★★★ (会津駒ヶ岳山頂から中門岳までは空中散歩のよう)
駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (最後のスポットに駐められたのはラッキーだったが、駐められないと国道の駐車場に駐めることとなる)
トイレ充実度 ★★☆☆☆ (駒ヶ岳山荘にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★★★★★ (登山口のそばに温泉がある)
安全度 ★★★★☆ (一部、木道が滑りやすいが気をつけて歩けば大丈夫。特に危険なところはない)
五竜岳(百名山56座登頂) [日本百名山]
五竜岳にチャレンジする。前日は五竜のゴンドラ駅のそばのアムルというペンションに泊まったのだが、ここが施設もよく、食事もよく、そして何よりコスパがよく、とてもいいペンションであった。幸先がよい。
さて、ゴンドラは8時15分から営業する。8時頃には切符売り場で待ち、4組目ぐらいで乗ることができた。ゴンドラで一挙に標高を稼ぐ。さらにリフトにも乗ると、スタート地点は1673メートルだ。ここの出発時間は8時50分である。リフトの終点付近は高山植物園となっており、そこから小遠見山はハイキング・ルートにもなっていて登山道は極めてよく整備されており、歩きやすい。しかし、階段もあるなど高さはしっかりと稼いでいく。天気も素晴らしく、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳が目の前に屹立している。素晴らしい景観に圧倒されると同時に、至福感を覚える。なぜ、素晴らしい景観をみると、至福感を覚えるかは不思議ではあるが、この日、ここに自分がいることが嬉しい。小遠見山は10時10分に到着。小遠見山からは360度の展望が得られるようだが、そこはスキップする。ここからは、本格的な登山道となる。ここから大遠見山までは歩きやすいが、狭い尾根を歩くので、足の踏み外しには気をつけないといけない。また、せっかく登ったのに下りもあったりして、そういう点では足への負担は大きい。大遠見山に着く頃ぐらいに、太股がピキキっときて、攣りそうになる。相変わらず、太股の筋肉は弱い。痙攣してしまうと、復活するのに時間がかかるので、だましだましで高さを稼ぐようにする。大遠見山に到着したのは11時30分。ここでおにぎり等昼食を摂る。そこから階段のような斜面を登ると西遠見ノ池がある、ちょっとした広場となる。ここからの展望はまさに絶景で、五竜岳の圧倒的な存在感に感服すると同時に、本当にこれに登れるのか、という不安な気持ちも湧く。これからは岩場と鎖場が続くということで、ストックをしまい、両手を使って登っていく。西遠見山から五竜山荘までは、これまでとは違って、本格的な登山道だ。一歩、一歩、慎重に進んでいく。岩稜登りなので、ルートには気をつけなくてはならない。幾つかの鎖場と階段を登っていくと、五竜山荘の赤い屋根が見える。ようやく着いたと喜んだのも束の間、五竜山荘に行くには一度、白岳に登り、そこから降りていかなくてはならないことを知る。身体は相当、疲れているので、こういうのはドッと疲れが増す。とはいえ、気力で白岳まで登る。白岳からは360度の展望が得られて、心が軽くなる。疲れも吹っ飛ぶような感じだ。とはいえ、慎重に五竜山荘まで降りていく。五竜山荘に到着したのは13時30分。
チェックインをして荷物を置き、少し、休んでから14時15分に五竜岳にチャレンジする。五竜山荘には往復するのに2時間以上はかかるので注意、と記した看板が設置されている。山荘と山頂の標高差は300メートル以上。山荘からの登山道はずっと岩稜歩きだ。ペンキでの印がなければ、どこを歩いていいか分からないような岩の世界である。まるで、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンド「イエス」のアルバム『リレイヤー』のカバーのような世界である。って、何を言っているか分からない人は分からないだろうが。
この山頂までの登山は結構、激しいのと、急斜面を横断するので、足下には気をつけなくてはならない。あと、途中からは登山というよりかはロッククライミングのような感じにもなるので、両手を使って登っていくような感じとなる。また、偽五竜岳のようなものが幾つかあって、ようやく着いたか、と安心すると何度も裏切られる。疲れていて、太股がピキキっと頻繁に来る中、なかなかこれは堪える。とはいえ、出口のないトンネルはない、ということで、ようやく山頂に着く。15時40分ということでコースタイムの1時間よりも遙かに時間はかかった。山頂は雲に覆われたり、晴れたりしたが、晴れた時は立山から剱が見えて素晴らしい展望が得られる。風も強くなく、まるで天国に来たかのような気分で、20分間ほどボーッとその場所にいる。16時になったので、山荘へ戻る。この帰路も岩稜を降りていくので気をつけなくてはならない。山荘に戻ったのは16時45分。
五竜山荘は、オールド・ファッションの山荘であり、満室であるところのキャンセルでぎりぎり来られたのだが、なぜか2階の部屋は我々二人で独占できた。コロナで定員を随分と絞っているということか。食事は第二クルーの17時40分から。カレーとコロッケなど。ご飯とお味噌汁はおかわり自由。カレーは美味しいと評判だったが、ごくふつうのカレー。まあ、山小屋で食べる料理はなんか、だいたい美味しく思えるから。個人的にはお味噌汁は嬉しく、これはおかわりをした。疲労困憊だったのか、18時30分にはもう爆睡をしてしまった。
2日目は3時30分起き。いろいろと準備をして、5時ちょっと前に朝食の席に着く。五竜山荘、朝食もなかなかボリュームがあり、ご飯とお味噌汁をおかわりできるので、ここでカロリーはバッチリ取ることができる。小屋を出たのは5時35分。小雨でレインコートを着ざるを得ない。白岳から西遠見までは、鎖場の連続で、どうもここでの事故が一番、多いらしい。ということで、丁寧に降りていく。西遠見に着いたのは7時ちょうど。それからは比較的楽な下りである。昨日、見えた絶景は、今日はまったく見えず、ガスの中を歩いて行く。ただ狭い尾根になっている部分もあるので、注意して歩いて行かないといけない。大遠見に着いたのは7時35分、中遠見に着いたのは8時5分。ここで10分ほど休憩して、小遠見に着いたのは8時35分。そして、リフトの上の駅に着いたのが9時15分。その後、リフトに乗ってもよかったのだが、歩いてゴンドラの頂上駅まで行く。これは10分ぐらいかかって、ゴンドラの頂上に着いたのは9時25分であった。4時間をぎりぎりきったかな、という感じである。五竜山荘から西遠見までは厳しかったが、それ以外は登りに比べると、下りは楽であった。温泉は五竜スキー場周辺が営業していないこともあり、八方温泉にて入る。

<ロープウェイから白馬市の方面を望む>

<ゴンドラの山頂周辺は高山植物園となっている>

<登山道は尾根道なので素晴らしい展望を得ることができる>

<登山道から望む五龍岳と唐松岳>

<登山道から鹿島槍ヶ岳を望む>

<五竜山荘が見えるが、そこに行くためには白岳に登り、降りていかなくてはならない>

<白岳から五竜岳と五竜山荘を望む>

<五竜山荘から東側方面を望む>


<五竜山荘から五竜岳への登山道は、ひたすら岩稜を登っていく感じで、ロッククライミングのようなものだ>

<五竜岳の山頂>

<山頂からは立山連峰、剣山を望める。今回は一眼レフは重いので持参せず、ゴープロでの撮影になってしまったため、広角すぎてその素晴らしさを写真で表現できないのは残念>

<山頂は雲海の上で、天国にいるかのような快適な気分にさせられる>
登山道整備度 ★★★★☆(小遠見岳まではハイキング・ルート・コースでもあるので、相当しっかりと整備されている。それ以降も西遠見までは細い尾根を注意すれば大丈夫であろう。西遠見から五竜山荘、五週山荘から山頂までは岩場なので、整備されているとは言いにくいが注意すれば登れる)
岩場度 ★★★★☆(西遠見からは山頂まで急斜面の岩場の連続)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (ぬかるみがないとは言えないが、気にするほどではなかった)
虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (西遠見で休憩していると蚊のような虫が大量にやってきたが、特に刺されたりはしなかった)
展望度 ★★★★★ (天国にいるかのような展望が山頂からは得られる。登山道も尾根道なので白馬連峰を眺めながら、快適な登山を楽しむことができる)
駐車場アクセス度 ★★★★★ (ロープウェイの駐車場はアクセスが極めて容易)
トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口と山荘にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (ロープウェイの駅にも温泉はある)
安全度 ★★☆☆☆ (長丁場であるのと西遠見から山頂までの岩場は落石等気をつけるスポットが多い。また、狭い尾根なので足を滑らせないことにも注意が必要だ)
さて、ゴンドラは8時15分から営業する。8時頃には切符売り場で待ち、4組目ぐらいで乗ることができた。ゴンドラで一挙に標高を稼ぐ。さらにリフトにも乗ると、スタート地点は1673メートルだ。ここの出発時間は8時50分である。リフトの終点付近は高山植物園となっており、そこから小遠見山はハイキング・ルートにもなっていて登山道は極めてよく整備されており、歩きやすい。しかし、階段もあるなど高さはしっかりと稼いでいく。天気も素晴らしく、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、唐松岳が目の前に屹立している。素晴らしい景観に圧倒されると同時に、至福感を覚える。なぜ、素晴らしい景観をみると、至福感を覚えるかは不思議ではあるが、この日、ここに自分がいることが嬉しい。小遠見山は10時10分に到着。小遠見山からは360度の展望が得られるようだが、そこはスキップする。ここからは、本格的な登山道となる。ここから大遠見山までは歩きやすいが、狭い尾根を歩くので、足の踏み外しには気をつけないといけない。また、せっかく登ったのに下りもあったりして、そういう点では足への負担は大きい。大遠見山に着く頃ぐらいに、太股がピキキっときて、攣りそうになる。相変わらず、太股の筋肉は弱い。痙攣してしまうと、復活するのに時間がかかるので、だましだましで高さを稼ぐようにする。大遠見山に到着したのは11時30分。ここでおにぎり等昼食を摂る。そこから階段のような斜面を登ると西遠見ノ池がある、ちょっとした広場となる。ここからの展望はまさに絶景で、五竜岳の圧倒的な存在感に感服すると同時に、本当にこれに登れるのか、という不安な気持ちも湧く。これからは岩場と鎖場が続くということで、ストックをしまい、両手を使って登っていく。西遠見山から五竜山荘までは、これまでとは違って、本格的な登山道だ。一歩、一歩、慎重に進んでいく。岩稜登りなので、ルートには気をつけなくてはならない。幾つかの鎖場と階段を登っていくと、五竜山荘の赤い屋根が見える。ようやく着いたと喜んだのも束の間、五竜山荘に行くには一度、白岳に登り、そこから降りていかなくてはならないことを知る。身体は相当、疲れているので、こういうのはドッと疲れが増す。とはいえ、気力で白岳まで登る。白岳からは360度の展望が得られて、心が軽くなる。疲れも吹っ飛ぶような感じだ。とはいえ、慎重に五竜山荘まで降りていく。五竜山荘に到着したのは13時30分。
チェックインをして荷物を置き、少し、休んでから14時15分に五竜岳にチャレンジする。五竜山荘には往復するのに2時間以上はかかるので注意、と記した看板が設置されている。山荘と山頂の標高差は300メートル以上。山荘からの登山道はずっと岩稜歩きだ。ペンキでの印がなければ、どこを歩いていいか分からないような岩の世界である。まるで、イギリスのプログレッシブ・ロック・バンド「イエス」のアルバム『リレイヤー』のカバーのような世界である。って、何を言っているか分からない人は分からないだろうが。
この山頂までの登山は結構、激しいのと、急斜面を横断するので、足下には気をつけなくてはならない。あと、途中からは登山というよりかはロッククライミングのような感じにもなるので、両手を使って登っていくような感じとなる。また、偽五竜岳のようなものが幾つかあって、ようやく着いたか、と安心すると何度も裏切られる。疲れていて、太股がピキキっと頻繁に来る中、なかなかこれは堪える。とはいえ、出口のないトンネルはない、ということで、ようやく山頂に着く。15時40分ということでコースタイムの1時間よりも遙かに時間はかかった。山頂は雲に覆われたり、晴れたりしたが、晴れた時は立山から剱が見えて素晴らしい展望が得られる。風も強くなく、まるで天国に来たかのような気分で、20分間ほどボーッとその場所にいる。16時になったので、山荘へ戻る。この帰路も岩稜を降りていくので気をつけなくてはならない。山荘に戻ったのは16時45分。
五竜山荘は、オールド・ファッションの山荘であり、満室であるところのキャンセルでぎりぎり来られたのだが、なぜか2階の部屋は我々二人で独占できた。コロナで定員を随分と絞っているということか。食事は第二クルーの17時40分から。カレーとコロッケなど。ご飯とお味噌汁はおかわり自由。カレーは美味しいと評判だったが、ごくふつうのカレー。まあ、山小屋で食べる料理はなんか、だいたい美味しく思えるから。個人的にはお味噌汁は嬉しく、これはおかわりをした。疲労困憊だったのか、18時30分にはもう爆睡をしてしまった。
2日目は3時30分起き。いろいろと準備をして、5時ちょっと前に朝食の席に着く。五竜山荘、朝食もなかなかボリュームがあり、ご飯とお味噌汁をおかわりできるので、ここでカロリーはバッチリ取ることができる。小屋を出たのは5時35分。小雨でレインコートを着ざるを得ない。白岳から西遠見までは、鎖場の連続で、どうもここでの事故が一番、多いらしい。ということで、丁寧に降りていく。西遠見に着いたのは7時ちょうど。それからは比較的楽な下りである。昨日、見えた絶景は、今日はまったく見えず、ガスの中を歩いて行く。ただ狭い尾根になっている部分もあるので、注意して歩いて行かないといけない。大遠見に着いたのは7時35分、中遠見に着いたのは8時5分。ここで10分ほど休憩して、小遠見に着いたのは8時35分。そして、リフトの上の駅に着いたのが9時15分。その後、リフトに乗ってもよかったのだが、歩いてゴンドラの頂上駅まで行く。これは10分ぐらいかかって、ゴンドラの頂上に着いたのは9時25分であった。4時間をぎりぎりきったかな、という感じである。五竜山荘から西遠見までは厳しかったが、それ以外は登りに比べると、下りは楽であった。温泉は五竜スキー場周辺が営業していないこともあり、八方温泉にて入る。

<ロープウェイから白馬市の方面を望む>

<ゴンドラの山頂周辺は高山植物園となっている>

<登山道は尾根道なので素晴らしい展望を得ることができる>

<登山道から望む五龍岳と唐松岳>

<登山道から鹿島槍ヶ岳を望む>

<五竜山荘が見えるが、そこに行くためには白岳に登り、降りていかなくてはならない>

<白岳から五竜岳と五竜山荘を望む>

<五竜山荘から東側方面を望む>


<五竜山荘から五竜岳への登山道は、ひたすら岩稜を登っていく感じで、ロッククライミングのようなものだ>

<五竜岳の山頂>

<山頂からは立山連峰、剣山を望める。今回は一眼レフは重いので持参せず、ゴープロでの撮影になってしまったため、広角すぎてその素晴らしさを写真で表現できないのは残念>

<山頂は雲海の上で、天国にいるかのような快適な気分にさせられる>
登山道整備度 ★★★★☆(小遠見岳まではハイキング・ルート・コースでもあるので、相当しっかりと整備されている。それ以降も西遠見までは細い尾根を注意すれば大丈夫であろう。西遠見から五竜山荘、五週山荘から山頂までは岩場なので、整備されているとは言いにくいが注意すれば登れる)
岩場度 ★★★★☆(西遠見からは山頂まで急斜面の岩場の連続)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (ぬかるみがないとは言えないが、気にするほどではなかった)
虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (西遠見で休憩していると蚊のような虫が大量にやってきたが、特に刺されたりはしなかった)
展望度 ★★★★★ (天国にいるかのような展望が山頂からは得られる。登山道も尾根道なので白馬連峰を眺めながら、快適な登山を楽しむことができる)
駐車場アクセス度 ★★★★★ (ロープウェイの駐車場はアクセスが極めて容易)
トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口と山荘にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★★★★☆ (ロープウェイの駅にも温泉はある)
安全度 ★★☆☆☆ (長丁場であるのと西遠見から山頂までの岩場は落石等気をつけるスポットが多い。また、狭い尾根なので足を滑らせないことにも注意が必要だ)
阿蘇山(日本百名山55座登頂) [日本百名山]
九州に行く機会があったので阿蘇山にチャレンジする。これまでも九州に行くたびにそのチャレンジを考えていたのだが、噴火警戒レベルが2であるので諦めていた。しかし、2021年10月にそのレベルが1になったので、今回も阿蘇山へのチャレンジを試みた。
伊丹空港から阿蘇熊本空港まで飛び、空港そばのリゾート・ホテルに泊まる。翌日は8時からホテルと空港を結ぶヴァンに乗せてもらい、レンタカー事務所で降ろしてもらう。そして、クルマを借りてまずは阿蘇火口に向かう。さて、しかし、阿蘇山上ターミナルで道は通行不可になっており、火口まで行けることができなかった。そうすると砂千里ヶ浜経由でチャレンジすることになるが、これだと私の登山マップだと130分。仙酔峡経由だとすずめ岩迂回ルートで90分なのと、また、こちらは天候が悪かったので、クルマで仙酔峡まで向かう。
途中、コンビニで朝食を取ったりしたこともあり、仙酔峡に着いたのは10時15分頃。ただ、この時、強い雨が降り始め、これは登山自体も諦めるかという気持ちが強くなる。しっかりとした登山の準備をしていなかったということもある。しかし、しばらくすると雨は降り止み、また状況がひどくなれば戻ればいいかという気持ちで10時20分頃から歩き始める。最初は仙酔尾根コースを取ることも考えたが、昨年、すずめ岩迂回ルートを再整備したというちらしをみたので、ここは迷わず、そちらのコースを取る。結果的に、これが大正解であることを下山時に知ることになる。
すずめ岩の分岐点までは、視界も広がり快調。歩道もしっかりと整備されていて、大変歩きやすい。また、50メートルごとに標識が立っており、自分のリズムをキープするうえでとても役立つ。こういう情報によって、本当、歩くインセンティブが増す。
分岐点からは、登山道は整備されていないのだが、岩にペンキでルートが示されているので、注意をしていれば迷うことはない。このルートも新しく整備されたため、標識がしっかりと配置されていて、安心だ。ここらへんからは霧雨になり、たまに雨雲も通る。そのような時は傘を差してやり過ごす。そんな感じで中岳に登頂する。時間は12時ちょうど。ほぼコース・タイム通りである。
残念ながら中岳からの展望はほぼゼロ。さて、ここから高岳までは20分ぐらい。風は相当、厳しいが雨が止んだこともあり、また高岳から仙酔尾根ルートを下った方が早く戻れると考え、濃霧の中、高岳まで向かう。高岳までのルートはまったく問題なく登れる。ここでも展望はゼロ。最近、山頂からの展望に恵まれていない。
さて、そこから仙酔尾根ルートを下り始めたのだが、いきなり急斜面のガレ場。これは結構、危ない。ということで慎重に慎重を重ねて下っていく。ほとんど登山道というか「道」のようなものはない状況だ。いや、この厳しさはまったく想定外だ。この厳しさはしかもずっと続く。ここを登らなくてよかったと思うと同時に、降りなくてもよかったなと後悔する。しかし、流石に戻るのは遠回りだろう、ということで降り続ける。ほとんど岩下りであり、手を使わないと厳しい。膝には結構、負担が大きいような急斜面だ。これは、ほぼずっと続く。さて、駐車場が近づき、ようやくレキから開放されたかと思ったら、そこは草が生い茂った道であった。草が生い茂っていて足下が見えないが、岩とかがゴロゴロしているので下手したら躓く。斜面も急なのでこれは躓いたら結構、怪我をする確率が高い。というか、もうちょっと整備して欲しい。ほとんど藪漕ぎのような感じで、駐車場に戻る。
そんな感じだったので、コース・タイムを大きく上回った。というか、このコース・タイム、ウサギのコース・タイムかとちょっと疑う。ガレのところをぴょんぴょんと岩を飛ぶように降りないとこの時間では下れないであろう。
展望は麓の方でしか得られなかったが、改めて阿蘇の雄大な自然は、日本一かと思う。多くの人は北海道こそ雄大なランドスケープだと考えているように思うが、個人的には阿蘇の雄大さには劣ると思う。これは、日本だけでなく、世界にも通じる迫力である。仙酔尾根は二度と登りたい(下りたい)とは思わないが、すずめ岩ルートであれば、また晴れた日に機会があれば是非とも再訪してみたい。

(駐車場から元ロープウェイの索道に沿って登っていく歩道は気持ちがよいほど整備されている)

(標識がしっかりと整備されているので、安心して自分のペースを保ちながら歩いて行ける)

(渓谷を流れる川もしっかりと硫黄分を含んだ水で濁っている。ただ、温かくはなかった)

(中岳に登るまでのルートは最近、整備されたということもあり急登、ガレであっても歩きやすい)

(中岳の山頂。展望は得られなかった)

(中岳から高岳とを結ぶ尾根道。おそらく凄い展望が得られるのであろうが、残念ながら濃霧で何も見えず)

(大岳の山頂。展望は得られなかった)

(仙酔尾根の入り口)

(仙酔尾根は急登のガレ。これは厳しい)

(もう登山かロッククライミングか分からないほどの急登)

(岩にペンキで印がつけられていなければ、どこが登山道かはまったく分からない)

(とはいえ、周辺の景色はすごいものがあり、まあ、この景色が登山のつらさを多少、慰めてくれる)

(ガレの急登がようやく終わったと思ったら、すさまじい藪が登山道を塞いでいる。この先はさらにひどくなり、ほとんど藪漕ぎ)
登山道整備度 ★★★★☆(すずめ岩ルート) ★☆☆☆☆(仙酔尾根ルート) (すずめ岩ルートは比較的よく整備されていて、歩きやすい。一方、仙酔尾根ルートは藪こぎのようなところもあり、また急なガレの連続でお勧めできない)
岩場度 ★★☆☆☆(すずめ岩ルート) ★★★★★(仙酔尾根ルート)(すずめ岩ルートはちょっとした岩場はあるがそれぐらい。仙酔尾根ルートは急斜面の岩場が8割ぐらいのイメージ)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (すずめ岩ルートはぬかるみはまったくない。仙酔尾根ルートは下の方に一部、ぬかるみのところがある)
虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫はほぼいなかった)
展望度 N/A (素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られなかったので評価できず)
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)
トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (阿蘇山なのでいろいろとありそうだが、内牧温泉まで行き、そこの個人経営の温泉に浸かる。もう少し調べればいいところがあるかもしれない)
安全度 ★★★☆☆ (すずめ岩ルートであれば、山頂まで登山道は比較的しっかりと整備されているが、仙酔尾根ルートは登山ルートも分かりづらく、注意した方がいい)
伊丹空港から阿蘇熊本空港まで飛び、空港そばのリゾート・ホテルに泊まる。翌日は8時からホテルと空港を結ぶヴァンに乗せてもらい、レンタカー事務所で降ろしてもらう。そして、クルマを借りてまずは阿蘇火口に向かう。さて、しかし、阿蘇山上ターミナルで道は通行不可になっており、火口まで行けることができなかった。そうすると砂千里ヶ浜経由でチャレンジすることになるが、これだと私の登山マップだと130分。仙酔峡経由だとすずめ岩迂回ルートで90分なのと、また、こちらは天候が悪かったので、クルマで仙酔峡まで向かう。
途中、コンビニで朝食を取ったりしたこともあり、仙酔峡に着いたのは10時15分頃。ただ、この時、強い雨が降り始め、これは登山自体も諦めるかという気持ちが強くなる。しっかりとした登山の準備をしていなかったということもある。しかし、しばらくすると雨は降り止み、また状況がひどくなれば戻ればいいかという気持ちで10時20分頃から歩き始める。最初は仙酔尾根コースを取ることも考えたが、昨年、すずめ岩迂回ルートを再整備したというちらしをみたので、ここは迷わず、そちらのコースを取る。結果的に、これが大正解であることを下山時に知ることになる。
すずめ岩の分岐点までは、視界も広がり快調。歩道もしっかりと整備されていて、大変歩きやすい。また、50メートルごとに標識が立っており、自分のリズムをキープするうえでとても役立つ。こういう情報によって、本当、歩くインセンティブが増す。
分岐点からは、登山道は整備されていないのだが、岩にペンキでルートが示されているので、注意をしていれば迷うことはない。このルートも新しく整備されたため、標識がしっかりと配置されていて、安心だ。ここらへんからは霧雨になり、たまに雨雲も通る。そのような時は傘を差してやり過ごす。そんな感じで中岳に登頂する。時間は12時ちょうど。ほぼコース・タイム通りである。
残念ながら中岳からの展望はほぼゼロ。さて、ここから高岳までは20分ぐらい。風は相当、厳しいが雨が止んだこともあり、また高岳から仙酔尾根ルートを下った方が早く戻れると考え、濃霧の中、高岳まで向かう。高岳までのルートはまったく問題なく登れる。ここでも展望はゼロ。最近、山頂からの展望に恵まれていない。
さて、そこから仙酔尾根ルートを下り始めたのだが、いきなり急斜面のガレ場。これは結構、危ない。ということで慎重に慎重を重ねて下っていく。ほとんど登山道というか「道」のようなものはない状況だ。いや、この厳しさはまったく想定外だ。この厳しさはしかもずっと続く。ここを登らなくてよかったと思うと同時に、降りなくてもよかったなと後悔する。しかし、流石に戻るのは遠回りだろう、ということで降り続ける。ほとんど岩下りであり、手を使わないと厳しい。膝には結構、負担が大きいような急斜面だ。これは、ほぼずっと続く。さて、駐車場が近づき、ようやくレキから開放されたかと思ったら、そこは草が生い茂った道であった。草が生い茂っていて足下が見えないが、岩とかがゴロゴロしているので下手したら躓く。斜面も急なのでこれは躓いたら結構、怪我をする確率が高い。というか、もうちょっと整備して欲しい。ほとんど藪漕ぎのような感じで、駐車場に戻る。
そんな感じだったので、コース・タイムを大きく上回った。というか、このコース・タイム、ウサギのコース・タイムかとちょっと疑う。ガレのところをぴょんぴょんと岩を飛ぶように降りないとこの時間では下れないであろう。
展望は麓の方でしか得られなかったが、改めて阿蘇の雄大な自然は、日本一かと思う。多くの人は北海道こそ雄大なランドスケープだと考えているように思うが、個人的には阿蘇の雄大さには劣ると思う。これは、日本だけでなく、世界にも通じる迫力である。仙酔尾根は二度と登りたい(下りたい)とは思わないが、すずめ岩ルートであれば、また晴れた日に機会があれば是非とも再訪してみたい。

(駐車場から元ロープウェイの索道に沿って登っていく歩道は気持ちがよいほど整備されている)

(標識がしっかりと整備されているので、安心して自分のペースを保ちながら歩いて行ける)

(渓谷を流れる川もしっかりと硫黄分を含んだ水で濁っている。ただ、温かくはなかった)

(中岳に登るまでのルートは最近、整備されたということもあり急登、ガレであっても歩きやすい)

(中岳の山頂。展望は得られなかった)

(中岳から高岳とを結ぶ尾根道。おそらく凄い展望が得られるのであろうが、残念ながら濃霧で何も見えず)

(大岳の山頂。展望は得られなかった)

(仙酔尾根の入り口)

(仙酔尾根は急登のガレ。これは厳しい)

(もう登山かロッククライミングか分からないほどの急登)

(岩にペンキで印がつけられていなければ、どこが登山道かはまったく分からない)

(とはいえ、周辺の景色はすごいものがあり、まあ、この景色が登山のつらさを多少、慰めてくれる)

(ガレの急登がようやく終わったと思ったら、すさまじい藪が登山道を塞いでいる。この先はさらにひどくなり、ほとんど藪漕ぎ)
登山道整備度 ★★★★☆(すずめ岩ルート) ★☆☆☆☆(仙酔尾根ルート) (すずめ岩ルートは比較的よく整備されていて、歩きやすい。一方、仙酔尾根ルートは藪こぎのようなところもあり、また急なガレの連続でお勧めできない)
岩場度 ★★☆☆☆(すずめ岩ルート) ★★★★★(仙酔尾根ルート)(すずめ岩ルートはちょっとした岩場はあるがそれぐらい。仙酔尾根ルートは急斜面の岩場が8割ぐらいのイメージ)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (すずめ岩ルートはぬかるみはまったくない。仙酔尾根ルートは下の方に一部、ぬかるみのところがある)
虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫はほぼいなかった)
展望度 N/A (素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られなかったので評価できず)
駐車場アクセス度 ★★★★★ (駐車場への道はしっかりと整備されている)
トイレ充実度 ★★☆☆☆ (登山道の入り口にはしっかりとトイレがある)
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (阿蘇山なのでいろいろとありそうだが、内牧温泉まで行き、そこの個人経営の温泉に浸かる。もう少し調べればいいところがあるかもしれない)
安全度 ★★★☆☆ (すずめ岩ルートであれば、山頂まで登山道は比較的しっかりと整備されているが、仙酔尾根ルートは登山ルートも分かりづらく、注意した方がいい)
白山(日本百名山54座登頂) [日本百名山]
7月の土曜日と日曜日にかけて一泊二日で白山にチャレンジする。金曜日の夜に京都を発ち、勝山のホテルで一泊。そこから市が瀬の駐車場まで1時間弱ぐらい。ホテルを出たのが8時頃であったので、市が瀬駐車場に到着したのは9時ちょっと前。連休の金曜日ということで、駐車場が埋まっていることを懸念したが、しっかりとバス停のそばの駐車場に停まることができた。9時発のバスに乗って、20分弱で別当分岐の登山口に着く。別当出合から室堂までは観光新道、砂防新道と二つの選択肢が大きくあるが、最近、観光新道は登山道が崩れたということもあり、砂防新道を選ぶ。
登山口からすぐ、長大な吊り橋を歩く。日本一長い、というような説明板があったが綾町にある吊り橋の方が長いと思う。何かの条件付きでの長さであろう。それは、ともかく、登山を開始してすぐ、このような吊り橋を渡るというのは、象徴的効果があってよい。鳥居をくぐるようなものか。

<登山直後にこの吊り橋を渡る。この劇的な演出は素晴らしい>
さて、登山開始後、急登というようなガイドブックの説明があったが、それほど急ではなく、しかも登山道はしっかりと整備されているのでとても歩きやすい。ここらへん、人気のある山ということもあるが、霊山であることも大きいのであろう。そういえば、御岳とかもとても歩きやすかった。前日は雨が降ったと思われるが、ぬかるみがない。ぬかるみがない登山道は本当、歩きやすくて楽しい。天気も上の方には雲もあるが、快適だ。霊山であるので原生林が保全されていることもあり、緑が美しい。本当、登山をしていると植林の森と原生林の美しさの違いがはっきりと分かって面白い。原生林の美しさは生態系の美しさでもある。

<原生林の中を歩く登山は気持ちいい>

<砂防新道は、登山道の横を砂防ダムが続く渓流が流れているからだろうか?>
中飯場に着いたのは10時10分。ほぼコースタイム通りだ。少々、休憩をして再び、歩き始める。階段をずっと登って行く感じで結構、厳しいが、道はよく整備されているので本当、歩きやすい。甚ノ助避難小屋に着いたのは11時45分。これもほぼコースタイム通りだ。ただ、甚ノ助避難小屋に到着する寸前ぐらいで太股が攣りそうになる。まあ、久しぶりの登山なので致し方ないが、ちょっとこれからまだ先が長いので不安になる。

<坂道は急だが、しっかりと登山道が整備されているので、とても歩きやすい>
甚ノ助避難小屋では水を補給。砂防新道、水場が多いので本当、嬉しい。水は結構、重いので大量に持ってこなくていいのは助かる。甚ノ助避難小屋からは大日山の方角の山々が展望できる。こういう雄大な光景をみると疲れが飛ぶ。ここで、朝、コンビニで買ったおにぎりを二つほど頬張る。日帰り登山ではなく、一泊だと食事が少なくて済むのが楽だ。特にガスボンベや食器類をもってこなくてもいいのは有り難い。

<甚ノ助避難小屋には水場だけでなく、トイレもある>
さて、それから分岐点までは太股が超絶、張っているのでゆっくりと歩いたこともあり、コースタイムを大幅に上回って12時30分に到着する。この頃になると、空も灰色になってきて、天気が崩れそうな予感もする。ここから黒ボコ岩までは、展望が開ける気持ちが晴れる登山道だ。急坂ではあるが、ワイルドフラワーが咲き乱れ、それらが沿道でマラソン・ランナーを応援する応援団のように見えてきて、力をもらえる。しかし、疲れ過ぎていて、それらを写真に収めるほどの体力は出てこない。

<分岐点の周辺からは素晴らしい展望を得ることができる>


<花の名山と呼ばれるだけあって、ワイルドフラワーが登山道の周辺でも咲き乱れていて、目と心が癒やされる>


<分岐点から黒ボコ岩にかけては、坂は急ではあるが、登山道もしっかりとしていて歩きやすく、周辺の景色も素晴らしく、登山の楽しさを感じることができる>
黒ボコ岩に到着したのは、13時30分。これもコースタイムをちょっとオーバーしている。黒ボコ岩には、大きな岩がごろごろしているのだが、これは火砕流によって山頂から運ばれてきた火山弾だそうだ。いや、白山って、実は活火山であったりするし、本当、日本列島は火山列島ということを、改めて痛感させられる(って、山に登るたびに認識を新たにさせられるのだが)。こんな火山列島に原発はあり得ない、という思いもここに新たにする。本当、原発推進派は山、登るといいと強く思う。

<黒ボコ岩をはじめ、周辺の巨岩はなかなかの迫力がある>
さて、黒ボコ岩を過ぎると、広大な弥陀ヶ原の高原が広がる。高原の横には巨大な雪渓が広がる。まだ7月中旬だから、なかなかそのスケールには迫力がある。そして、目の先には白山の御前峰の山頂がみえる。相当の存在感と迫力だ。この高原は木道がしっかりと整備されていて、高低差もほとんどなく歩いてきて、本当に気持ちがよい。さて、しかし、弥陀ヶ原から室堂まではまた坂になる。大して厳しくはないが、疲れた身体にはまあまあ堪える。そして室堂に14時15分に到着。ほぼ5時間弱か。

<弥陀ヶ原の高原からは、周辺の山々を広く展望することができる>

<弥陀ヶ原から御前峰を展望する>

<弥陀ヶ原は木道でしっかりと整備された道を歩いて行く。気持ちがよい>
室堂に荷物を置いて、軽い格好で御前峰にチャレンジ。室堂からは40分とそばなのだが、登っている途中で急に天候が悪化。雨も降り始めたので、諦めて室堂に戻る。これは正解であった。というのも、室堂に着いたころには豪雨になっていたからだ。室堂でチェックインをする。チェックインの順番で男女問わず、雑魚寝という話であったが、それほど宿泊客がいなかったようで、私は二人用の個室空間を独り占め。しかも、中高年の男性ばかりが同室であり、どうもしっかりと部屋分けもされているようだ。ということで、最初は、もう、サーディンのような状況を覚悟していたのに、結果的には、これまでの山小屋経験でも相当、快適な滞在をすることができた。

<室堂はしっかりとした宿泊施設である>

<室堂のすぐそばに立地し、御前峰への登山道がある白山神社>

<室堂の部屋は快適であった。プライバシーもめちゃくちゃ確保できている>
夕食は17時。食事はおかずの違いで二つの選択肢がある。魚とハンバーグ。どちらも美味しそうではないが、ハンバーグ。とはいえ、こうやって温かい食事を摂ることができるのは本当、有り難い。生ビールも飲み、すぐに就寝。

<室堂の夕食。こういう温かい食事が取れるのは有り難い>
翌日は午前12時頃に起きる。それから寝られず、ずっとシーツの中でもぞもぞしていたが朝4時頃になり部屋の電気が点いたタイミングで起床する。朝ご飯は5時からだが、日の出は4時50分前後。周囲はガスに覆われているが、雨は降っていないので朝食前に御前山へチャレンジする。これは漫画家の塀内夏子が100名山にチャレンジした際に山小屋に泊まった時によく使った手であるが、これは相当、一理あると思う。というのは、多くの場合、山小屋は山頂の比較的そばに立地しているので、一時間ちょっとで往復できる。そうすると、日の出の時間を計算して登り始めると、6時ちょっと過ぎに山小屋に戻ってくることができ、それから朝食、パッキングするとロジ的にとても楽だからだ。
室堂から御前山まではコースタイムでは登りは40分、下りは30分。昨日、少しだけ登りかけたのでルートは分かる。そして、登山道は石でしっかりと固められており、とても歩きやすい。頂上までは何の問題もなく、行くことができた。残念ながら、ガスでほとんど何も見えなかったが、登山道沿いに多くの花が咲き乱れていて、それがちょっとしたご褒美のようだ。

<頂上はガスでほとんど何も見られなかった>
さて、室堂に降りてきて、朝食を摂る。朝食はソーセージか鯖焼きを選ぶことができる。これは、流石に鯖焼き。ほぼ夕食と同じような内容だが、梅干しが食べ放題なのでご飯をたくさん食べることができる。ここで炭水化物を摂れるのは有り難い。
そのまま、すぐ降りればいいのだが、睡眠不足なのだろうか。急に睡魔が襲ったのと、雨が降り始めたのでチェックアウトぎりぎりの8時までうたた寝をする。そして、8時頃から降り始める。御前峰はまったくその姿を見られない。ガスの中をゆっくりと降りていく。途中、雨が降ってきたので、傘を差す。こういう時は、やっぱり傘が便利だ。行き交う人々に当たらないように気をつけないといけないが。
雨が降っていたにも関わらず、登山道がぬかるみになっているところはほとんどなく、こういうのは本当、有り難い。ただ、登りの登山者が多く、しかもグループで長蛇の列をなしていくので、礼儀正しく、待っているといつまでも降りることができないことが判明。グループ客が登る際は、うまくこちらも降りられる時は、積極的に降りていかないと時間がかかってしょうがない。ここらへんは、上手い人の後ろにピタッとついていると降りられることを発見。
さて、登山口に到着したのは11時。ほぼ3時間で降りることができた。帰りは白峰温泉に入って、汗を流す。白峰温泉もなかなかよかった。
二日目の天候がよければ、さらに快適な登山になったかと思うが、それでも一日目、弥陀ヶ原から御前峰を展望できたのはよかった。私は、登山はするが、あまり登山が好きではなく、もう一度登りたいと思う山は少ないのだが、昨年、登った御岳に次いで、白山ならもう一度、チャレンジしたいなと思わせられた。
登山道整備度 ★★★★★ (山頂までしっかりと整備されていて、極めて歩きやすい。さすが霊山)
岩場度 ★☆☆☆☆ (手を使わないといけないような岩場もなく、快適な登山が楽しめる)
登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (ぬかるみはまったくといっていいほどない)
虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (虫はいないとは言わないが、煩わしいことはなかった)
展望度 ★★★★★ (独立峰なので素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られない)
駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (夏の混雑時はシャトルバスに乗らなくてはならない)
トイレ充実度 ★★★★★ (ところどころにある)
下山後の温泉充実度 ★★★☆☆ (白峰温泉はなかなかよかった)
安全度 ★★★★★ (山頂まで登山道はしっかりと整備されており、道に迷うようなところもなく、安全な登山が楽しめるであろう)
登山口からすぐ、長大な吊り橋を歩く。日本一長い、というような説明板があったが綾町にある吊り橋の方が長いと思う。何かの条件付きでの長さであろう。それは、ともかく、登山を開始してすぐ、このような吊り橋を渡るというのは、象徴的効果があってよい。鳥居をくぐるようなものか。

<登山直後にこの吊り橋を渡る。この劇的な演出は素晴らしい>
さて、登山開始後、急登というようなガイドブックの説明があったが、それほど急ではなく、しかも登山道はしっかりと整備されているのでとても歩きやすい。ここらへん、人気のある山ということもあるが、霊山であることも大きいのであろう。そういえば、御岳とかもとても歩きやすかった。前日は雨が降ったと思われるが、ぬかるみがない。ぬかるみがない登山道は本当、歩きやすくて楽しい。天気も上の方には雲もあるが、快適だ。霊山であるので原生林が保全されていることもあり、緑が美しい。本当、登山をしていると植林の森と原生林の美しさの違いがはっきりと分かって面白い。原生林の美しさは生態系の美しさでもある。

<原生林の中を歩く登山は気持ちいい>

<砂防新道は、登山道の横を砂防ダムが続く渓流が流れているからだろうか?>
中飯場に着いたのは10時10分。ほぼコースタイム通りだ。少々、休憩をして再び、歩き始める。階段をずっと登って行く感じで結構、厳しいが、道はよく整備されているので本当、歩きやすい。甚ノ助避難小屋に着いたのは11時45分。これもほぼコースタイム通りだ。ただ、甚ノ助避難小屋に到着する寸前ぐらいで太股が攣りそうになる。まあ、久しぶりの登山なので致し方ないが、ちょっとこれからまだ先が長いので不安になる。

<坂道は急だが、しっかりと登山道が整備されているので、とても歩きやすい>
甚ノ助避難小屋では水を補給。砂防新道、水場が多いので本当、嬉しい。水は結構、重いので大量に持ってこなくていいのは助かる。甚ノ助避難小屋からは大日山の方角の山々が展望できる。こういう雄大な光景をみると疲れが飛ぶ。ここで、朝、コンビニで買ったおにぎりを二つほど頬張る。日帰り登山ではなく、一泊だと食事が少なくて済むのが楽だ。特にガスボンベや食器類をもってこなくてもいいのは有り難い。

<甚ノ助避難小屋には水場だけでなく、トイレもある>
さて、それから分岐点までは太股が超絶、張っているのでゆっくりと歩いたこともあり、コースタイムを大幅に上回って12時30分に到着する。この頃になると、空も灰色になってきて、天気が崩れそうな予感もする。ここから黒ボコ岩までは、展望が開ける気持ちが晴れる登山道だ。急坂ではあるが、ワイルドフラワーが咲き乱れ、それらが沿道でマラソン・ランナーを応援する応援団のように見えてきて、力をもらえる。しかし、疲れ過ぎていて、それらを写真に収めるほどの体力は出てこない。

<分岐点の周辺からは素晴らしい展望を得ることができる>


<花の名山と呼ばれるだけあって、ワイルドフラワーが登山道の周辺でも咲き乱れていて、目と心が癒やされる>


<分岐点から黒ボコ岩にかけては、坂は急ではあるが、登山道もしっかりとしていて歩きやすく、周辺の景色も素晴らしく、登山の楽しさを感じることができる>
黒ボコ岩に到着したのは、13時30分。これもコースタイムをちょっとオーバーしている。黒ボコ岩には、大きな岩がごろごろしているのだが、これは火砕流によって山頂から運ばれてきた火山弾だそうだ。いや、白山って、実は活火山であったりするし、本当、日本列島は火山列島ということを、改めて痛感させられる(って、山に登るたびに認識を新たにさせられるのだが)。こんな火山列島に原発はあり得ない、という思いもここに新たにする。本当、原発推進派は山、登るといいと強く思う。

<黒ボコ岩をはじめ、周辺の巨岩はなかなかの迫力がある>
さて、黒ボコ岩を過ぎると、広大な弥陀ヶ原の高原が広がる。高原の横には巨大な雪渓が広がる。まだ7月中旬だから、なかなかそのスケールには迫力がある。そして、目の先には白山の御前峰の山頂がみえる。相当の存在感と迫力だ。この高原は木道がしっかりと整備されていて、高低差もほとんどなく歩いてきて、本当に気持ちがよい。さて、しかし、弥陀ヶ原から室堂まではまた坂になる。大して厳しくはないが、疲れた身体にはまあまあ堪える。そして室堂に14時15分に到着。ほぼ5時間弱か。

<弥陀ヶ原の高原からは、周辺の山々を広く展望することができる>

<弥陀ヶ原から御前峰を展望する>

<弥陀ヶ原は木道でしっかりと整備された道を歩いて行く。気持ちがよい>
室堂に荷物を置いて、軽い格好で御前峰にチャレンジ。室堂からは40分とそばなのだが、登っている途中で急に天候が悪化。雨も降り始めたので、諦めて室堂に戻る。これは正解であった。というのも、室堂に着いたころには豪雨になっていたからだ。室堂でチェックインをする。チェックインの順番で男女問わず、雑魚寝という話であったが、それほど宿泊客がいなかったようで、私は二人用の個室空間を独り占め。しかも、中高年の男性ばかりが同室であり、どうもしっかりと部屋分けもされているようだ。ということで、最初は、もう、サーディンのような状況を覚悟していたのに、結果的には、これまでの山小屋経験でも相当、快適な滞在をすることができた。

<室堂はしっかりとした宿泊施設である>

<室堂のすぐそばに立地し、御前峰への登山道がある白山神社>

<室堂の部屋は快適であった。プライバシーもめちゃくちゃ確保できている>
夕食は17時。食事はおかずの違いで二つの選択肢がある。魚とハンバーグ。どちらも美味しそうではないが、ハンバーグ。とはいえ、こうやって温かい食事を摂ることができるのは本当、有り難い。生ビールも飲み、すぐに就寝。

<室堂の夕食。こういう温かい食事が取れるのは有り難い>
翌日は午前12時頃に起きる。それから寝られず、ずっとシーツの中でもぞもぞしていたが朝4時頃になり部屋の電気が点いたタイミングで起床する。朝ご飯は5時からだが、日の出は4時50分前後。周囲はガスに覆われているが、雨は降っていないので朝食前に御前山へチャレンジする。これは漫画家の塀内夏子が100名山にチャレンジした際に山小屋に泊まった時によく使った手であるが、これは相当、一理あると思う。というのは、多くの場合、山小屋は山頂の比較的そばに立地しているので、一時間ちょっとで往復できる。そうすると、日の出の時間を計算して登り始めると、6時ちょっと過ぎに山小屋に戻ってくることができ、それから朝食、パッキングするとロジ的にとても楽だからだ。
室堂から御前山まではコースタイムでは登りは40分、下りは30分。昨日、少しだけ登りかけたのでルートは分かる。そして、登山道は石でしっかりと固められており、とても歩きやすい。頂上までは何の問題もなく、行くことができた。残念ながら、ガスでほとんど何も見えなかったが、登山道沿いに多くの花が咲き乱れていて、それがちょっとしたご褒美のようだ。

<頂上はガスでほとんど何も見られなかった>
さて、室堂に降りてきて、朝食を摂る。朝食はソーセージか鯖焼きを選ぶことができる。これは、流石に鯖焼き。ほぼ夕食と同じような内容だが、梅干しが食べ放題なのでご飯をたくさん食べることができる。ここで炭水化物を摂れるのは有り難い。
そのまま、すぐ降りればいいのだが、睡眠不足なのだろうか。急に睡魔が襲ったのと、雨が降り始めたのでチェックアウトぎりぎりの8時までうたた寝をする。そして、8時頃から降り始める。御前峰はまったくその姿を見られない。ガスの中をゆっくりと降りていく。途中、雨が降ってきたので、傘を差す。こういう時は、やっぱり傘が便利だ。行き交う人々に当たらないように気をつけないといけないが。
雨が降っていたにも関わらず、登山道がぬかるみになっているところはほとんどなく、こういうのは本当、有り難い。ただ、登りの登山者が多く、しかもグループで長蛇の列をなしていくので、礼儀正しく、待っているといつまでも降りることができないことが判明。グループ客が登る際は、うまくこちらも降りられる時は、積極的に降りていかないと時間がかかってしょうがない。ここらへんは、上手い人の後ろにピタッとついていると降りられることを発見。
さて、登山口に到着したのは11時。ほぼ3時間で降りることができた。帰りは白峰温泉に入って、汗を流す。白峰温泉もなかなかよかった。
二日目の天候がよければ、さらに快適な登山になったかと思うが、それでも一日目、弥陀ヶ原から御前峰を展望できたのはよかった。私は、登山はするが、あまり登山が好きではなく、もう一度登りたいと思う山は少ないのだが、昨年、登った御岳に次いで、白山ならもう一度、チャレンジしたいなと思わせられた。
登山道整備度 ★★★★★ (山頂までしっかりと整備されていて、極めて歩きやすい。さすが霊山)
岩場度 ★☆☆☆☆ (手を使わないといけないような岩場もなく、快適な登山が楽しめる)
登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (ぬかるみはまったくといっていいほどない)
虫うっとうしい度 ★★☆☆☆ (虫はいないとは言わないが、煩わしいことはなかった)
展望度 ★★★★★ (独立峰なので素晴らしい展望を目にすることができる・・・筈だったが個人的にはガスで見られない)
駐車場アクセス度 ★★★☆☆ (夏の混雑時はシャトルバスに乗らなくてはならない)
トイレ充実度 ★★★★★ (ところどころにある)
下山後の温泉充実度 ★★★☆☆ (白峰温泉はなかなかよかった)
安全度 ★★★★★ (山頂まで登山道はしっかりと整備されており、道に迷うようなところもなく、安全な登山が楽しめるであろう)
開聞岳(日本百名山53座登頂) [日本百名山]
開聞岳に登る。前泊は「民宿かいもん」に宿泊したのだが、この民宿は口コミの評判の高さ通りに素晴らしい民宿であった。まあ、その素晴らしさは、ホスピタリティと食事の美味しさにある。朝は4時30分から起きてもらい、珈琲にサンドイッチまでつくってくれていた。ちなみに、朝食はお弁当としておにぎりを3つも予めつくってもらっていたにも関わらずである。

<登山全日に民宿かいもんから開聞岳を見る。この日は山頂が見えた>
開聞岳の登山口までは、「民宿かいもん」からも歩いて15分ぐらいかと思うが、この15分間が結構、負担になるかもしれないのでレンタカーで最寄りの駐車場まで行く。駐車場に車を駐めて出発したのは5時30分。日は昇っているが、曇っていることもあってそれほど明るくない。駐車場からは山頂が雲で覆われている開聞岳が見える。この雲がいなくなれば開聞岳山頂からは360度の大展望が得られる筈だ。淡い期待をもって登り始める。駐車場から登山口の二合目までは、まあまあ歩く。

<登山口からは山容がはっきりと見られた。ただし、山頂は雲がかかっている>
登山口からは、亜熱帯のような森の中を歩いて行く。しばらくすると他の道との交差点に着く。ここが2.5合目だ。そこから森は鬱蒼としてきて、昼なお暗いような感じになってくる。朝が早くて曇っていることもあり、ここでヘッドランプを点ける。3合目についたのは6時。森はさらに深くなっていく。ただ、登山道は整備されていて歩きやすい。4合目についたのは6時20分。ほぼコースタイム通り。そして5合目が6時30分。ここからは海が展望でき、なかなかの景色を楽しむことができる。しかし、結果的にはここが今回の登山で唯一、楽しめた展望であった。

<登山口からの登山道はよく整備されていて歩きやすい>

<徐々に森が暗くなっていく。懐中電灯をとりあえず点けて進む>

<五合目までは坂も緩やかで、木段も整備されていて極めて歩きやすい>

<五合目からは展望が得られる。しかし、これが結果的には最後の展望であった>
6合目は6時50分。登山路はここらへんから険しくなっていき、それまでは快適であったのが、急に岩場の激しいルートになる。7合目は7時5分。そこからは太平洋が展望できる筈だが、雲の隙間に色で海が判別できるような感じ。もう、雲の傘の中に入ってしまっている。その先は、もう完全な岩場で、ストックはむしろ邪魔。今回は手袋を忘れてしまったのだが、これは大失敗である。ちょっと油断をしたら、濡れた岩に滑って右手を思い切り岩にぶつける。瞬間、手の指を骨折したかと冷や汗をかいたが、どうにか打撲だけで済んだようだ。冷却スプレーを持ってきていたので助かった。ここまで登り詰めで、自分が思っていたより足にきていたようだ。5合目を越えた後は、ほとんど急な坂道なので、筋肉は相当張っていたようだ。もう、この天候だと山頂で展望も得られないし、下山するかと思ったが、あと少しなので頑張って登り続ける。8号目は7時35分。九号目は7時50分。山頂そばの御岳神社に着いたのが8時10分。山頂は8時15分。猛烈な風が吹いていて、体感温度は相当、低い。岩場の陰で風をしのぎ、おにぎりを食べる。視界は悲しいほどゼロ。山頂にはもう一人、地元のおばさんがいた。彼女はもう何回も開聞岳には登っているそうだが、実は屋久島が見えたことはまだないそうである。意外と屋久島は、遠いことを知る。もっと、ずっと近いのかと思っていた。

<五合目を過ぎると登山道は岩だらけになる。ストックは使えず、手袋は必須であったが、私は手袋を忘れて苦労した>

<晴れていたら見事な海が望めたろうが、まったくそれは期待外れに終わった>

<山頂に近づくほど岩は厳しくなる。足下に気をつけないと怪我をする。私も危ない思いをした>

<山頂そばの御岳神社>
展望も得られず、あと風を凌いではいても猛烈に寒くなってきたので、そそくさと下山する。8時30分には下山開始である。右手は相変わらず痛いので、丁寧にゆっくりと降りていく。9合目は8時50分。5合目は10時。5合目は行きよりもさらに展望が開け、とてもいい感じである。結局、今回の登山で得られた展望は往復の5合目のそれだけであった。ちょっと悔しい。悔しいといえば、5合目辺りから天気がどんどんとよくなったことである。思わず、登り直そうかと思ったぐらいであるが、流石にそれは右手が痛いのと、仕事が溜まっているので諦めた。登山口に戻ったのは10時50分。往復で5時間20分の登山であった。温泉は山川町の「たまてばこ温泉」に行ったのだが、これは素晴らしくよかった。露天風呂から得られる景観としては、個人的にはベストであった。ここは大のお勧めだ。ここからは開聞岳も見られるのだが、温泉から出る時(12時過ぎ)まではまだ雲が帽子のように開聞岳の山頂にちょこっと乗っていた。登り直さなくてよかったと思いつつ、鹿児島駅方面に向かった。

<山頂はまったく視界が得られず、また激しい風が吹いていて体感温度は相当、低かった>

<写真ではあまり分からないかもしれないが、風はなかなか激しかった>

<五合目までに戻ってようやく展望が得られた。池田湖もみられる>

<五合目から指宿方面を展望する>

<登山口に戻ったら、見事な晴天になっていた>

<ただし、山頂は相変わらず雲に覆われていた>

<たまてばこ温泉に浸かった時点も、まだ山頂は雲に覆われていた>
登山道整備度 ★★★☆☆ (5合目までは素晴らしい。その後の岩場は険しい)
岩場度 ★★★★☆ (ストックは使えない。手袋必須)
登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (濡れてはいるのだがぬかるみはそれほどない)
虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはまったくなかった)
展望度 ★★★★☆ (本来は素晴らしい展望が得られるはず。ただ、山は木に覆われているので、登山道からの展望はそれほど得られない)
駐車場アクセス度 ★★★★☆ (駐車場から登山口までちょっとあるが、非常に多くの台数が駐められる)
トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (登山口にあるのみ)
下山後の温泉充実度 ★★★★★ (素晴らしすぎる)
安全度 ★★☆☆☆ (低山ではあるが、岩場が多く、また崖を歩いて行くので遭難者が多いのは頷ける)

<登山全日に民宿かいもんから開聞岳を見る。この日は山頂が見えた>
開聞岳の登山口までは、「民宿かいもん」からも歩いて15分ぐらいかと思うが、この15分間が結構、負担になるかもしれないのでレンタカーで最寄りの駐車場まで行く。駐車場に車を駐めて出発したのは5時30分。日は昇っているが、曇っていることもあってそれほど明るくない。駐車場からは山頂が雲で覆われている開聞岳が見える。この雲がいなくなれば開聞岳山頂からは360度の大展望が得られる筈だ。淡い期待をもって登り始める。駐車場から登山口の二合目までは、まあまあ歩く。

<登山口からは山容がはっきりと見られた。ただし、山頂は雲がかかっている>
登山口からは、亜熱帯のような森の中を歩いて行く。しばらくすると他の道との交差点に着く。ここが2.5合目だ。そこから森は鬱蒼としてきて、昼なお暗いような感じになってくる。朝が早くて曇っていることもあり、ここでヘッドランプを点ける。3合目についたのは6時。森はさらに深くなっていく。ただ、登山道は整備されていて歩きやすい。4合目についたのは6時20分。ほぼコースタイム通り。そして5合目が6時30分。ここからは海が展望でき、なかなかの景色を楽しむことができる。しかし、結果的にはここが今回の登山で唯一、楽しめた展望であった。

<登山口からの登山道はよく整備されていて歩きやすい>

<徐々に森が暗くなっていく。懐中電灯をとりあえず点けて進む>

<五合目までは坂も緩やかで、木段も整備されていて極めて歩きやすい>

<五合目からは展望が得られる。しかし、これが結果的には最後の展望であった>
6合目は6時50分。登山路はここらへんから険しくなっていき、それまでは快適であったのが、急に岩場の激しいルートになる。7合目は7時5分。そこからは太平洋が展望できる筈だが、雲の隙間に色で海が判別できるような感じ。もう、雲の傘の中に入ってしまっている。その先は、もう完全な岩場で、ストックはむしろ邪魔。今回は手袋を忘れてしまったのだが、これは大失敗である。ちょっと油断をしたら、濡れた岩に滑って右手を思い切り岩にぶつける。瞬間、手の指を骨折したかと冷や汗をかいたが、どうにか打撲だけで済んだようだ。冷却スプレーを持ってきていたので助かった。ここまで登り詰めで、自分が思っていたより足にきていたようだ。5合目を越えた後は、ほとんど急な坂道なので、筋肉は相当張っていたようだ。もう、この天候だと山頂で展望も得られないし、下山するかと思ったが、あと少しなので頑張って登り続ける。8号目は7時35分。九号目は7時50分。山頂そばの御岳神社に着いたのが8時10分。山頂は8時15分。猛烈な風が吹いていて、体感温度は相当、低い。岩場の陰で風をしのぎ、おにぎりを食べる。視界は悲しいほどゼロ。山頂にはもう一人、地元のおばさんがいた。彼女はもう何回も開聞岳には登っているそうだが、実は屋久島が見えたことはまだないそうである。意外と屋久島は、遠いことを知る。もっと、ずっと近いのかと思っていた。

<五合目を過ぎると登山道は岩だらけになる。ストックは使えず、手袋は必須であったが、私は手袋を忘れて苦労した>

<晴れていたら見事な海が望めたろうが、まったくそれは期待外れに終わった>

<山頂に近づくほど岩は厳しくなる。足下に気をつけないと怪我をする。私も危ない思いをした>

<山頂そばの御岳神社>
展望も得られず、あと風を凌いではいても猛烈に寒くなってきたので、そそくさと下山する。8時30分には下山開始である。右手は相変わらず痛いので、丁寧にゆっくりと降りていく。9合目は8時50分。5合目は10時。5合目は行きよりもさらに展望が開け、とてもいい感じである。結局、今回の登山で得られた展望は往復の5合目のそれだけであった。ちょっと悔しい。悔しいといえば、5合目辺りから天気がどんどんとよくなったことである。思わず、登り直そうかと思ったぐらいであるが、流石にそれは右手が痛いのと、仕事が溜まっているので諦めた。登山口に戻ったのは10時50分。往復で5時間20分の登山であった。温泉は山川町の「たまてばこ温泉」に行ったのだが、これは素晴らしくよかった。露天風呂から得られる景観としては、個人的にはベストであった。ここは大のお勧めだ。ここからは開聞岳も見られるのだが、温泉から出る時(12時過ぎ)まではまだ雲が帽子のように開聞岳の山頂にちょこっと乗っていた。登り直さなくてよかったと思いつつ、鹿児島駅方面に向かった。

<山頂はまったく視界が得られず、また激しい風が吹いていて体感温度は相当、低かった>

<写真ではあまり分からないかもしれないが、風はなかなか激しかった>

<五合目までに戻ってようやく展望が得られた。池田湖もみられる>

<五合目から指宿方面を展望する>

<登山口に戻ったら、見事な晴天になっていた>

<ただし、山頂は相変わらず雲に覆われていた>

<たまてばこ温泉に浸かった時点も、まだ山頂は雲に覆われていた>
登山道整備度 ★★★☆☆ (5合目までは素晴らしい。その後の岩場は険しい)
岩場度 ★★★★☆ (ストックは使えない。手袋必須)
登山道ぬかるみ度 ★☆☆☆☆ (濡れてはいるのだがぬかるみはそれほどない)
虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはまったくなかった)
展望度 ★★★★☆ (本来は素晴らしい展望が得られるはず。ただ、山は木に覆われているので、登山道からの展望はそれほど得られない)
駐車場アクセス度 ★★★★☆ (駐車場から登山口までちょっとあるが、非常に多くの台数が駐められる)
トイレ充実度 ★☆☆☆☆ (登山口にあるのみ)
下山後の温泉充実度 ★★★★★ (素晴らしすぎる)
安全度 ★★☆☆☆ (低山ではあるが、岩場が多く、また崖を歩いて行くので遭難者が多いのは頷ける)
那須岳(日本百名山52座登頂) [日本百名山]
10月10日のまさに紅葉日和に那須岳にチャレンジする。9時に那須塩原駅にてゼミの卒業生3人を拾い、レンタカーにて那須ロープウェイの乗車口に向かう。さて、しかし、那須ロープウェイの入り口から渋滞が続いているようで、この状況ではロープウェイ乗車口では駐車が出来ないのではと考えて、大丸駐車場のところで車を駐車し、そこからバスで行くことにする。これは結果論的に大正解の判断となった。大丸駐車場からはバスにはすぐ乗れたが、当たり前だがバスも渋滞でほとんど移動できない。運転手さんが、歩いた方が早いですよ、と言って皆を降ろしてくれたので、そのようにする。大丸駐車場からロープウェイ乗車口までは、20分ほどであった。道路と並行するようにトレイルが整備されているので歩きやすい。ロープウェイに乗って山頂に着いたのは11時。三本鎗岳に行くのは遅くとも9時発とガイドブックに書いてあったので、これはもう茶臼岳と朝日岳の二つだなと判断する。
さて、下の方は晴れていたのだが、ロープウェイの頂上口はガスが凄く、視界は悪い。さらに結構の風が吹いていて、先が思いやられる。茶臼岳への道のりは、ほとんど樹木がなく、さすが活火山であるなと改めて思う。道のりは手を使うほどではないが、急な岩場を歩いて行くという感じ。ロープウェイで一挙にあがっても、茶臼岳へ行くのはそれほど簡単ではない。茶臼岳の山頂に着いたのは11時30分。周囲はガスに覆われ、視界は効かない。そして、風が凄い。まあ、これぐらいの風は何回も体験してはいるが、水分を含んでいるとちょっと低体温症とかを意識しなくてはいけない強さだ。ここで簡単に昼ご飯を食べて、そそくさと朝日岳へと向かう。朝日岳へのコースはちょっと風も緩み、比較的、快適に歩を進めることができる。ここでガスが晴れ、朝日岳の雄壮なる姿、そして紅葉に染まる過程にある山並を観ることができる。まあ、これを観たくて多くの人が訪れるのはよく分かる。

ロープウェイの乗り場では視界が開けていたのだが・・・

ロープウェイを降りると周りはガス。草木なき登山道を歩いて行く。

茶臼岳。風が強かった。

茶臼岳から朝日岳へ。

途中、瞬間的にガスが晴れる。紅葉と緑のグラデーションが美しい。
さて、ロープウェイと朝日岳方面へとの分岐点にある避難小屋に着いたのは12時45分。この避難小屋はトイレもなく、本当に避難のための小屋である。そこから朝日岳に向かうが、途中、絶壁のトラバースのようなところへ行く。ちょっとスリリングだ。そして、岩登りのような急登の鎖場を登っていく。ここらへんからまたガスが視界を遮り始める。朝日岳は三本鎗岳へのコースからちょっと横に逸れる。ルートは分かりにくいので注意が必要だ。朝日岳に登頂したのは13時30分。視界がちょっとでも開けるのを期待したが、まったく展望は得られなかった。仕方がないので15分ぐらい休んで帰路に着く。休むといっても風が相当、強いのでリラックスはできにくい。帰路もなかなかの斜度の岩の中を降りて行くという感じ。危険を感じるほどではないが、油断をすると危ない。避難小屋は、行きと違ってガスで覆われていた。本当、登山はタイミングだなと思う。避難小屋からは、ロープウェイ駅への道を取る。行きはここらへんは晴れていたのだが、帰りはもう霧雨の中を歩いて行く感じ。ただ、登山道はしっかりと整備されていて歩きやすい。

避難小屋

避難小屋から朝日岳は結構な壁に沿って歩いて行く

ちょっとアドベンチャラスな感じ

朝日岳山頂

ほとんどガスで視界はゼロに近かったが、ちょっとだけ展望が開けた瞬間にシャッターを下ろす
ロープウェイ駅に着いたのは15時30分。バスの時間が18分後だったので、大丸駐車場までも歩く。ちょうど我々が着いた時にバスも着いた。その後、鹿の湯に寄る。鹿の湯は昔の風情が満載の素晴らしい露天風呂だ。やはり、活火山のある登山はその後の温泉が素晴らしい。17時に鹿の湯を出て、レンタカーを返却し、18時03分の新幹線で帰京。赤羽の居酒屋にいってちょっと打ち上げ。
いい一日であった。
さて、下の方は晴れていたのだが、ロープウェイの頂上口はガスが凄く、視界は悪い。さらに結構の風が吹いていて、先が思いやられる。茶臼岳への道のりは、ほとんど樹木がなく、さすが活火山であるなと改めて思う。道のりは手を使うほどではないが、急な岩場を歩いて行くという感じ。ロープウェイで一挙にあがっても、茶臼岳へ行くのはそれほど簡単ではない。茶臼岳の山頂に着いたのは11時30分。周囲はガスに覆われ、視界は効かない。そして、風が凄い。まあ、これぐらいの風は何回も体験してはいるが、水分を含んでいるとちょっと低体温症とかを意識しなくてはいけない強さだ。ここで簡単に昼ご飯を食べて、そそくさと朝日岳へと向かう。朝日岳へのコースはちょっと風も緩み、比較的、快適に歩を進めることができる。ここでガスが晴れ、朝日岳の雄壮なる姿、そして紅葉に染まる過程にある山並を観ることができる。まあ、これを観たくて多くの人が訪れるのはよく分かる。

ロープウェイの乗り場では視界が開けていたのだが・・・

ロープウェイを降りると周りはガス。草木なき登山道を歩いて行く。

茶臼岳。風が強かった。

茶臼岳から朝日岳へ。

途中、瞬間的にガスが晴れる。紅葉と緑のグラデーションが美しい。
さて、ロープウェイと朝日岳方面へとの分岐点にある避難小屋に着いたのは12時45分。この避難小屋はトイレもなく、本当に避難のための小屋である。そこから朝日岳に向かうが、途中、絶壁のトラバースのようなところへ行く。ちょっとスリリングだ。そして、岩登りのような急登の鎖場を登っていく。ここらへんからまたガスが視界を遮り始める。朝日岳は三本鎗岳へのコースからちょっと横に逸れる。ルートは分かりにくいので注意が必要だ。朝日岳に登頂したのは13時30分。視界がちょっとでも開けるのを期待したが、まったく展望は得られなかった。仕方がないので15分ぐらい休んで帰路に着く。休むといっても風が相当、強いのでリラックスはできにくい。帰路もなかなかの斜度の岩の中を降りて行くという感じ。危険を感じるほどではないが、油断をすると危ない。避難小屋は、行きと違ってガスで覆われていた。本当、登山はタイミングだなと思う。避難小屋からは、ロープウェイ駅への道を取る。行きはここらへんは晴れていたのだが、帰りはもう霧雨の中を歩いて行く感じ。ただ、登山道はしっかりと整備されていて歩きやすい。

避難小屋

避難小屋から朝日岳は結構な壁に沿って歩いて行く

ちょっとアドベンチャラスな感じ

朝日岳山頂

ほとんどガスで視界はゼロに近かったが、ちょっとだけ展望が開けた瞬間にシャッターを下ろす
ロープウェイ駅に着いたのは15時30分。バスの時間が18分後だったので、大丸駐車場までも歩く。ちょうど我々が着いた時にバスも着いた。その後、鹿の湯に寄る。鹿の湯は昔の風情が満載の素晴らしい露天風呂だ。やはり、活火山のある登山はその後の温泉が素晴らしい。17時に鹿の湯を出て、レンタカーを返却し、18時03分の新幹線で帰京。赤羽の居酒屋にいってちょっと打ち上げ。
いい一日であった。
タグ:那須岳
御岳山(日本百名山51座登頂) [日本百名山]
御岳山にチャレンジする。御岳山は2014年9月の噴火以降、登山ルートが立ち入り規制されたが、最近、緩和された。ということで、どうせ登るのであれば最高峰の剣ヶ峰に行こうと考える。ただ、どの登山道の規制が緩和されたのかがよく分からなかった。そこで、前泊した木曽福島のホテルの受け付けのお兄さんに尋ねると、よく理解しておらず、とりあえず御岳ロープウェイのルートがいいんじゃないですかと答える。御岳ロープウェイ は始発が7時。ただ、それよりは田ノ原ルートの方がいいだろうな、と思っていた。さて、ホテルは当日、予約したのでもう夕食は用意できない、ということなので木曽福島の街中にでる。どうも「くるまや」という蕎麦屋が有名のようなので、そこに行こうとするともう閉まっていた。仕方がないので、そばの「たちばな」という居酒屋に入る。長野県はどうも非常事態宣言に指定されていないそうで、お酒が飲めるので、久し振りに居酒屋で日本酒を飲む。さて、そこでダメ元でお店の人に御岳山の登山ルートを尋ねると、なんとご主人はメチャクチャ詳しくて、田ノ原ルートからだと王滝までは行けるが、その先は通行できないと教えてくれる。これは、ホームページとかを熟読すれば分かったことだが、私はよく読み取れていなかった。田ノ原ルートで行こうと思っていたので、この情報はメチャクチャ助かる。さらに、ロープウェイで行くのもいいが、黒沢口6合目までは車で行くことが出来、そこから50分ぐらいでロープウェイの山頂駅からのルートと合流すると教えてくれる。7時にロープウェイの駐車場に行くのは日の出が5時30分ということを考えると勿体ない。起床時間にも依るが、黒沢口6合目か御岳ロープウェイで登ることを決める。このご主人は拡大した地図まで渡してくれた。
翌日は2時前ぐらいに起床する。ちょっと早すぎたので布団でゴロゴロしていたが4時には床から出て4時45分ぐらいに宿を出る。ここから黒沢口6合目までは26キロメートル。途中、セブンイレブンに寄り、朝食のサンドイッチと昼食のおにぎりを購入する。黒沢口6合目までの道のりはなかなかの山道で結局、思ったよりも遅く6時頃に到着してしまった。ここは相当、駐車場の台数には余裕があるのだが、結構、埋まっていた。穴場のルートなのかなと思っていたが、大間違いだ。御岳山、私が思っていたよりはるかに人気のあるルートなのではないかと思われる。駐車場には駐まれたが、もう既に日は出ており、もう少し早く宿を出ていればよかったと後悔する。
登山の準備をして出発したのは6時10分。登山道はしっかりと整備されており、歩きやすい。昨日までの雨で泥濘んではいるが、木の階段が組まれているので苦ではない。登山ではこの泥濘道に手こずることが多いので、これは有り難い。さて、出発地点は1800メートルとそれほど高くはないが、それでも高山病気質の私はあまり気分がよくない。高山病を発症したら元も子もないので、通常のゆっくりペースをさらにゆっくりさせて、どんどん後続に追い越されても、一歩一歩噛みしめるように歩いて行く。黒沢口ルート、傾斜はなかなか急なので楽なルートではない。御岳ロープウェイとの合流点には7時に着く。御岳ロープウェイ組よりは早い到達時間であるが、それほどのアドバンテージでもない。その後のルートもしっかりと整備はされていて歩きやすいが、なかなかの斜面である。ただ、ところどころで気の合間から見られる中央アルプスの山々の美しさに癒やされる。7時45分に後続にどんどん追い越されていく。尋ねると、ロープウェイ組であった。たったの45分のアドバンテージのために300メートル余計に登ったのかと思うと、もっと早く起きていけばと思わずにはいられない。ロープウェイ組はまだ歩き始めということもあって元気に登っていく。8合目に到着したのは8時。ここには山荘があって、食事が取れる。というか、7合目にも山荘があり、8合目にも9合目にも山荘があって、そういう意味では登山をするうえでのサポート・サービスが充実した山であるといえよう。

<黒沢口6合目の駐車場は相当の台数が駐められる。この写真以外にも2箇所ある。ただ、6時前でも相当数、既に駐車していた>

<黒沢口6合目の入り口>

<気持ちのよい森の中を歩いて行く。登山道はしっかりと整備されていて快適だ>

<朝日の中を歩いて行くのは登山の醍醐味の一つであろう>

<八合目になると途端に展望が開ける>

<八合目からちょっと登ったところからの素晴らしい展望。左に見えるのが乗鞍岳だ>
8合目から上は灌木しか生えていない。もう既に紅葉が始まっていて、その色彩が美しく晴れやかな気分となる。8号目からは木曽アルプス、南アルプス、先週登った乗鞍岳、北アルプスが展望できる。非常に豪華な景観を望める。8号目からは登山道にレキが目立つが登山上がしっかりと整備されているので歩きやすい。しかも急斜面ではあるが、鎖場や梯子はまったくない。この歩きやすさはこの御岳登山の魅力の一つといってもいいであろう。これは人気がある訳だと納得する。石室山荘の手前で森林限界。これから先はもう岩の世界である。十勝岳とか霧島岳(韓国岳)の火山もそうだが、日本の山の山頂の多くがまるでイメージとする火星のような荒廃した景観であるということは登山をするまで知らなかったことである。

<レキの登山道だがしっかりと整備されており歩きやすい>

<既に紅葉が始まっている>
9号目の手前にある石室山荘に到着したのは9時20分。ここでおにぎりなど簡単にエネルギーを吸収し、長袖のシャツや虫除けなどこれからの山頂アタックに不要なものをここに預けさせてもらう。こういうサービスをしてくれる山荘があるのは本当、有り難い。ここで2014年に亡くなられた方々への供養の気持ちを込めて、好きではないヘルメットを被る。ヘルメットは御岳山登山のために今回、初めて買ったものである。さて、随分と身軽になったので足取りも軽く、山頂を目指す。二ノ池を通過するのが10時ぐらい。私が写真でみた二ノ池は青かったが、今日の二ノ池は白濁した色であった。2014年からこのような色のままなのかもしれない。さて、そこから先は、もう私の苦手のレキの登山道なのかなと思っていたら、難しいところは、しっかりと階段状の木道が整備されていて歩きやすい。そして、何より展望が別格によい。嬉しい気持ちになりながら標高を稼いでいく。ゆっくりと疲れないように歩いていたこともあって高山病にもならずに済みそうだ。

<石室山荘。ここまでの登山の疲れを取るのにうってつけの場所に建っている>

<九合目から上はまったくもってぺんぺん草も生えない荒野のような道を行く>

<二ノ池>

<苦手なレキの登山道だが、しっかりとこのような木の階段が設置されているのでとても歩きやすい。いい登山道だ>

<頂上手前。2014年の事故以降につくられた避難場所。ちょっとデザインが今一つ>

<頂上にはこの80段ほどの階段を登らなくては成らない。最後の試練>
山頂に着いたのは10時20分。最後に80段ぐらいの階段を登らさせられる。山頂からは乗鞍岳、北アルプス、八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、そして恵那山までもが展望できる。天気に恵まれたこともあって、素晴らしい景色を楽しむことができた。つくづく、登山は天気によってその体験が大きく左右されることを痛感する。今日は大当たりであった(いや、晴れということが分かったので登ったということもあるが)。
山頂ではインスタント・ラーメンを食べる。いつもは普通のカップヌードルなのだが、今日は趣向を変えたものを買ったら「激辛インスタント・ラーメン」であった。京都の一乗寺にある「極鶏ラーメン」をモデルにしたものだが、そもそも当たり前だが麺が違うし、味も全然、違う。それはいいが、この激辛というのは登山には極めて不適切だ。お腹を壊したらどうする、と思いつつ悔しいので食べる。
11時15分頃に下山を開始する。登山計画書では30分休憩だが、どうも自分は60分は休憩を取りたいタイプのようだ。これからは登山計画でも60分間の休憩時間としておこう。今回は1300メートルの登山であったが、太股が攣りそうなこともなく、結構、順調に上がってこれた。とはいえ、下りでは膝を痛める可能性があるので、慎重にゆっくりペースで降りて行く。12時頃に石室山荘に到着。荷物を受け取り、300円のオロナミンCを飲んで8号目に向かう。結構、膝は痛むので、随時、休んでマッサージをする。8号目の到着は13時。コースタイムを大きく上回る時間である。というか、自分はこの下りが人より時間がかかることを改めて認識する。そして、7号目の力餅のある行場山荘に着いたのは13時50分。せっかくなので「力餅(ぜんざい)」を食べて休む。500円だが、疲れた身体にぜんざいの甘さとお餅のもちもち感が嬉しい。お店を出たのは14時ちょっと過ぎ。そして、最後の力を振り絞って黒沢口6合目に着く。到着時間は14時40分。下りに時間を取られたが、それでも膝も痛くはなく、太股も一度も痙攣しなかったこと、さらには尻餅をつかなかったことはちょっとした成果である。
帰りは木曽福島の街並みを見学し、一挙に東京まで戻る。連休の合間ではあったが、中央高速で25キロの渋滞に遭い、家に着いたのは23時近くであった。

<山頂から二ノ池方面を望む>

<山頂から木曽山脈の方を望む。右手には王滝方面の登山口が見える>

<連休中ということもあって多くの登山客が登っていた>

<行場山荘の力餅。疲れた身体にはじんとくる美味しさだ>
登山道整備度 ★★★★★ (難しいところには階段が整備されていて、非常によい)
岩場度 ☆☆☆☆☆ (手を使って登らなくてはいけないところはほとんどない)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (8合目までは多少、ぬかるんでいる)
虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはほとんどない)
展望度 ★★★★★ (絶景)
駐車場アクセス度 ★★★★★
トイレ充実度 ★★★☆☆
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆
安全度 ★★☆☆☆ (登山道がしっかりしているので、安全)
翌日は2時前ぐらいに起床する。ちょっと早すぎたので布団でゴロゴロしていたが4時には床から出て4時45分ぐらいに宿を出る。ここから黒沢口6合目までは26キロメートル。途中、セブンイレブンに寄り、朝食のサンドイッチと昼食のおにぎりを購入する。黒沢口6合目までの道のりはなかなかの山道で結局、思ったよりも遅く6時頃に到着してしまった。ここは相当、駐車場の台数には余裕があるのだが、結構、埋まっていた。穴場のルートなのかなと思っていたが、大間違いだ。御岳山、私が思っていたよりはるかに人気のあるルートなのではないかと思われる。駐車場には駐まれたが、もう既に日は出ており、もう少し早く宿を出ていればよかったと後悔する。
登山の準備をして出発したのは6時10分。登山道はしっかりと整備されており、歩きやすい。昨日までの雨で泥濘んではいるが、木の階段が組まれているので苦ではない。登山ではこの泥濘道に手こずることが多いので、これは有り難い。さて、出発地点は1800メートルとそれほど高くはないが、それでも高山病気質の私はあまり気分がよくない。高山病を発症したら元も子もないので、通常のゆっくりペースをさらにゆっくりさせて、どんどん後続に追い越されても、一歩一歩噛みしめるように歩いて行く。黒沢口ルート、傾斜はなかなか急なので楽なルートではない。御岳ロープウェイとの合流点には7時に着く。御岳ロープウェイ組よりは早い到達時間であるが、それほどのアドバンテージでもない。その後のルートもしっかりと整備はされていて歩きやすいが、なかなかの斜面である。ただ、ところどころで気の合間から見られる中央アルプスの山々の美しさに癒やされる。7時45分に後続にどんどん追い越されていく。尋ねると、ロープウェイ組であった。たったの45分のアドバンテージのために300メートル余計に登ったのかと思うと、もっと早く起きていけばと思わずにはいられない。ロープウェイ組はまだ歩き始めということもあって元気に登っていく。8合目に到着したのは8時。ここには山荘があって、食事が取れる。というか、7合目にも山荘があり、8合目にも9合目にも山荘があって、そういう意味では登山をするうえでのサポート・サービスが充実した山であるといえよう。

<黒沢口6合目の駐車場は相当の台数が駐められる。この写真以外にも2箇所ある。ただ、6時前でも相当数、既に駐車していた>

<黒沢口6合目の入り口>

<気持ちのよい森の中を歩いて行く。登山道はしっかりと整備されていて快適だ>

<朝日の中を歩いて行くのは登山の醍醐味の一つであろう>

<八合目になると途端に展望が開ける>

<八合目からちょっと登ったところからの素晴らしい展望。左に見えるのが乗鞍岳だ>
8合目から上は灌木しか生えていない。もう既に紅葉が始まっていて、その色彩が美しく晴れやかな気分となる。8号目からは木曽アルプス、南アルプス、先週登った乗鞍岳、北アルプスが展望できる。非常に豪華な景観を望める。8号目からは登山道にレキが目立つが登山上がしっかりと整備されているので歩きやすい。しかも急斜面ではあるが、鎖場や梯子はまったくない。この歩きやすさはこの御岳登山の魅力の一つといってもいいであろう。これは人気がある訳だと納得する。石室山荘の手前で森林限界。これから先はもう岩の世界である。十勝岳とか霧島岳(韓国岳)の火山もそうだが、日本の山の山頂の多くがまるでイメージとする火星のような荒廃した景観であるということは登山をするまで知らなかったことである。

<レキの登山道だがしっかりと整備されており歩きやすい>

<既に紅葉が始まっている>
9号目の手前にある石室山荘に到着したのは9時20分。ここでおにぎりなど簡単にエネルギーを吸収し、長袖のシャツや虫除けなどこれからの山頂アタックに不要なものをここに預けさせてもらう。こういうサービスをしてくれる山荘があるのは本当、有り難い。ここで2014年に亡くなられた方々への供養の気持ちを込めて、好きではないヘルメットを被る。ヘルメットは御岳山登山のために今回、初めて買ったものである。さて、随分と身軽になったので足取りも軽く、山頂を目指す。二ノ池を通過するのが10時ぐらい。私が写真でみた二ノ池は青かったが、今日の二ノ池は白濁した色であった。2014年からこのような色のままなのかもしれない。さて、そこから先は、もう私の苦手のレキの登山道なのかなと思っていたら、難しいところは、しっかりと階段状の木道が整備されていて歩きやすい。そして、何より展望が別格によい。嬉しい気持ちになりながら標高を稼いでいく。ゆっくりと疲れないように歩いていたこともあって高山病にもならずに済みそうだ。

<石室山荘。ここまでの登山の疲れを取るのにうってつけの場所に建っている>

<九合目から上はまったくもってぺんぺん草も生えない荒野のような道を行く>

<二ノ池>

<苦手なレキの登山道だが、しっかりとこのような木の階段が設置されているのでとても歩きやすい。いい登山道だ>

<頂上手前。2014年の事故以降につくられた避難場所。ちょっとデザインが今一つ>

<頂上にはこの80段ほどの階段を登らなくては成らない。最後の試練>
山頂に着いたのは10時20分。最後に80段ぐらいの階段を登らさせられる。山頂からは乗鞍岳、北アルプス、八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、そして恵那山までもが展望できる。天気に恵まれたこともあって、素晴らしい景色を楽しむことができた。つくづく、登山は天気によってその体験が大きく左右されることを痛感する。今日は大当たりであった(いや、晴れということが分かったので登ったということもあるが)。
山頂ではインスタント・ラーメンを食べる。いつもは普通のカップヌードルなのだが、今日は趣向を変えたものを買ったら「激辛インスタント・ラーメン」であった。京都の一乗寺にある「極鶏ラーメン」をモデルにしたものだが、そもそも当たり前だが麺が違うし、味も全然、違う。それはいいが、この激辛というのは登山には極めて不適切だ。お腹を壊したらどうする、と思いつつ悔しいので食べる。
11時15分頃に下山を開始する。登山計画書では30分休憩だが、どうも自分は60分は休憩を取りたいタイプのようだ。これからは登山計画でも60分間の休憩時間としておこう。今回は1300メートルの登山であったが、太股が攣りそうなこともなく、結構、順調に上がってこれた。とはいえ、下りでは膝を痛める可能性があるので、慎重にゆっくりペースで降りて行く。12時頃に石室山荘に到着。荷物を受け取り、300円のオロナミンCを飲んで8号目に向かう。結構、膝は痛むので、随時、休んでマッサージをする。8号目の到着は13時。コースタイムを大きく上回る時間である。というか、自分はこの下りが人より時間がかかることを改めて認識する。そして、7号目の力餅のある行場山荘に着いたのは13時50分。せっかくなので「力餅(ぜんざい)」を食べて休む。500円だが、疲れた身体にぜんざいの甘さとお餅のもちもち感が嬉しい。お店を出たのは14時ちょっと過ぎ。そして、最後の力を振り絞って黒沢口6合目に着く。到着時間は14時40分。下りに時間を取られたが、それでも膝も痛くはなく、太股も一度も痙攣しなかったこと、さらには尻餅をつかなかったことはちょっとした成果である。
帰りは木曽福島の街並みを見学し、一挙に東京まで戻る。連休の合間ではあったが、中央高速で25キロの渋滞に遭い、家に着いたのは23時近くであった。

<山頂から二ノ池方面を望む>

<山頂から木曽山脈の方を望む。右手には王滝方面の登山口が見える>

<連休中ということもあって多くの登山客が登っていた>

<行場山荘の力餅。疲れた身体にはじんとくる美味しさだ>
登山道整備度 ★★★★★ (難しいところには階段が整備されていて、非常によい)
岩場度 ☆☆☆☆☆ (手を使って登らなくてはいけないところはほとんどない)
登山道ぬかるみ度 ★★☆☆☆ (8合目までは多少、ぬかるんでいる)
虫うっとうしい度 ★☆☆☆☆ (虫が鬱陶しいことはほとんどない)
展望度 ★★★★★ (絶景)
駐車場アクセス度 ★★★★★
トイレ充実度 ★★★☆☆
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆
安全度 ★★☆☆☆ (登山道がしっかりしているので、安全)
乗鞍岳(日本百名山50座登頂) [日本百名山]
乗鞍岳にチャレンジする。これまで乗鞍岳には二度チャレンジしたことがある。一度目は畳平までは辿り着いたが、あまりのガスと高山病のような症状がでたので諦めた。二度目は雨で畳平まで行くバスに乗ることさえしなかった。乗鞍岳は百名山の中では、そうとう登頂が楽な山と知られている。しかし、私にとってはなかなか手強い存在であった。その手強さの一番の要員は私が高山病になりやすいということがある。最初にトライしたのは、松本で宿泊して、そのままバスターミナルに向かったので、いきなり短時間で2000メートルも登ることになった。そして、おそらく寝不足でもあったかと思う。そういう失敗をしたので、今回の前泊は乗鞍高原にて行った。乗鞍高原だと、それでもう標高は1600メートルもある。少しでも高さに慣れた方がよい。
寝不足も大敵ということで、20時頃には就寝する。しかし、2時ちょっと過ぎには目が覚める。始発バスは6時10分で、それに乗る計画だったが、こんなに早く目が覚めたなら、4時10分とかの来光バスにも乗れる。それに乗ろうかと調べたら、前日の18時までに予約をしておかないといけないらしい。残念だが諦める。普通の月曜日だというのに、5時30分には結構、多くの人がいた。その前日の日曜日だったら、相当、人がいたであろう。コロナなのに、あまり人は行動を抑制していないようだ。って、人のことは言えない。バスは時間通り出発し、6時55分頃に畳平に到着。なんと気温は6度。相当、寒い。ちょっと高山病的な気分のよくなさはあるが、まあ、これぐらいなら大丈夫。大事をとってゆっくりと進んでいく。天気は最高によい。まさに三度目の正直。

(バスターミナルからも剣が峰が見える。三度目の挑戦で初めての晴天)

(9月13日であるにも関わらず、畳平は6度という寒さ)

(畳平からの登山口の入り口)
お花畑を右手に見つつ、歩を進めると砂利道の車道に出る。これは歩くのは楽だが、味気ない。ただ、そこから左手に広がる展望は素晴らしいの一言につきる。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳とが見える。しばらく歩くと、肩の小屋に着く。時間的には7時40分。ここからは、登山道。レキが多い登山道で、ハイキングというよりかは登山という気分にさせられる。剣ヶ峰への登山道自体は、典型的な火山登山で、レキと低木で景観的には目を楽しませるものがないが、展望はもう特別に素晴らしい。雨や霧の日ではなく、この晴れの日に登山できたことはラッキーだ(いや、三回目にしてようやく晴れたというのが実態だが)。

(登山始めは右手に花畑をみながら歩いて行く)

(砂利道の車道を歩いて行く。素っ気ない登山道だが展望は素晴らしい)

(肩の小屋からは本格的な登山道が始まる)

(振り返ると北アルプスの素晴らしい展望が広がっている)

(百名山としては簡単に登れるといわれる乗鞍岳であるが、このレキを登っていくのは簡単ではない)

(乗鞍岳も火山であるのだな、ということがこの無味乾燥な登山道から理解できる)

(権現池の向こうには白山がみられる)
頂上小屋に着いたのは8時30分。ここでは珈琲も飲める。私はドリップ式の珈琲をもってきたのでここのは飲まなかったが、軽い荷物で上がっても肩の小屋では食事もできるし、頂上小屋では珈琲も飲める。なかなか充実したサービスが提供されている。この小屋からの展望も素晴らしいの一言で、北アルプス、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳ともう絶景を楽しめる。とはいえ、頂上はさらにいいだろうと20分ほど登ると頂上に着いた。頂上からはまさに360度の大展望が得られる。富士山が北岳の左側にちょこっと覗くように顔を出している。ちっちゃい、それほど威厳もないような富士山ではあるが、富士山が見えると見えないとでえらく得した感が違う。全然活躍しない大谷翔平でも、試合に出ているのを見ると嬉しいのとかと感覚は近いのかもしれない。ここでカップ麺を食べ、珈琲を飲み、帰路に着く。下り始めたのは9時30分ぐらいだ。

(頂上小屋では珈琲を飲むことができる)

(頂上小屋から南アルプスを展望する)

(御岳山も見ることができる)

(頂上から南アルプス方面を展望する)
下りは比較的早めのペースで降りて行った。これはバスが一時間に一本しか走っていないからで、10時05分は無理だが、その次には乗りたかったからである。そのためにはコースタイム通りで下山しないといけない。今回はストックを敢えてもたずに登山をしたが、膝にくることもなく、太股の筋肉にも特にハリは出来ず、無事に11時頃には下山することができた。11時05分発のバスに乗って、バスターミナルに戻ったのは11時50分。宿泊した宿が帰りに温泉に寄っていいと言ってくれたのでお言葉に甘えて行く。記念すべき百名山の50座目は、特に危険もなく、楽しい登山であった。

(下山もずっと素晴らしい展望を楽しむことができる。これは乗鞍岳登山の魅力である。ただし、晴れていないといけないが)
寝不足も大敵ということで、20時頃には就寝する。しかし、2時ちょっと過ぎには目が覚める。始発バスは6時10分で、それに乗る計画だったが、こんなに早く目が覚めたなら、4時10分とかの来光バスにも乗れる。それに乗ろうかと調べたら、前日の18時までに予約をしておかないといけないらしい。残念だが諦める。普通の月曜日だというのに、5時30分には結構、多くの人がいた。その前日の日曜日だったら、相当、人がいたであろう。コロナなのに、あまり人は行動を抑制していないようだ。って、人のことは言えない。バスは時間通り出発し、6時55分頃に畳平に到着。なんと気温は6度。相当、寒い。ちょっと高山病的な気分のよくなさはあるが、まあ、これぐらいなら大丈夫。大事をとってゆっくりと進んでいく。天気は最高によい。まさに三度目の正直。

(バスターミナルからも剣が峰が見える。三度目の挑戦で初めての晴天)

(9月13日であるにも関わらず、畳平は6度という寒さ)

(畳平からの登山口の入り口)
お花畑を右手に見つつ、歩を進めると砂利道の車道に出る。これは歩くのは楽だが、味気ない。ただ、そこから左手に広がる展望は素晴らしいの一言につきる。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳とが見える。しばらく歩くと、肩の小屋に着く。時間的には7時40分。ここからは、登山道。レキが多い登山道で、ハイキングというよりかは登山という気分にさせられる。剣ヶ峰への登山道自体は、典型的な火山登山で、レキと低木で景観的には目を楽しませるものがないが、展望はもう特別に素晴らしい。雨や霧の日ではなく、この晴れの日に登山できたことはラッキーだ(いや、三回目にしてようやく晴れたというのが実態だが)。

(登山始めは右手に花畑をみながら歩いて行く)

(砂利道の車道を歩いて行く。素っ気ない登山道だが展望は素晴らしい)

(肩の小屋からは本格的な登山道が始まる)

(振り返ると北アルプスの素晴らしい展望が広がっている)

(百名山としては簡単に登れるといわれる乗鞍岳であるが、このレキを登っていくのは簡単ではない)

(乗鞍岳も火山であるのだな、ということがこの無味乾燥な登山道から理解できる)

(権現池の向こうには白山がみられる)
頂上小屋に着いたのは8時30分。ここでは珈琲も飲める。私はドリップ式の珈琲をもってきたのでここのは飲まなかったが、軽い荷物で上がっても肩の小屋では食事もできるし、頂上小屋では珈琲も飲める。なかなか充実したサービスが提供されている。この小屋からの展望も素晴らしいの一言で、北アルプス、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳ともう絶景を楽しめる。とはいえ、頂上はさらにいいだろうと20分ほど登ると頂上に着いた。頂上からはまさに360度の大展望が得られる。富士山が北岳の左側にちょこっと覗くように顔を出している。ちっちゃい、それほど威厳もないような富士山ではあるが、富士山が見えると見えないとでえらく得した感が違う。全然活躍しない大谷翔平でも、試合に出ているのを見ると嬉しいのとかと感覚は近いのかもしれない。ここでカップ麺を食べ、珈琲を飲み、帰路に着く。下り始めたのは9時30分ぐらいだ。

(頂上小屋では珈琲を飲むことができる)

(頂上小屋から南アルプスを展望する)

(御岳山も見ることができる)

(頂上から南アルプス方面を展望する)
下りは比較的早めのペースで降りて行った。これはバスが一時間に一本しか走っていないからで、10時05分は無理だが、その次には乗りたかったからである。そのためにはコースタイム通りで下山しないといけない。今回はストックを敢えてもたずに登山をしたが、膝にくることもなく、太股の筋肉にも特にハリは出来ず、無事に11時頃には下山することができた。11時05分発のバスに乗って、バスターミナルに戻ったのは11時50分。宿泊した宿が帰りに温泉に寄っていいと言ってくれたのでお言葉に甘えて行く。記念すべき百名山の50座目は、特に危険もなく、楽しい登山であった。

(下山もずっと素晴らしい展望を楽しむことができる。これは乗鞍岳登山の魅力である。ただし、晴れていないといけないが)
タグ:乗鞍岳
火打山(日本百名山49座登頂) [日本百名山]
前日の妙高山に次いで、火打山にチャレンジする。黒沢池ヒュッテの朝食を4時30分にとり、5時30分に出発。ちなみに朝食はクレープにジャム、ツナ缶、缶詰の桜桃、スープに珈琲であった。ヒュッテは冷蔵庫が使えないのでそのようなメニューとなる。珈琲が美味しい。さて、今日は昨日とは打って変わった好天気である。「天気とくらす」での予報は、火打山は「C評価(登山に適していない)」であったが、今日は千載一遇の登山日和である。ここらへんの予報はなかなか当たらないと改めて思う。

<茶臼山の登山道から後ろを振り返ると昨日はみられなかった妙高山がその姿を現していた>

<茶臼山の登山道は尾根道なので、左手には日本海が見られる>

<雷菱の印象的な赤い壁を望む>

<登山道の両側はクマザサが群生している>

<高谷池の湿原>
さて黒沢池からは茶臼山を乗り越えて高谷池ヒュッテに向かうことになる。この茶臼山はいっきなり結構の登りがあるので起きたばかりの身体には結構、負荷がある。振り返ると昨日はまったくその姿をみられなかった妙高山がその雄壮たる姿を現している。日本海も見られ、この尾根道は気持ちがよい。さて、ただ茶臼山の山頂からは木に邪魔され展望が得られない。茶臼山の山頂から写真を撮ろうと考えないで、その手前で撮ることをお勧めする。さらに、茶臼山から東側(黒沢池ヒュッテ側)は比較的、クマザサが刈られていて歩きやすいが、高谷池ヒュッテ側はそこらへんが管理されず、歩きにくい。特にヒュッテに近いところは、沢を降りる形になるが、岩と泥の中を歩いて行くのは結構、しんどいものがあった。

<火打山をバックにした高谷池>

<高谷池ヒュッテ>
さて、高谷池ヒュッテには7時ちょっと前に着く。荷物を置き、身軽になって再チャレンジする。高谷池ヒュッテは目の前に高谷池の湿原が広がり、早朝の光の中、高山湿原の素晴らしさを身体全体で感じる。晴れていると本当に、高山湿原は素晴らしい。高谷池ヒュッテからは火打山の壮麗なる姿が高谷池の向こう側に見える。妙高山のような特異な形状ではなく、円錐型の山らしい形をした山である。火打山、影火打山、焼山の山塊をバックにした、この湿原は極めてフォトジェニックで素晴らしい。昨日の雨で空のホコリが流されたからだと思われるが、早朝の光が、山、池、樹木を素晴らしい色で照らしている。

<素晴らしい高原湿原>

<高原湿原は木道で歩いて行くので快適だ>

<ふと振り返ると妙高山のユニークな形を確認することができる>
高谷池ヒュッテを出発したのは7時ちょうどぐらい。ここから火打山までの2時間弱の登山は天気が素晴らしいこともあったが、相当、優れた登山体験を提供してくれる。妙高山の理不尽に近い、修行のような厳しさとは違い、登山の楽しさを体感させてくれるようなルートである。これは、登山道の不安定な場所はところどころ木道が整備されているなどして歩きやすくなっていることに加えて、管理も行き届いているからであろう。隣同士にある百名山であるにも関わらず、この登山環境の差は驚くものがある。一方はフルサービスの美味しい料理を提供してくれるフレンチ・レストランであるとすれば、もう一方はセルフサービスのうどん屋のような感じである。

<天狗の庭と火打山>

<火打山と逆さ火打>

<妙高山>

<さっきまで見えていた北アルプスが雲で覆われ始める>

<火打山の山頂>


<火打山からは360度の見事な展望を得ることができた>
高谷池ヒュッテを過ぎて15分ぐらい行くと「天狗の庭」という高山湿原がある。この湿原も見事である。ここらへんはすべて木道であるので歩きは快適だ。この湿原歩きは、高谷池ヒュッテから火打山登山のハイライトの一つであろう。湿原が終わると坂が始まる。坂は比較的、急だが、昨日の妙高山に比べればずっと楽である。坂もそれほどは急でないのに加え、登山道が管理されているので歩きやすいからだ。さらには、尾根道なので右手に日本海、左手に高妻山、さらに前方には北アルプスの山容、振り返れば妙高山が展望できる。まさに空中散歩のような気分で標高を上げていくことができ、登山の醍醐味を味わうことができる。山頂の直前には階段があり、これはこれできついが、機械的なモーションで上がっていくと山頂がいきなり目の前に広がる。山頂に着いた時は、急激に発達した水蒸気で北アルプスこそは展望が得られなかったが、それ以外は昨日とは打って変わって素晴らしい展望が広がる。あと15分ほど早く着いたら、北アルプスも見られたかもしれないが、逆にあと15分ほど遅れて着いたら、今、見られているものも雲で隠されていたかもしれない。昨日まで振っていた大量の水分が、今日の晴天と高温で凄い勢いで水蒸気となって山を覆い始めているからだ。山頂にはコースタイムより時間を取り、9時ちょっと前に到着。しばらく展望を楽しんで、帰路に着く。出発時間は9時。

<登山道の真っ直ぐ先に見える妙高山>
帰路も気持ちよく降りて行ったのだが、ふと振り返ると雲が火打山の山頂を覆い始めている。本当、登山はタイミングだなとつくづく思わされる。我々は満点ではなかったかもしれないが、97点ぐらいのタイミングのよさだなと思う。高谷池ヒュッテに到着したのは、10時20分。ここで昼ご飯を取る。昼ご飯といっても、高谷池ヒュッテで購入できるのはカップ麺か、カップ飯。私はカップ麺を買う。カップ麺のごみも持って帰らなくてはいけないのは負担だが、カップ麺に入れるお湯とかをヒュッテが提供してくれるのは有り難い。山小屋があると、もってくる荷物がグッと減るので本当、有り難い。食事をして、最後の火打山の勇姿を満喫して、帰路に着く。出発時間は11時である。

<富士見平分岐でふと空を見上げると夏らしい色合いの青空>

<美しい苔に覆われた倒木>

<十二曲り>

<登山道沿いには多くのキノコが生えている>

<黒沢橋そばの黒沢の清流>

<登山道入り口に戻る。ほぼ34時間ぶり>
高谷池ヒュッテから富士見分岐までは黒沢池ヒュッテ側と違って谷道で、沢のような泥々としたところを歩いて行く。富士見平分岐は12時頃に到着。そこからは急坂を下りていく。なかなかの急坂で膝への負担を気にしつつ、丁寧に降りて行く。そして、12曲りを経て、黒沢橋。黒沢橋からはほぼ平らの木道で歩くのは楽。ただ、足の親指に水ぶくれのようなものができたので、それをかばいつつ降りて行く。あと、随分と温度があがってきたので若干、熱中症が気になる。十二分の水分を摂取しながらある一会区。笹ヶ峰キャンプ場に着いたのは14時15分。昨日の妙高山登山とほぼ同じ距離を歩いたが、登りと下りという差はあるが、疲労度は全然、違う。杉ノ原スキー場にある苗名の湯で汗を流し、帰路に着いた。
登山道整備度 ★★★☆☆ (ヒュッテから山頂までしっかりと整備されているが、妙高との分岐点からヒュッテまでは歩きにくい)
岩場度 ★☆☆☆☆ (手を使わないといけないような岩場もなく、快適な登山が楽しめる)
登山道ぬかるみ度 ★★★★☆ (妙高との分岐点からヒュッテまでは相当のぬかるみ)
虫うっとうしい度 ★★★☆☆ (虫はヒュッテまでは結構いる)
展望度 ★★★★☆ (相当、素晴らしい展望が得られる。妙高山などが美しい)
駐車場アクセス度 ★★★★★ (登山口の駐車場は相当、優れていると思われる)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (山小屋があるので、それほど心配しなくてもいいかも)
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (ちょっと駐車場から走らないといけない)
安全度 ★★★☆☆ (ヒュッテから山頂まで登山道はしっかりと整備されているが、ヒュッテまではぬかるみ道などもあり、必ずしも安心とはいえない)

<茶臼山の登山道から後ろを振り返ると昨日はみられなかった妙高山がその姿を現していた>

<茶臼山の登山道は尾根道なので、左手には日本海が見られる>

<雷菱の印象的な赤い壁を望む>

<登山道の両側はクマザサが群生している>

<高谷池の湿原>
さて黒沢池からは茶臼山を乗り越えて高谷池ヒュッテに向かうことになる。この茶臼山はいっきなり結構の登りがあるので起きたばかりの身体には結構、負荷がある。振り返ると昨日はまったくその姿をみられなかった妙高山がその雄壮たる姿を現している。日本海も見られ、この尾根道は気持ちがよい。さて、ただ茶臼山の山頂からは木に邪魔され展望が得られない。茶臼山の山頂から写真を撮ろうと考えないで、その手前で撮ることをお勧めする。さらに、茶臼山から東側(黒沢池ヒュッテ側)は比較的、クマザサが刈られていて歩きやすいが、高谷池ヒュッテ側はそこらへんが管理されず、歩きにくい。特にヒュッテに近いところは、沢を降りる形になるが、岩と泥の中を歩いて行くのは結構、しんどいものがあった。

<火打山をバックにした高谷池>

<高谷池ヒュッテ>
さて、高谷池ヒュッテには7時ちょっと前に着く。荷物を置き、身軽になって再チャレンジする。高谷池ヒュッテは目の前に高谷池の湿原が広がり、早朝の光の中、高山湿原の素晴らしさを身体全体で感じる。晴れていると本当に、高山湿原は素晴らしい。高谷池ヒュッテからは火打山の壮麗なる姿が高谷池の向こう側に見える。妙高山のような特異な形状ではなく、円錐型の山らしい形をした山である。火打山、影火打山、焼山の山塊をバックにした、この湿原は極めてフォトジェニックで素晴らしい。昨日の雨で空のホコリが流されたからだと思われるが、早朝の光が、山、池、樹木を素晴らしい色で照らしている。

<素晴らしい高原湿原>

<高原湿原は木道で歩いて行くので快適だ>

<ふと振り返ると妙高山のユニークな形を確認することができる>
高谷池ヒュッテを出発したのは7時ちょうどぐらい。ここから火打山までの2時間弱の登山は天気が素晴らしいこともあったが、相当、優れた登山体験を提供してくれる。妙高山の理不尽に近い、修行のような厳しさとは違い、登山の楽しさを体感させてくれるようなルートである。これは、登山道の不安定な場所はところどころ木道が整備されているなどして歩きやすくなっていることに加えて、管理も行き届いているからであろう。隣同士にある百名山であるにも関わらず、この登山環境の差は驚くものがある。一方はフルサービスの美味しい料理を提供してくれるフレンチ・レストランであるとすれば、もう一方はセルフサービスのうどん屋のような感じである。

<天狗の庭と火打山>

<火打山と逆さ火打>

<妙高山>

<さっきまで見えていた北アルプスが雲で覆われ始める>

<火打山の山頂>


<火打山からは360度の見事な展望を得ることができた>
高谷池ヒュッテを過ぎて15分ぐらい行くと「天狗の庭」という高山湿原がある。この湿原も見事である。ここらへんはすべて木道であるので歩きは快適だ。この湿原歩きは、高谷池ヒュッテから火打山登山のハイライトの一つであろう。湿原が終わると坂が始まる。坂は比較的、急だが、昨日の妙高山に比べればずっと楽である。坂もそれほどは急でないのに加え、登山道が管理されているので歩きやすいからだ。さらには、尾根道なので右手に日本海、左手に高妻山、さらに前方には北アルプスの山容、振り返れば妙高山が展望できる。まさに空中散歩のような気分で標高を上げていくことができ、登山の醍醐味を味わうことができる。山頂の直前には階段があり、これはこれできついが、機械的なモーションで上がっていくと山頂がいきなり目の前に広がる。山頂に着いた時は、急激に発達した水蒸気で北アルプスこそは展望が得られなかったが、それ以外は昨日とは打って変わって素晴らしい展望が広がる。あと15分ほど早く着いたら、北アルプスも見られたかもしれないが、逆にあと15分ほど遅れて着いたら、今、見られているものも雲で隠されていたかもしれない。昨日まで振っていた大量の水分が、今日の晴天と高温で凄い勢いで水蒸気となって山を覆い始めているからだ。山頂にはコースタイムより時間を取り、9時ちょっと前に到着。しばらく展望を楽しんで、帰路に着く。出発時間は9時。

<登山道の真っ直ぐ先に見える妙高山>
帰路も気持ちよく降りて行ったのだが、ふと振り返ると雲が火打山の山頂を覆い始めている。本当、登山はタイミングだなとつくづく思わされる。我々は満点ではなかったかもしれないが、97点ぐらいのタイミングのよさだなと思う。高谷池ヒュッテに到着したのは、10時20分。ここで昼ご飯を取る。昼ご飯といっても、高谷池ヒュッテで購入できるのはカップ麺か、カップ飯。私はカップ麺を買う。カップ麺のごみも持って帰らなくてはいけないのは負担だが、カップ麺に入れるお湯とかをヒュッテが提供してくれるのは有り難い。山小屋があると、もってくる荷物がグッと減るので本当、有り難い。食事をして、最後の火打山の勇姿を満喫して、帰路に着く。出発時間は11時である。

<富士見平分岐でふと空を見上げると夏らしい色合いの青空>

<美しい苔に覆われた倒木>

<十二曲り>

<登山道沿いには多くのキノコが生えている>

<黒沢橋そばの黒沢の清流>

<登山道入り口に戻る。ほぼ34時間ぶり>
高谷池ヒュッテから富士見分岐までは黒沢池ヒュッテ側と違って谷道で、沢のような泥々としたところを歩いて行く。富士見平分岐は12時頃に到着。そこからは急坂を下りていく。なかなかの急坂で膝への負担を気にしつつ、丁寧に降りて行く。そして、12曲りを経て、黒沢橋。黒沢橋からはほぼ平らの木道で歩くのは楽。ただ、足の親指に水ぶくれのようなものができたので、それをかばいつつ降りて行く。あと、随分と温度があがってきたので若干、熱中症が気になる。十二分の水分を摂取しながらある一会区。笹ヶ峰キャンプ場に着いたのは14時15分。昨日の妙高山登山とほぼ同じ距離を歩いたが、登りと下りという差はあるが、疲労度は全然、違う。杉ノ原スキー場にある苗名の湯で汗を流し、帰路に着いた。
登山道整備度 ★★★☆☆ (ヒュッテから山頂までしっかりと整備されているが、妙高との分岐点からヒュッテまでは歩きにくい)
岩場度 ★☆☆☆☆ (手を使わないといけないような岩場もなく、快適な登山が楽しめる)
登山道ぬかるみ度 ★★★★☆ (妙高との分岐点からヒュッテまでは相当のぬかるみ)
虫うっとうしい度 ★★★☆☆ (虫はヒュッテまでは結構いる)
展望度 ★★★★☆ (相当、素晴らしい展望が得られる。妙高山などが美しい)
駐車場アクセス度 ★★★★★ (登山口の駐車場は相当、優れていると思われる)
トイレ充実度 ★★★☆☆ (山小屋があるので、それほど心配しなくてもいいかも)
下山後の温泉充実度 ★★☆☆☆ (ちょっと駐車場から走らないといけない)
安全度 ★★★☆☆ (ヒュッテから山頂まで登山道はしっかりと整備されているが、ヒュッテまではぬかるみ道などもあり、必ずしも安心とはいえない)
妙高山(日本百名山48座登頂) [日本百名山]
妙高山にトライする。前日、妙高高原のホテルに泊まり、5時にはホテルを発つ。笹ヶ峰のキャンプ場の駐車場に向かう。雨天の予報もあり、小雨が降っている中、キャンプ場の駐車場にはほとんど車がいない。準備をして6時頃に笹ヶ峰の登山口から出発する。最初はブナ林の木道を歩いて行く。緩やかに登っていくが、ほとんど難しいところはない。小雨が降っているがブナの木々がその勢いを柔らかくしてくれる。ほぼ1時間ぐらいで黒沢橋を渡る。そして、すぐに12曲りと呼ばれる急坂に届く。なかなかの急坂であるが、それを越えて、しばらく行くとさらに急坂に出る。こちらの方がむしろ12曲りよりも難敵だ。ただ、この頃になると雨足が弱くなってくるのが救いとなる。ここらへんは尾根道であるが、木々に覆われているので、そして、そもそも雲に覆われていて、ほとんど展望も得られない。

<登山口>

<黒沢橋>

<黒沢の急流>

<雲に覆われて展望は得られにくいが、雨足は弱い。雨に濡れたブナ林の緑が美しい>
坂が緩やかになってしばらく歩くと富士見平分岐に出る。ほぼ9時頃である。ここは、火打山方面と妙高山方面とにの分岐点である。右に折れて妙高山方面の道を行く。緩やかに高度を下げるような形で黒沢池のある湿原を歩いて行く。この湿原の淵を通る登山道は木道がしっかりと整備されていて歩きやすい。相変わらず、雲に覆われてはいるが、湿原は展望できるて、気持ちよく距離を稼ぐことができる。そして、この湿原と山の淵に黒沢池ヒュッテが建つ。ドーム型の特徴的な意匠が目を惹くこの山小屋を設計したのは、吉阪隆正氏である。ル・コルビュジエに師事した建築家として知られる氏であるが、大学時代は山岳部に所属し、大の登山家であった。その吉阪氏の設計なので、それは山小屋としても秀でた建築であるのは間違いない。この日はこの山小屋に泊まるので、入らない荷物をここに置かさせてもらい、妙高山の山頂へと向かう。黒沢池ヒュッテを発ったのは10時30分。黒沢池ヒュッテの東には大倉山が聳える。これを越えなくてはいけないのだが、じめじめした沢を登っていくので決して気持ちいい感じではない。この頃には雨も晴れたこともあり、虫が多い。大倉山乗越の峠に着いたのは30分後。



<黒沢池のある湿原。気持ちが晴れるような気持ちよい景色の中を歩く>

<40分ほど湿原を歩くと、黒沢池ヒュッテのユニークな意匠が姿を現す>

<巨匠吉阪隆正のデザインによる建物である>
さて、それからは大倉山と妙高山の二つの山の狭間の谷に降りていかなくてはならないのだが、これがとんでもない難路であった。それは途中、崩落箇所が幾つかあり、しかも登山道にはクマザサの根が張っているのだが、これを踏むと横に滑るのだ。そして、滑る先は崖。後で、黒沢池ヒュッテの管理者に聞いたのだが、やはり、ここで滑り、滑落する人達は結構多く、そのたびにレスキューをしにいくのだそうだ。ある人の場合は、結局、それらのレスキュー隊でも脱出させられずに消防署に来てもらったケースもあるそうだ。めちゃくちゃ危ないな、と歩いていた時にも思っていたが、実際、滑落した人も少なくなく、そして滑落すると自力では脱出できない。ここを歩いていた時に、環境省はもっとしっかりと国立公園の登山道を整備しろ、と心の中で毒まいていたのだが、実際、この歩道は問題視されているらしく、今度、新しい登山道を整備する計画があるそうだ。ということで、妙高山に登山を考えている人は、この登山道が出来た後にチャレンジされるといいかと考える。そう思わせるぐらい、この大蔵乗越から長助池の現行のルートは歩いても楽しくないし、危険である。というか、このルートを取るぐらいなら、妙高高原スカイケーブルを用いたルートを取るべきであろう。
長助池分岐には、水が溢れていて気持ちいいのだが、生憎、蚊が多くいたこともあり、ゆっくりと休ませてはくれなかった。そこを12時過ぎに早々と立ち、妙高山を登り始める。妙高山は山頂が全方位とも崖のような急斜面であり、長助池分岐からもちょっと緩やかな沢のようなところを登ると、クライミングのような急登が現れる。妙高山は、映画「E.T.」で有名になったワイオミング州のデビルズ・タワーのような形状をしているので、最後の登りがまさに絶壁を登るような感じとなっているのだ。この急登は半端なく厳しく、息が上がり続け、途中、目の前が暗くなりそうな状態にもなる。相方がおらず、一人で登っていたら、とても登り切ることはできなかったであろう。呼吸のリズムを気にしながら、とりあえず気絶するようになることは避け、ゆっくりと一歩一歩進んでいく。すると、どうにか妙高山の山頂に到着することができた。到着時間は13時30分。

<妙高山の北峰>
山頂はガスでほとんど何も見られない状況であるが、「天気とくらす」の予測ほど風は強くなかった。雨が降っていないことはせめてもの救いである。妙高山には二つの山頂がある。足はもうガクガクであったが、頑張って南峰へといく。途中、日本岩という巨岩があるロック・ガーデンのような場所がある。晴れていたら、さぞかし綺麗だろうが、こうガスが出ているとあまりその凄さが感じられない。

<北峰と南峰の中間には巨岩がゴロゴロ転がっているロック・ガーデンのような場所がある>

<妙高山南峰>

<頂上からは絶景が望めるはずなのだが、ガスに覆われてほとんど何も見られない>
満身創痍に近かったので、頂上で10分間ほど横になって休憩を取る。そして、14時頃から下山を開始する。登りが厳しいということは、下りも厳しいということだ。それほどゆっくりと降りた積もりはないのだが、コースタイムより10分も遅く、長助池に到着する。ここの泉で顔を洗い、身体を冷やす。冷たい水を身体が喜ぶ。さて、ここから大倉乗越は登り。なんで、ここで登るのかと思うが、疲れ切った身体にむち打ち、また滑落しないよう気を張ってトラバースをする。この登山道は、繰り返しになるが、とても百名山の登山道と思えないほど酷い。ただ、後で黒沢池ヒュッテの管理者に聞いた話だが、ここらへんの登山道の管理はボランティア任せらしい。ボランティアは人手が足りず、また、重作業なのでなかなか管理ができないというのが実情らしい。例えば関温泉からのルートはクマザサに登山道が覆われ、道をみつけるのも難しいような状況だそうだ。多少、関温泉からのルートを考えていたこともあったので、つくづくそのルートを取らなくてよかった。

<この日の登山で唯一の青空が見えた瞬間>
さて、大倉乗越を過ぎると、あとは下り。ただ、この下りも沢のような道を降りていくので気をつけないといけない。ゆっくりと慎重に降りていき、黒沢池ヒュッテに到着。到着したのは16時30分であった。今日はこちらで泊まる。コロナが感染拡大していることもあってか、宿泊者は私と同行者の二人だけ。管理人も我々も皆、ワクチンを二回接種しているので、まず安心だ。ということで、極めてコロナ・フリーな山小屋泊となった。コロナの山登りの必須品であるマイ・シーツを敷いて、夕ご飯のシチューを食べると、速攻で眠りに落ちる。明日は火打山である。

<登山口>

<黒沢橋>

<黒沢の急流>

<雲に覆われて展望は得られにくいが、雨足は弱い。雨に濡れたブナ林の緑が美しい>
坂が緩やかになってしばらく歩くと富士見平分岐に出る。ほぼ9時頃である。ここは、火打山方面と妙高山方面とにの分岐点である。右に折れて妙高山方面の道を行く。緩やかに高度を下げるような形で黒沢池のある湿原を歩いて行く。この湿原の淵を通る登山道は木道がしっかりと整備されていて歩きやすい。相変わらず、雲に覆われてはいるが、湿原は展望できるて、気持ちよく距離を稼ぐことができる。そして、この湿原と山の淵に黒沢池ヒュッテが建つ。ドーム型の特徴的な意匠が目を惹くこの山小屋を設計したのは、吉阪隆正氏である。ル・コルビュジエに師事した建築家として知られる氏であるが、大学時代は山岳部に所属し、大の登山家であった。その吉阪氏の設計なので、それは山小屋としても秀でた建築であるのは間違いない。この日はこの山小屋に泊まるので、入らない荷物をここに置かさせてもらい、妙高山の山頂へと向かう。黒沢池ヒュッテを発ったのは10時30分。黒沢池ヒュッテの東には大倉山が聳える。これを越えなくてはいけないのだが、じめじめした沢を登っていくので決して気持ちいい感じではない。この頃には雨も晴れたこともあり、虫が多い。大倉山乗越の峠に着いたのは30分後。



<黒沢池のある湿原。気持ちが晴れるような気持ちよい景色の中を歩く>

<40分ほど湿原を歩くと、黒沢池ヒュッテのユニークな意匠が姿を現す>

<巨匠吉阪隆正のデザインによる建物である>
さて、それからは大倉山と妙高山の二つの山の狭間の谷に降りていかなくてはならないのだが、これがとんでもない難路であった。それは途中、崩落箇所が幾つかあり、しかも登山道にはクマザサの根が張っているのだが、これを踏むと横に滑るのだ。そして、滑る先は崖。後で、黒沢池ヒュッテの管理者に聞いたのだが、やはり、ここで滑り、滑落する人達は結構多く、そのたびにレスキューをしにいくのだそうだ。ある人の場合は、結局、それらのレスキュー隊でも脱出させられずに消防署に来てもらったケースもあるそうだ。めちゃくちゃ危ないな、と歩いていた時にも思っていたが、実際、滑落した人も少なくなく、そして滑落すると自力では脱出できない。ここを歩いていた時に、環境省はもっとしっかりと国立公園の登山道を整備しろ、と心の中で毒まいていたのだが、実際、この歩道は問題視されているらしく、今度、新しい登山道を整備する計画があるそうだ。ということで、妙高山に登山を考えている人は、この登山道が出来た後にチャレンジされるといいかと考える。そう思わせるぐらい、この大蔵乗越から長助池の現行のルートは歩いても楽しくないし、危険である。というか、このルートを取るぐらいなら、妙高高原スカイケーブルを用いたルートを取るべきであろう。
長助池分岐には、水が溢れていて気持ちいいのだが、生憎、蚊が多くいたこともあり、ゆっくりと休ませてはくれなかった。そこを12時過ぎに早々と立ち、妙高山を登り始める。妙高山は山頂が全方位とも崖のような急斜面であり、長助池分岐からもちょっと緩やかな沢のようなところを登ると、クライミングのような急登が現れる。妙高山は、映画「E.T.」で有名になったワイオミング州のデビルズ・タワーのような形状をしているので、最後の登りがまさに絶壁を登るような感じとなっているのだ。この急登は半端なく厳しく、息が上がり続け、途中、目の前が暗くなりそうな状態にもなる。相方がおらず、一人で登っていたら、とても登り切ることはできなかったであろう。呼吸のリズムを気にしながら、とりあえず気絶するようになることは避け、ゆっくりと一歩一歩進んでいく。すると、どうにか妙高山の山頂に到着することができた。到着時間は13時30分。

<妙高山の北峰>
山頂はガスでほとんど何も見られない状況であるが、「天気とくらす」の予測ほど風は強くなかった。雨が降っていないことはせめてもの救いである。妙高山には二つの山頂がある。足はもうガクガクであったが、頑張って南峰へといく。途中、日本岩という巨岩があるロック・ガーデンのような場所がある。晴れていたら、さぞかし綺麗だろうが、こうガスが出ているとあまりその凄さが感じられない。

<北峰と南峰の中間には巨岩がゴロゴロ転がっているロック・ガーデンのような場所がある>

<妙高山南峰>

<頂上からは絶景が望めるはずなのだが、ガスに覆われてほとんど何も見られない>
満身創痍に近かったので、頂上で10分間ほど横になって休憩を取る。そして、14時頃から下山を開始する。登りが厳しいということは、下りも厳しいということだ。それほどゆっくりと降りた積もりはないのだが、コースタイムより10分も遅く、長助池に到着する。ここの泉で顔を洗い、身体を冷やす。冷たい水を身体が喜ぶ。さて、ここから大倉乗越は登り。なんで、ここで登るのかと思うが、疲れ切った身体にむち打ち、また滑落しないよう気を張ってトラバースをする。この登山道は、繰り返しになるが、とても百名山の登山道と思えないほど酷い。ただ、後で黒沢池ヒュッテの管理者に聞いた話だが、ここらへんの登山道の管理はボランティア任せらしい。ボランティアは人手が足りず、また、重作業なのでなかなか管理ができないというのが実情らしい。例えば関温泉からのルートはクマザサに登山道が覆われ、道をみつけるのも難しいような状況だそうだ。多少、関温泉からのルートを考えていたこともあったので、つくづくそのルートを取らなくてよかった。

<この日の登山で唯一の青空が見えた瞬間>
さて、大倉乗越を過ぎると、あとは下り。ただ、この下りも沢のような道を降りていくので気をつけないといけない。ゆっくりと慎重に降りていき、黒沢池ヒュッテに到着。到着したのは16時30分であった。今日はこちらで泊まる。コロナが感染拡大していることもあってか、宿泊者は私と同行者の二人だけ。管理人も我々も皆、ワクチンを二回接種しているので、まず安心だ。ということで、極めてコロナ・フリーな山小屋泊となった。コロナの山登りの必須品であるマイ・シーツを敷いて、夕ご飯のシチューを食べると、速攻で眠りに落ちる。明日は火打山である。
谷川岳(日本百名山47座登頂) [日本百名山]
昨年の12月に足首を捻挫した。それ以来、初めての登山にチャレンジした。谷川岳ならどうにか登れるかも、ということでいろいろと不安はあったが挑戦してみた。難しければ、戻る覚悟をしてでの挑戦である。朝、5時ぐらいに家を出ようと思っていたのだが、なかなか寝付けず、結局、目が覚めたのは6時過ぎであった。ただ、急いで用意をして出発をしたら7時前に家を出ることができた。
オリンピック開催中ということや、四連休の最終日ということもあり、道路は空いており、谷川岳のロープウェイの駐車場に到着したのは10時前ぐらいであった。ロープウェイの運賃は往復で2100円。3分間隔で動いているので凄い輸送力である。ロープウェイに乗車したのは10時20分。15分で天神平駅に着く。その後、リフトに乗ると170メートルぐらいは標高で得をするが、そのまま歩き始める。高原植物が多く咲いていて目を楽しませてくれる
さて、ひさりぶりの登山ということもあり、丁寧にゆっくりと登っていく。登り始めてすぐ、ストックを車のトランクに置きっぱなしにしていることに気づくが後の祭りだ。これは、下りで足に来るだろうと予測するが、その予測は当たる。ただし、予測していた膝ではなく、太股に来たが。
その後、ガスは出るのだが、このときは天気も良く、随分と暑く、熱中症を気にするような感じであった。早めに経口補水液などを飲み、熱中症にならないように気をつける。しばらく行くと、リフトからのトレイルと合流し、さらにしばらく歩くと熊穴沢避難小屋に着く。11時15分だ。それからしばらく行くと、急斜面となる。ヒモもあり、鎖場もあり、なかなか厳しいが、登りに関しては鎖に頼らなくても登れる程度の斜度である。ただ、急斜面がずっと続くので太股には結構、厳しい。天狗の腰掛け岩を過ぎ、天狗の留まり場に着いたのが12時ちょうど。ここから山の方はクマザサの緑が絨毯のように広がり、美しい。
ここらへんから雲が発達してきて、展望は得られなくなるが、涼しいのはちょっと助かる。そのまま肩の小屋に行き、休むかとも考えたが、一瞬、晴れ間が雲の中に見えたので一気に登ることとする。とはいえ、ここらへんで太股が相当、張ってくる。膝のサポーターを太股に巻くと状況はよくはなった。しかし、ここで痙攣すると、あとあと大変なことになるので、だましだまし歩いて行く。トマの耳までは、ここからだとすぐ。登頂したのは13時ちょうど。ここで休憩とし、昼食を取る。タイツの上から筋肉痛のためのサロンパスのスプレーを吹く。30分ほど滞在したが、雲が凄い勢いでまた視界を遮り、ほとんど何も見えなかった。さて、そこからオキの耳まではアップ・ダウンのある岩場を15分ほど行く。登頂時は13時45分だ。最終のロープウェイの時間は17時ということで急いで帰路に着く。
帰路の下山時は、もう太股との格闘だ。ただ、ちょっと休めば状況は改善するので、時間はかかるがゆっくりと降りればいいだけの話である。天狗の留まり場を通過したのは14時20分。そして、天狗の腰掛け岩ではゆっくりと休憩。到着時は15時。そこからは太股への負担も特になく降りられたので、天神平駅に到着したのは15時45分であった。
四連休の最終日ということもあり、ハイキング的な格好で登っている人を数人、見かけた。鎖場などは、降りることに難儀をしていて、見ていてハラハラさせられた。谷川岳はアクセスがいいので、ちょっとハイキング気分で来られる人も多いのかもしれないが、リフトで天神峠に行くぐらいで留めた方がいいのではないだろうか。ロープウェイで高度は稼げるが、この登山は結構、厳しい。同じ百名山でも八幡平、筑波山、霧ヶ峰、大台ヶ原などとは全然、違う。というか、ちゃんとした登山である。
その後、湯テルメ・谷川で汗を流したが、この町営の温泉施設はとてもよかった。

ロープウェイから東にある朝日岳の方角を望む

ロープウェイの天神平駅周辺はワイルドフラワーが咲き乱れていて、目に楽しい

ロープウェイの駅からしばらくはブナ林の中を歩いて行く

木道が整備されていて、急登が始まるまでは歩きやすい

急登は始まると、以後、ほとんど同じような斜度が続く。これは相当、きつい。


天狗の留まり場から上は笹に覆われた緑が眩しい

天狗の留まり場から肩の小屋までも急坂が続く

とりあえず証拠写真

これも証拠写真

トマの耳からは360度の展望が得られるらしいが、雲でほとんど何も見えず

たまに雲の合間から雄大であろう景色の一部を見ることができる

天狗の腰掛け岩周辺。熊穴沢避難小屋からは階段を上るような急登。初級者には厳しい山かと思う。

天狗の腰掛け岩から南東方向を望む

登山後の温泉は谷川温泉の湯テルメ・谷川がいいかと思う。露天風呂は野趣溢れる。
オリンピック開催中ということや、四連休の最終日ということもあり、道路は空いており、谷川岳のロープウェイの駐車場に到着したのは10時前ぐらいであった。ロープウェイの運賃は往復で2100円。3分間隔で動いているので凄い輸送力である。ロープウェイに乗車したのは10時20分。15分で天神平駅に着く。その後、リフトに乗ると170メートルぐらいは標高で得をするが、そのまま歩き始める。高原植物が多く咲いていて目を楽しませてくれる
さて、ひさりぶりの登山ということもあり、丁寧にゆっくりと登っていく。登り始めてすぐ、ストックを車のトランクに置きっぱなしにしていることに気づくが後の祭りだ。これは、下りで足に来るだろうと予測するが、その予測は当たる。ただし、予測していた膝ではなく、太股に来たが。
その後、ガスは出るのだが、このときは天気も良く、随分と暑く、熱中症を気にするような感じであった。早めに経口補水液などを飲み、熱中症にならないように気をつける。しばらく行くと、リフトからのトレイルと合流し、さらにしばらく歩くと熊穴沢避難小屋に着く。11時15分だ。それからしばらく行くと、急斜面となる。ヒモもあり、鎖場もあり、なかなか厳しいが、登りに関しては鎖に頼らなくても登れる程度の斜度である。ただ、急斜面がずっと続くので太股には結構、厳しい。天狗の腰掛け岩を過ぎ、天狗の留まり場に着いたのが12時ちょうど。ここから山の方はクマザサの緑が絨毯のように広がり、美しい。
ここらへんから雲が発達してきて、展望は得られなくなるが、涼しいのはちょっと助かる。そのまま肩の小屋に行き、休むかとも考えたが、一瞬、晴れ間が雲の中に見えたので一気に登ることとする。とはいえ、ここらへんで太股が相当、張ってくる。膝のサポーターを太股に巻くと状況はよくはなった。しかし、ここで痙攣すると、あとあと大変なことになるので、だましだまし歩いて行く。トマの耳までは、ここからだとすぐ。登頂したのは13時ちょうど。ここで休憩とし、昼食を取る。タイツの上から筋肉痛のためのサロンパスのスプレーを吹く。30分ほど滞在したが、雲が凄い勢いでまた視界を遮り、ほとんど何も見えなかった。さて、そこからオキの耳まではアップ・ダウンのある岩場を15分ほど行く。登頂時は13時45分だ。最終のロープウェイの時間は17時ということで急いで帰路に着く。
帰路の下山時は、もう太股との格闘だ。ただ、ちょっと休めば状況は改善するので、時間はかかるがゆっくりと降りればいいだけの話である。天狗の留まり場を通過したのは14時20分。そして、天狗の腰掛け岩ではゆっくりと休憩。到着時は15時。そこからは太股への負担も特になく降りられたので、天神平駅に到着したのは15時45分であった。
四連休の最終日ということもあり、ハイキング的な格好で登っている人を数人、見かけた。鎖場などは、降りることに難儀をしていて、見ていてハラハラさせられた。谷川岳はアクセスがいいので、ちょっとハイキング気分で来られる人も多いのかもしれないが、リフトで天神峠に行くぐらいで留めた方がいいのではないだろうか。ロープウェイで高度は稼げるが、この登山は結構、厳しい。同じ百名山でも八幡平、筑波山、霧ヶ峰、大台ヶ原などとは全然、違う。というか、ちゃんとした登山である。
その後、湯テルメ・谷川で汗を流したが、この町営の温泉施設はとてもよかった。

ロープウェイから東にある朝日岳の方角を望む

ロープウェイの天神平駅周辺はワイルドフラワーが咲き乱れていて、目に楽しい

ロープウェイの駅からしばらくはブナ林の中を歩いて行く

木道が整備されていて、急登が始まるまでは歩きやすい

急登は始まると、以後、ほとんど同じような斜度が続く。これは相当、きつい。


天狗の留まり場から上は笹に覆われた緑が眩しい

天狗の留まり場から肩の小屋までも急坂が続く

とりあえず証拠写真

これも証拠写真

トマの耳からは360度の展望が得られるらしいが、雲でほとんど何も見えず

たまに雲の合間から雄大であろう景色の一部を見ることができる

天狗の腰掛け岩周辺。熊穴沢避難小屋からは階段を上るような急登。初級者には厳しい山かと思う。

天狗の腰掛け岩から南東方向を望む

登山後の温泉は谷川温泉の湯テルメ・谷川がいいかと思う。露天風呂は野趣溢れる。
塔ノ岳に登る(丹沢山未踏) [日本百名山]
そろそろ今年の登山シーズンも終わりである。ということで頑張って丹沢山にチャレンジすることにした。11月22日ということで日の出も遅いし、日の入りも早い。歩ける時間が短いということで相当、厳しい行程になるが、ガイドブックには「健脚の人なら日帰りも可能」と書いている。健脚ではないが、頑張ってチャレンジをすることにした。ただ、日の入りの時間を考えて、16時までには戻ってくることを胆に銘じる。
当日、起きたのは4時。ちょっと遅い。急いで支度をし、珈琲をつくり、おにぎりをつくって家を出る。家を出たのは5時過ぎ。これは、7時発かなと半ば諦めていたのだが、なんと菩提峠の駐車場には6時についた。そして念のためのヒル対策をして、登山を開始したのが6時15分。家を出たのが遅い割には、思ったより随分と早く出発できた。というか、丹沢、近すぎないか。こんなに近いのか、丹沢。
ちなみに丹沢に来るのは人生2度目。一度目は大学時代に彼女とドライブで縦断しただけだ。それ以来というか、歩きでは人生初めてである。丹沢にこんな近くに住んでいたのに。

<菩提峠の駐車場>
菩提峠からの登山口はよく分からず、違うところに行こうとしたのだが、他の登山者が違うルートをとっていたので間違いに気づいた。本当、登山は出だしが肝心だ。さて、菩提峠から二ノ塔までは、スギ林の急坂を歩いて行く。メインルートではないので、結構、道が分かりにくい。小一時間ぐらい歩くと、ようやく二ノ塔尾根のルートとぶつかる。ここからは尾根道で展望が広がって気持ちがよい。というか、結果的に富士山をしっかりと見られたのはこの尾根道からであった。とは、ここを歩いている時には夢にも思わなかった。これは、塔ノ岳からの富士山の展望は素晴らしいものがあると期待に胸を膨らませて高度を上げていく。

<菩提峠の駐車場から二ノ塔への登山口は結構、分かりにくい>

<登山道からは秦野市街地と相模湾を展望することができる>

<菩提峠から二ノ塔までは結構の急坂である。ロープもあったりする>

<曙で東雲がやわらかく輝きはじめていく>

<太陽が昇ってくると、小田原市街地の方が朝日で美しく照り出される>
二ノ塔に着いて、ちょっと歩くと三ノ塔。三ノ塔からは、はるか下の方に鳥尾山荘が見える。三ノ塔から鳥尾山荘までは鎖場のある急な坂を下りる。なんで登っているのに下るのか。その理不尽さに納得できないものを感じつつも、他にルートもないので涙ながらに降りていく。しかも鎖場のあるところは崖である。崖を降りるのだ。鳥尾山荘に着いたのは既に8時。4時に下山することを考えると、9時30分までに塔ノ岳に着ければ丹沢山にチャレンジできるし、そうでなければ戻ろうと考えている。そして、11時までに塔ノ岳に到着できなければ、そのまま帰路につこうとも考えていたので、この鳥尾山荘までに2時間かかったのは結構、微妙な感じである。

<木道がしっかりと整備されており、そういう点からは歩きやすい>
登山道自体は、随分と細い尾根を歩くところもあるが、木道も設置されていたりして全般的には歩きやすい。全般的に乾いており、泥のぬかるみ道を歩かない登山はちょっと嬉しい。また、尾根道であるので左手には小田原や秦野の市街地、そしてその先の相模湾、大島などが展望でき、右手には丹沢の山塊、来た道を振り返れば相模原市や町田市の市街地が展望でき、景観的には素晴らしい。流石、尾根道であると感心する。ただ、紅葉には間に合わず、ほとんど枯木の中を歩いて行く。

<富士山は表尾根の途中まではその勇姿を現していたが、塔ノ岳からは見ることはできなかった>

<けっこう厳しい鎖場もある>
そして、新大日を経て木の又小屋に着いたのが9時30分。丹沢山にチャレンジするためには、塔ノ岳に9時30分には到着しなくてはいけなかったことを考えると、ここで丹沢行は断念。と同時に、太股がピキピキ痙攣し始める。これは、太股が攣る前兆である。ということで、ここで休む。ちょっと休んだぐらいでは、復活しないので、ゆっくりだましだまし塔ノ岳に向かっていく。塔ノ岳の山頂に登頂したのは10時ちょっと過ぎ。4時間というのは、ほぼコースタイム通り。ただ、コースタイム通りのペースで歩いたこと、特に序盤でハイペースになったことが後半のバテに繋がってしまったと思われる。

<塔ノ岳の山頂は広く、ちょっとした広場的な空間となっている>
さて、期待した塔ノ岳からの富士山であったが、雲が出てきて見えずじまい。そのうち晴れるかなと昼ご飯を用意し始めたら、どんどん天気は悪化する一方だ。というか、塔ノ岳周辺も相模湾からの黒い雲に覆われ始めた。駐車場を出発した時は、流石に雨は降らないだろうと思っていたのだが、本当、山はなめられない。

<10時の塔ノ岳の光景。東を展望>

<11時ちょっと前にほぼ同じ光景を撮影。1時間でこれだけ天気が悪化した>
天気も崩れそうになったので、もういそいそと下山することにした。出発したのは11時。一時間の間でまさに天国から地獄のような天気の変化である。丹沢のような標高が低く、市街地のすぐそばにある山でもこんなに天候の変化が激しいとは驚きだ。雲は山のちょっと上をすごいスピードで南から北へと移動している。これは、雨も降るかなと思ったが、幸い、雨になることはなかった。行きは雄大な展望が開けていたのに、帰りは雲の切れ目から市街地が展望できるような状況である。この表尾根の辛いのは下山時も登りがあることだ。特に、鳥尾山荘から三ノ塔は壁のような急坂を登らせられる。鎖場もあるし。
三ノ塔に到着したのは13時20分。二ノ塔を過ぎたあたりから膝にもきはじめる。なかなかの厳しさだ。ゆっくりとジグザグに降りていくが、途中、あまりの急坂でジグザグに歩くこともできないような状態になる。丹沢山に登れなかったにもかかわらず、這々の体で菩提峠の駐車場に戻ってくる。14時30分ちょっと前。1時間の休憩時間を入れて、8時間30分の登山であった。走行距離も12キロぐらいなので、ちょっとした百名山なみのハードな登山であった。

<行きとはまったく違って暗雲が空を覆っている>

<たまに雲の切れ目から展望できる市街地が美しい>

<11月下旬であったが駐車場そばでリンドウが咲いていた>
次回は、表尾根を歩いていた時にみつけた戸沢山荘に駐車をして、できればみやま山荘に一泊するようなルートで丹沢山にチャレンジしたいと思う。これまでまったく縁がないに等しかった丹沢であるが、次回訪れるのは、結構、すぐ先であるような気がする。
当日、起きたのは4時。ちょっと遅い。急いで支度をし、珈琲をつくり、おにぎりをつくって家を出る。家を出たのは5時過ぎ。これは、7時発かなと半ば諦めていたのだが、なんと菩提峠の駐車場には6時についた。そして念のためのヒル対策をして、登山を開始したのが6時15分。家を出たのが遅い割には、思ったより随分と早く出発できた。というか、丹沢、近すぎないか。こんなに近いのか、丹沢。
ちなみに丹沢に来るのは人生2度目。一度目は大学時代に彼女とドライブで縦断しただけだ。それ以来というか、歩きでは人生初めてである。丹沢にこんな近くに住んでいたのに。

<菩提峠の駐車場>
菩提峠からの登山口はよく分からず、違うところに行こうとしたのだが、他の登山者が違うルートをとっていたので間違いに気づいた。本当、登山は出だしが肝心だ。さて、菩提峠から二ノ塔までは、スギ林の急坂を歩いて行く。メインルートではないので、結構、道が分かりにくい。小一時間ぐらい歩くと、ようやく二ノ塔尾根のルートとぶつかる。ここからは尾根道で展望が広がって気持ちがよい。というか、結果的に富士山をしっかりと見られたのはこの尾根道からであった。とは、ここを歩いている時には夢にも思わなかった。これは、塔ノ岳からの富士山の展望は素晴らしいものがあると期待に胸を膨らませて高度を上げていく。

<菩提峠の駐車場から二ノ塔への登山口は結構、分かりにくい>

<登山道からは秦野市街地と相模湾を展望することができる>

<菩提峠から二ノ塔までは結構の急坂である。ロープもあったりする>

<曙で東雲がやわらかく輝きはじめていく>

<太陽が昇ってくると、小田原市街地の方が朝日で美しく照り出される>
二ノ塔に着いて、ちょっと歩くと三ノ塔。三ノ塔からは、はるか下の方に鳥尾山荘が見える。三ノ塔から鳥尾山荘までは鎖場のある急な坂を下りる。なんで登っているのに下るのか。その理不尽さに納得できないものを感じつつも、他にルートもないので涙ながらに降りていく。しかも鎖場のあるところは崖である。崖を降りるのだ。鳥尾山荘に着いたのは既に8時。4時に下山することを考えると、9時30分までに塔ノ岳に着ければ丹沢山にチャレンジできるし、そうでなければ戻ろうと考えている。そして、11時までに塔ノ岳に到着できなければ、そのまま帰路につこうとも考えていたので、この鳥尾山荘までに2時間かかったのは結構、微妙な感じである。

<木道がしっかりと整備されており、そういう点からは歩きやすい>
登山道自体は、随分と細い尾根を歩くところもあるが、木道も設置されていたりして全般的には歩きやすい。全般的に乾いており、泥のぬかるみ道を歩かない登山はちょっと嬉しい。また、尾根道であるので左手には小田原や秦野の市街地、そしてその先の相模湾、大島などが展望でき、右手には丹沢の山塊、来た道を振り返れば相模原市や町田市の市街地が展望でき、景観的には素晴らしい。流石、尾根道であると感心する。ただ、紅葉には間に合わず、ほとんど枯木の中を歩いて行く。

<富士山は表尾根の途中まではその勇姿を現していたが、塔ノ岳からは見ることはできなかった>

<けっこう厳しい鎖場もある>
そして、新大日を経て木の又小屋に着いたのが9時30分。丹沢山にチャレンジするためには、塔ノ岳に9時30分には到着しなくてはいけなかったことを考えると、ここで丹沢行は断念。と同時に、太股がピキピキ痙攣し始める。これは、太股が攣る前兆である。ということで、ここで休む。ちょっと休んだぐらいでは、復活しないので、ゆっくりだましだまし塔ノ岳に向かっていく。塔ノ岳の山頂に登頂したのは10時ちょっと過ぎ。4時間というのは、ほぼコースタイム通り。ただ、コースタイム通りのペースで歩いたこと、特に序盤でハイペースになったことが後半のバテに繋がってしまったと思われる。

<塔ノ岳の山頂は広く、ちょっとした広場的な空間となっている>
さて、期待した塔ノ岳からの富士山であったが、雲が出てきて見えずじまい。そのうち晴れるかなと昼ご飯を用意し始めたら、どんどん天気は悪化する一方だ。というか、塔ノ岳周辺も相模湾からの黒い雲に覆われ始めた。駐車場を出発した時は、流石に雨は降らないだろうと思っていたのだが、本当、山はなめられない。

<10時の塔ノ岳の光景。東を展望>

<11時ちょっと前にほぼ同じ光景を撮影。1時間でこれだけ天気が悪化した>
天気も崩れそうになったので、もういそいそと下山することにした。出発したのは11時。一時間の間でまさに天国から地獄のような天気の変化である。丹沢のような標高が低く、市街地のすぐそばにある山でもこんなに天候の変化が激しいとは驚きだ。雲は山のちょっと上をすごいスピードで南から北へと移動している。これは、雨も降るかなと思ったが、幸い、雨になることはなかった。行きは雄大な展望が開けていたのに、帰りは雲の切れ目から市街地が展望できるような状況である。この表尾根の辛いのは下山時も登りがあることだ。特に、鳥尾山荘から三ノ塔は壁のような急坂を登らせられる。鎖場もあるし。
三ノ塔に到着したのは13時20分。二ノ塔を過ぎたあたりから膝にもきはじめる。なかなかの厳しさだ。ゆっくりとジグザグに降りていくが、途中、あまりの急坂でジグザグに歩くこともできないような状態になる。丹沢山に登れなかったにもかかわらず、這々の体で菩提峠の駐車場に戻ってくる。14時30分ちょっと前。1時間の休憩時間を入れて、8時間30分の登山であった。走行距離も12キロぐらいなので、ちょっとした百名山なみのハードな登山であった。

<行きとはまったく違って暗雲が空を覆っている>

<たまに雲の切れ目から展望できる市街地が美しい>

<11月下旬であったが駐車場そばでリンドウが咲いていた>
次回は、表尾根を歩いていた時にみつけた戸沢山荘に駐車をして、できればみやま山荘に一泊するようなルートで丹沢山にチャレンジしたいと思う。これまでまったく縁がないに等しかった丹沢であるが、次回訪れるのは、結構、すぐ先であるような気がする。
巻機山(日本百名山46座登頂) [日本百名山]
大学の講義が始まると講義や校務に追われて忙しい。結果、秋に百名山にチャレンジすることがなかなか適わなくなる。そんなことでは不味いと思い、尾瀬の燧ヶ岳にチャレンジしようとしたのだが、ゴートゥーで前泊するような宿がまったくない。それでは谷川岳にしようと水上にある安宿を予約した。予約した後、しかし、ロープウェイの始発は何時かな、とネットで調べたら、なんとロープウェイは運行中止になっていた。何それ!と思ったが、当日予約なのでキャンセルしても全額払わなくてはならない。それなら近場の苗場山に行くかと思ったが、天気予報では苗場山は雪。ということで、それではと巻機山にチャレンジすることにした。
宿を4時前に出て、途中、コンビニエンス・ストアに寄って巻機山の登山口の駐車場に着いたのが5時15分ぐらい。まだ空は暗いが、既に駐車場は結構、混んでいる。いろいろと身支度を調え、出発したのは5時50分。駐車場が多く、登山口を探すのにちょっと迷った。第四駐車場のところに登山口はあった。
既に空は明るくなりつつあり、山はまさに燃えるような色をしている。素晴らしい紅葉だ。
登山口を進むとすぐに沢コースと尾根コースの分岐点になる。沢コースは最近の大雨で崩落が激しく、登りはともかく下りは禁じられている。当然、尾根コースをとる。しばらくは緩やかな登りであるが、泥のぬかるみ道なので滑りやすい。なんか、日本の登山は泥道か礫を歩かされるかのどっちかだな。どちらにしろ、あまり快適ではない。ただ、巻機山の麓に広がるブナ林は素晴らしい。幹が太くなく、スマートなプロポーションをしているブナの木だ。
私の登山の弱点は下りに弱いということである。この下りに弱いというのは、元気な登り時に膝を痛めてしまうからなので、今回はゆっくりとマイペースで登っていくこととした。マラソンで最初に飛ばして後半、ガクッとくるような登り方をするのが問題であるのだ。ということで、抜かれてもじっと我慢をして一歩一歩、噛みしめるように登っていく。結果、この日は下りも膝にこないで下山をすることができたので、これからもこの登り方を守っていきたいと思う。
さて、歩いて二時間ぐらい経つと徐々に展望が開け、驚くような美しい紅葉に彩られた山が登山口の両側に展開する。そして、ほぼ2時間15分後(8時05分)に6合目に到着する。ほぼコースタイム通りである(『日本百名山-山あるきガイド』(JTBパブリッシング))。6合目は展望台になっており、見事な紅葉と六日町、さらには遠く日本海までも望むことができる。ここで軽くおにぎりを食べて休憩。
そこからはクマザサに覆われた中、泥の急斜面が続く。泥がまるでダーク・チョコレートのようだ。登山靴は泥だらけである。ここを我慢して歩いて行くと、八合目に出る。八合目からはしっかりと木で階段がつくられており、非常に歩きやすい。天気は快晴で、素晴らしい紅く燃えるような紅葉の山々を見ながら歩いて行く登山は、気持ちも晴れる。忙しい中、無理して時間をつくって登山に来てよかったとつくづく思う。
階段を登り切って左に歩いて行くとニセ巻機山に到着する。向かいには巻機山本峰と、その左に堂々とした山容の割引岳を見ることができる。時間は9時10分。この行程でもコースタイムより早い。多くの登山客に抜かれて歩いていた割には、ペースは決して悪くない。そこから5分ほど下ると巻機山避難小屋に着く。ここではトイレがあり、私も用を足す。そこからはまた登りになる。織姫の池と呼ばれる池塘に映える空と山を見ながら、稜線へと足を運ぶ。ここは御機屋といわれて、ちょっと平らになっている。ここは巻機山山頂の看板が立っている。実際の山頂は、もっと右にあるのだが、植生保全のために立ち入りができない。そのための措置である。とりあえず、ここで記念撮影をする。
当初は、ここで食事でもして引き返すことも考えたのだが、既に多くの登山客がここで食事を取っていた。時間は10時ちょっと前。下山はコースタイムより、遙かに時間がかかる傾向にある私だが、流石に登りの4時間よりかかることはないだろうと思い切って三角点があり展望のよい牛ヶ岳まで足を延ばし、そこで昼ご飯を食べることにした。牛カ岳に行く途中には本峰もある。本峰は平らで、あまり感動を覚えない。それより、この牛カ岳への尾根道は左に日本海の素晴らしい展望、目の前に越後三山、さらには右には平ヶ岳、燧ヶ岳、日光白根山、さらに後ろには谷川連峰、苗場山などを見ることができ、歩いていて本当に気持ちがよい。牛カ岳の近くにいくと奥只見湖も見える。
牛カ岳は尾根の先端という感じの場所で、そこから先は急坂となっている。何人かの人がいたが、空きスペースを探してお湯を沸かそうと思ったらなんと鍋を忘れた。本当、先日、買ったばかりなのに情けない。カップヌードルのビッグサイズをそのまま持ち帰る羽目になった。
牛カ岳は11時頃に発つ。下山の目標時間は4時間30分である。下りが何より弱点の私は、登りと同じように休みつつ、降りていくことを今日は自らに課すこととした。11時30分頃に御機屋を通過し、12時頃にはニセ巻機山を通過。8合目から6合目にかけては、途中、凄まじい泥濘の急坂を注意して下りていき、6合目には13時頃に到着。ニセ巻機山から6合目の下山はコースタイムの45分よりもかかっている。しかし、焦りは禁物だ。焦ると膝に来て、結果、余計時間がかかることになるからだ。先月の雨飾山では、まさに下山でコースタイムの1.5倍もかかることになってしまったが、これは膝が痛くなったからだ。
6合目を過ぎたあたりから、あれだけ晴天だったのに雲が出てきた。本当、山の天気はよく分からない。人にどんどん追い越されるが、何しろ泥に足を取られて滑らないことを念頭に下山する。とはいえ、一度は滑って尻餅をついてしまった。この滑るのは足の筋肉が持ちこたえることが出来なくなっているからだ。しかし、雨飾山よりはずっと足のコンディションはよい。三合目を越えると平らになったので、ちょっとペースを速めた。登山口に到着したのは14時40分。これもコースタイムの90分よりは時間がかかったが、10分程度であり、これは私的には相当の頑張りで、自分でもちょっと驚いた。やればできるじゃないか、という感じである。合計8時間50分の登山となり、いつもは体力を100%以上、使い切っている場合が多く、もう這々の体となっているのだが、今回は多少、余裕がある。将来に繋がる登山であったかなと思う。
私は、百名山にチャレンジはしているが、ほとんど苦行なので滅多に同じ山にもう一度登りたいとは思わない。苦行じゃなくて簡単な山はそれほど魅力がないので、やはりもう一度チャレンジしたいとは思わない。しかし、この巻機山は違った。もう一度、機会があれば登りたいと思わせた。こんなに気分よく、さらに達成感をも兼ねて登山をできたのは初めてかもしれない。

(5時前であるが駐車場には多くの車が既に駐車していた)

(登山口からすぐに分岐点がある)

(泥のぬかるみ道の急坂が続く)

(6合目の展望台)

(6合目から8合目までの泥濘んだ急坂)

(8合目からは階段が続いて歩きやすい)

(ニセ巻機山)

(ニセ巻機山から割引岳を望む)

(避難小屋)

(織姫の池)

(御機屋と呼ばれる稜線に開けた場所。巻機山山頂の看板が立っている)

(御機屋から牛カ岳へと向かう)

(牛カ岳)

(牛カ岳周辺の山々は真っ赤に燃えていた)

(まるで空中散歩をしているかのような尾根道)

(笹の緑と紅葉の赤とのコントラストが美しい)

(御機屋からニセ巻機山を望む)

(ニセ巻機山から八合目へと下りていく)

(ちょうど7合目周辺からの紅葉は見事であった)
宿を4時前に出て、途中、コンビニエンス・ストアに寄って巻機山の登山口の駐車場に着いたのが5時15分ぐらい。まだ空は暗いが、既に駐車場は結構、混んでいる。いろいろと身支度を調え、出発したのは5時50分。駐車場が多く、登山口を探すのにちょっと迷った。第四駐車場のところに登山口はあった。
既に空は明るくなりつつあり、山はまさに燃えるような色をしている。素晴らしい紅葉だ。
登山口を進むとすぐに沢コースと尾根コースの分岐点になる。沢コースは最近の大雨で崩落が激しく、登りはともかく下りは禁じられている。当然、尾根コースをとる。しばらくは緩やかな登りであるが、泥のぬかるみ道なので滑りやすい。なんか、日本の登山は泥道か礫を歩かされるかのどっちかだな。どちらにしろ、あまり快適ではない。ただ、巻機山の麓に広がるブナ林は素晴らしい。幹が太くなく、スマートなプロポーションをしているブナの木だ。
私の登山の弱点は下りに弱いということである。この下りに弱いというのは、元気な登り時に膝を痛めてしまうからなので、今回はゆっくりとマイペースで登っていくこととした。マラソンで最初に飛ばして後半、ガクッとくるような登り方をするのが問題であるのだ。ということで、抜かれてもじっと我慢をして一歩一歩、噛みしめるように登っていく。結果、この日は下りも膝にこないで下山をすることができたので、これからもこの登り方を守っていきたいと思う。
さて、歩いて二時間ぐらい経つと徐々に展望が開け、驚くような美しい紅葉に彩られた山が登山口の両側に展開する。そして、ほぼ2時間15分後(8時05分)に6合目に到着する。ほぼコースタイム通りである(『日本百名山-山あるきガイド』(JTBパブリッシング))。6合目は展望台になっており、見事な紅葉と六日町、さらには遠く日本海までも望むことができる。ここで軽くおにぎりを食べて休憩。
そこからはクマザサに覆われた中、泥の急斜面が続く。泥がまるでダーク・チョコレートのようだ。登山靴は泥だらけである。ここを我慢して歩いて行くと、八合目に出る。八合目からはしっかりと木で階段がつくられており、非常に歩きやすい。天気は快晴で、素晴らしい紅く燃えるような紅葉の山々を見ながら歩いて行く登山は、気持ちも晴れる。忙しい中、無理して時間をつくって登山に来てよかったとつくづく思う。
階段を登り切って左に歩いて行くとニセ巻機山に到着する。向かいには巻機山本峰と、その左に堂々とした山容の割引岳を見ることができる。時間は9時10分。この行程でもコースタイムより早い。多くの登山客に抜かれて歩いていた割には、ペースは決して悪くない。そこから5分ほど下ると巻機山避難小屋に着く。ここではトイレがあり、私も用を足す。そこからはまた登りになる。織姫の池と呼ばれる池塘に映える空と山を見ながら、稜線へと足を運ぶ。ここは御機屋といわれて、ちょっと平らになっている。ここは巻機山山頂の看板が立っている。実際の山頂は、もっと右にあるのだが、植生保全のために立ち入りができない。そのための措置である。とりあえず、ここで記念撮影をする。
当初は、ここで食事でもして引き返すことも考えたのだが、既に多くの登山客がここで食事を取っていた。時間は10時ちょっと前。下山はコースタイムより、遙かに時間がかかる傾向にある私だが、流石に登りの4時間よりかかることはないだろうと思い切って三角点があり展望のよい牛ヶ岳まで足を延ばし、そこで昼ご飯を食べることにした。牛カ岳に行く途中には本峰もある。本峰は平らで、あまり感動を覚えない。それより、この牛カ岳への尾根道は左に日本海の素晴らしい展望、目の前に越後三山、さらには右には平ヶ岳、燧ヶ岳、日光白根山、さらに後ろには谷川連峰、苗場山などを見ることができ、歩いていて本当に気持ちがよい。牛カ岳の近くにいくと奥只見湖も見える。
牛カ岳は尾根の先端という感じの場所で、そこから先は急坂となっている。何人かの人がいたが、空きスペースを探してお湯を沸かそうと思ったらなんと鍋を忘れた。本当、先日、買ったばかりなのに情けない。カップヌードルのビッグサイズをそのまま持ち帰る羽目になった。
牛カ岳は11時頃に発つ。下山の目標時間は4時間30分である。下りが何より弱点の私は、登りと同じように休みつつ、降りていくことを今日は自らに課すこととした。11時30分頃に御機屋を通過し、12時頃にはニセ巻機山を通過。8合目から6合目にかけては、途中、凄まじい泥濘の急坂を注意して下りていき、6合目には13時頃に到着。ニセ巻機山から6合目の下山はコースタイムの45分よりもかかっている。しかし、焦りは禁物だ。焦ると膝に来て、結果、余計時間がかかることになるからだ。先月の雨飾山では、まさに下山でコースタイムの1.5倍もかかることになってしまったが、これは膝が痛くなったからだ。
6合目を過ぎたあたりから、あれだけ晴天だったのに雲が出てきた。本当、山の天気はよく分からない。人にどんどん追い越されるが、何しろ泥に足を取られて滑らないことを念頭に下山する。とはいえ、一度は滑って尻餅をついてしまった。この滑るのは足の筋肉が持ちこたえることが出来なくなっているからだ。しかし、雨飾山よりはずっと足のコンディションはよい。三合目を越えると平らになったので、ちょっとペースを速めた。登山口に到着したのは14時40分。これもコースタイムの90分よりは時間がかかったが、10分程度であり、これは私的には相当の頑張りで、自分でもちょっと驚いた。やればできるじゃないか、という感じである。合計8時間50分の登山となり、いつもは体力を100%以上、使い切っている場合が多く、もう這々の体となっているのだが、今回は多少、余裕がある。将来に繋がる登山であったかなと思う。
私は、百名山にチャレンジはしているが、ほとんど苦行なので滅多に同じ山にもう一度登りたいとは思わない。苦行じゃなくて簡単な山はそれほど魅力がないので、やはりもう一度チャレンジしたいとは思わない。しかし、この巻機山は違った。もう一度、機会があれば登りたいと思わせた。こんなに気分よく、さらに達成感をも兼ねて登山をできたのは初めてかもしれない。

(5時前であるが駐車場には多くの車が既に駐車していた)

(登山口からすぐに分岐点がある)

(泥のぬかるみ道の急坂が続く)

(6合目の展望台)

(6合目から8合目までの泥濘んだ急坂)

(8合目からは階段が続いて歩きやすい)

(ニセ巻機山)

(ニセ巻機山から割引岳を望む)

(避難小屋)

(織姫の池)

(御機屋と呼ばれる稜線に開けた場所。巻機山山頂の看板が立っている)

(御機屋から牛カ岳へと向かう)

(牛カ岳)

(牛カ岳周辺の山々は真っ赤に燃えていた)

(まるで空中散歩をしているかのような尾根道)

(笹の緑と紅葉の赤とのコントラストが美しい)

(御機屋からニセ巻機山を望む)

(ニセ巻機山から八合目へと下りていく)

(ちょうど7合目周辺からの紅葉は見事であった)
焼岳(日本百名山44座登頂) [日本百名山]
焼岳に挑戦する。前日の夜11時頃に塩尻市内のビジネスホテルに到着する。天気予報では松本市内の降水確率は40%ぐらいだったので、これは無理だろうと半ば諦めていたのだが、登山天気アプリをみると、上高地の降水確率は6時から12時までゼロ、12時から18時までの間では降水量1mmの雨が降るという予想であった。これは5時の始発の沢渡から上高地に行くバスに乗れれば、雨が降り始めた時にはあわよくば登山口に戻れるかもしれないし、そうでなくても登山口そばには戻っているだろうと考え、朝3時40分にアラームをセットして眠る。
はずだったのだが、車を運転している時に珈琲を飲み過ぎたのか、目が覚めて一睡もしないで3時30分になってしまった。どうするか、と行くことを躊躇したが、こういう時に諦めたら100名山登頂は絶対無理だと思い、ホテルを発つ。沢渡に着く前にセブンイレブンで朝食のサンドイッチとお握りを購入する。最近のワンパターンである。
沢渡への道は意外と遠く、4時50分頃に到着する。まだ周囲は暗い。急いで準備をする訳にもいかず、靴を履いたり、タイツを履いたりしていたら始発のバスは出発してしまった。その次は6時であった。土曜日であったので、結構、多くの客がいるのかと思ったが空いていた。帝国ホテル前にて降りる。6時30分ぐらいである。朝焼けに映える上高地を囲む山々のシルエットが息を呑むほど美しい。これは日本のヨセミテだ。
さて、そこから田代橋の方に行くと、穂高登山口に出る。穂高はまだまだハードルが高いので、ここは左に曲がって焼岳へ。ちなみに、焼岳を私はずっと「やきだけ」と読んでいたのだが「やけだけ」なのですね。
砂利道をしばらく歩き。左側に大正池の地獄的な景観が広がる。なかなか、迫力がある。15分ぐらい歩くと焼岳の登山口に出る。ここからは砂利道を外れ、本格的な登山道となる。最初の30分ぐらいは樺の美しい森の中を快適に歩いて行く。しかし、だんだんと傾斜がきつくなり、7時30分ぐらいには森に入って初めて焼岳がその姿を森の木々の中から現す。なんか神々しいのと、同時に、あんな高いところまで登れるのだろうかと不安になる。なんせ、睡眠不足なので体力の消耗が気になるのだ。
また、周りにまったく人気がない。というか、百名山の単独行でこんなに一人になったことは初めてである。そしたら、妙に尿の臭いが強い箇所を通り過ぎた。人間にしてはちょっと臭いが濃すぎる。一昨日にも熊が出没したというニュースがあったので、流石に不安になって、iPhoneで音楽を流しながら歩いて行くこととした。さらに30分ぐらい歩いて行くと、森から抜け、谷が展望できるところに出る。ここらへんからは梯子も出始め、なかなか技術と度胸が必要となってくる。8時45分には、登山コース最後の梯子に到着するが、ここは二つの梯子が括り合わされて長い一つの梯子になっているのだが、その梯子の繋ぎのところを登っていくのはなかなか緊張する。これは二つの梯子の傾きがズレているからだ。流石にここを通る時は眠気も覚めた。ただ、嬉しいのは梯子を越えると、目に見えて高度を得たことが分かることだ。また、この梯子を越えると、谷向こうに焼岳の北岳の素晴らしい展望が得られる。天気も最高に近く、午後の降水予報を敢えて無視してきたことは正しい判断であったと確信する。
ただ、ここらへんからか、寝不足もあって高山病のような症状が出始める。これは、通常、これだけ登山で体力を消耗すると空腹を覚えるのだが、その空腹感がまったく出てこないのである。これ以上、高山病を悪化しては不味いと意識し、ゆっくりとゆっくりと登っていくことにする。ここらへんになると、私を追い抜いていく人も出始め、この山に自分一人ではないという、ある意味当たり前のことを実感して少し、安堵を覚える。
焼岳小屋に到着したのは9時15分。コースタイムとほぼ変わらない。途中からゆっくりペースにしたわりには悪くない。ただ、ここでは流石にちょっとでも目を閉じた方がいいと考え、ベンチに座り10分ぐらい仮眠する。
コースタイムをみると焼岳小屋から頂上まで1時間10分であった。まあ、これまでゆっくりペースでもコースタイムだったので、10時30分にはつけるだろうと思ったのだが、これは大間違いであった。焼岳の山頂を目前にしてからが遠い、遠い。ガレ場の急坂で滑りやすいというのもあるが、なかなか高さを稼げない。ところどころから噴煙がまだ出ており、風向きによっては強烈な硫黄臭に襲われる。周囲を見渡せば笠ヶ岳、穂高連山が見えて、本当、素晴らしい景観の中にいて、気は高揚するのだが、山頂は近いようで遠い。結局、山頂に到達したのは11時。コースタイムのよりも1.5倍もかかった。
山頂からは南にある乗鞍岳も展望でき、本当、今日は素晴らしい登山日であったことを実感する。焼岳からはまさに360度の絶景を楽しむことができる。神々が遊ぶ谷、というヨセミテのキャッチフレーズを思い出す。槍ヶ岳も見ることができる。いつか、これらの山に登頂しなくては、とちょっと気持ちも高揚する。
山頂は飽きないが、午後の雨が来る前に急いで下山しないと、と考え11時20分には出発する。下りは結構、ペースをあげたのだが、焼岳小屋に着いたのは、やはりコースタイムより1.5以上倍かかった13時到着であった。ちょっとだけここでも目をつぶり、下山を開始する。これまで晴天の中にいた焼岳に雲がかかっている。ちょっと不吉な前兆だなと思ったのだが、最初の梯子を下りた時ぐらいから雨が降り始め、3つ目ぐらいの梯子を下りた時には土砂降りになった。これはもうしょうがないとカメラをリュックに入れて、雨仕様に着替え、下山を続ける。このとき、山を登っているグループと出会ったのだが、彼らは焼岳小屋に宿泊する予定なのだろうか。あの梯子を濡れた中、のぼるのは嫌だろうなと同情する。
それからは雨の中、ゆっくりと歩く。途中、猿の大群と出会い、相当緊張したが、無事に通り過ぎることができた。ただ、猿の群れと歩いている時はペースが相当、落ちてしまった。
雨の中、歩いていたこともあり、随分と体温も上がり、膝も痛くなったりして、さらには寝不足であったこともあり、なかなかしんどい下山となった。最初は15時台のバスに乗れるのではないかと思ったのだが、思ったよりずっと時間がかかり、結局、這々の体で登山口に戻ってきたのが15時10分。
最終バスの16時には余裕の15時40分にはバスターミナルには着いたのだが、それでも下山に4時間20分もかかってしまった。登りに4時間30分かかったことを考えると、下山は相当、ペースが落ちてしまったのかもしれない。休憩を入れたら9時間以上の登山になってしまい、もう相当、疲労困憊の登山にはなってしまったが、山頂までは本当に素晴らしい天気に恵まれ、そういう意味では充実した登山ではあった。

<西穂高登山口。私は左の焼岳登山口へ>

<幻想的な朝靄の樺の森の中を歩いて行く>

<森の中から焼岳がその姿を現す。挑発されているような気分>

<谷の向こう側の焼岳の勇姿。天気がよく見事な山容に感動する>

<梯子は結構、厳しい。緊張して登っていく>
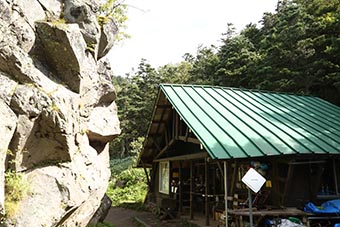
<焼岳小屋にはトイレや飲み物等を販売するキオスクがある>

<焼岳の山頂はすぐ登れそうで結構、遠い>

<ところどころに出ている噴煙から、ここがまだ活火山であることに気づかされる>

<あと少し、あと少しと思っても山頂にはなかなかたどり着けない。コースタイムは短すぎると思う>

<山頂直前にも二つの噴火口があり、風向きによっては相当、硫黄臭がきつい>

<山頂にようやく到着。コースタイムを大幅にオーバー>

<お釜はなかなか神秘的>

<笠ヶ岳のまるで壁のような山容>

<上高地が箱庭のように見える>

<乗鞍岳も展望することができた>

<1時過ぎには急に雲行きが怪しくなり、1時30分から雨が降り始める>
はずだったのだが、車を運転している時に珈琲を飲み過ぎたのか、目が覚めて一睡もしないで3時30分になってしまった。どうするか、と行くことを躊躇したが、こういう時に諦めたら100名山登頂は絶対無理だと思い、ホテルを発つ。沢渡に着く前にセブンイレブンで朝食のサンドイッチとお握りを購入する。最近のワンパターンである。
沢渡への道は意外と遠く、4時50分頃に到着する。まだ周囲は暗い。急いで準備をする訳にもいかず、靴を履いたり、タイツを履いたりしていたら始発のバスは出発してしまった。その次は6時であった。土曜日であったので、結構、多くの客がいるのかと思ったが空いていた。帝国ホテル前にて降りる。6時30分ぐらいである。朝焼けに映える上高地を囲む山々のシルエットが息を呑むほど美しい。これは日本のヨセミテだ。
さて、そこから田代橋の方に行くと、穂高登山口に出る。穂高はまだまだハードルが高いので、ここは左に曲がって焼岳へ。ちなみに、焼岳を私はずっと「やきだけ」と読んでいたのだが「やけだけ」なのですね。
砂利道をしばらく歩き。左側に大正池の地獄的な景観が広がる。なかなか、迫力がある。15分ぐらい歩くと焼岳の登山口に出る。ここからは砂利道を外れ、本格的な登山道となる。最初の30分ぐらいは樺の美しい森の中を快適に歩いて行く。しかし、だんだんと傾斜がきつくなり、7時30分ぐらいには森に入って初めて焼岳がその姿を森の木々の中から現す。なんか神々しいのと、同時に、あんな高いところまで登れるのだろうかと不安になる。なんせ、睡眠不足なので体力の消耗が気になるのだ。
また、周りにまったく人気がない。というか、百名山の単独行でこんなに一人になったことは初めてである。そしたら、妙に尿の臭いが強い箇所を通り過ぎた。人間にしてはちょっと臭いが濃すぎる。一昨日にも熊が出没したというニュースがあったので、流石に不安になって、iPhoneで音楽を流しながら歩いて行くこととした。さらに30分ぐらい歩いて行くと、森から抜け、谷が展望できるところに出る。ここらへんからは梯子も出始め、なかなか技術と度胸が必要となってくる。8時45分には、登山コース最後の梯子に到着するが、ここは二つの梯子が括り合わされて長い一つの梯子になっているのだが、その梯子の繋ぎのところを登っていくのはなかなか緊張する。これは二つの梯子の傾きがズレているからだ。流石にここを通る時は眠気も覚めた。ただ、嬉しいのは梯子を越えると、目に見えて高度を得たことが分かることだ。また、この梯子を越えると、谷向こうに焼岳の北岳の素晴らしい展望が得られる。天気も最高に近く、午後の降水予報を敢えて無視してきたことは正しい判断であったと確信する。
ただ、ここらへんからか、寝不足もあって高山病のような症状が出始める。これは、通常、これだけ登山で体力を消耗すると空腹を覚えるのだが、その空腹感がまったく出てこないのである。これ以上、高山病を悪化しては不味いと意識し、ゆっくりとゆっくりと登っていくことにする。ここらへんになると、私を追い抜いていく人も出始め、この山に自分一人ではないという、ある意味当たり前のことを実感して少し、安堵を覚える。
焼岳小屋に到着したのは9時15分。コースタイムとほぼ変わらない。途中からゆっくりペースにしたわりには悪くない。ただ、ここでは流石にちょっとでも目を閉じた方がいいと考え、ベンチに座り10分ぐらい仮眠する。
コースタイムをみると焼岳小屋から頂上まで1時間10分であった。まあ、これまでゆっくりペースでもコースタイムだったので、10時30分にはつけるだろうと思ったのだが、これは大間違いであった。焼岳の山頂を目前にしてからが遠い、遠い。ガレ場の急坂で滑りやすいというのもあるが、なかなか高さを稼げない。ところどころから噴煙がまだ出ており、風向きによっては強烈な硫黄臭に襲われる。周囲を見渡せば笠ヶ岳、穂高連山が見えて、本当、素晴らしい景観の中にいて、気は高揚するのだが、山頂は近いようで遠い。結局、山頂に到達したのは11時。コースタイムのよりも1.5倍もかかった。
山頂からは南にある乗鞍岳も展望でき、本当、今日は素晴らしい登山日であったことを実感する。焼岳からはまさに360度の絶景を楽しむことができる。神々が遊ぶ谷、というヨセミテのキャッチフレーズを思い出す。槍ヶ岳も見ることができる。いつか、これらの山に登頂しなくては、とちょっと気持ちも高揚する。
山頂は飽きないが、午後の雨が来る前に急いで下山しないと、と考え11時20分には出発する。下りは結構、ペースをあげたのだが、焼岳小屋に着いたのは、やはりコースタイムより1.5以上倍かかった13時到着であった。ちょっとだけここでも目をつぶり、下山を開始する。これまで晴天の中にいた焼岳に雲がかかっている。ちょっと不吉な前兆だなと思ったのだが、最初の梯子を下りた時ぐらいから雨が降り始め、3つ目ぐらいの梯子を下りた時には土砂降りになった。これはもうしょうがないとカメラをリュックに入れて、雨仕様に着替え、下山を続ける。このとき、山を登っているグループと出会ったのだが、彼らは焼岳小屋に宿泊する予定なのだろうか。あの梯子を濡れた中、のぼるのは嫌だろうなと同情する。
それからは雨の中、ゆっくりと歩く。途中、猿の大群と出会い、相当緊張したが、無事に通り過ぎることができた。ただ、猿の群れと歩いている時はペースが相当、落ちてしまった。
雨の中、歩いていたこともあり、随分と体温も上がり、膝も痛くなったりして、さらには寝不足であったこともあり、なかなかしんどい下山となった。最初は15時台のバスに乗れるのではないかと思ったのだが、思ったよりずっと時間がかかり、結局、這々の体で登山口に戻ってきたのが15時10分。
最終バスの16時には余裕の15時40分にはバスターミナルには着いたのだが、それでも下山に4時間20分もかかってしまった。登りに4時間30分かかったことを考えると、下山は相当、ペースが落ちてしまったのかもしれない。休憩を入れたら9時間以上の登山になってしまい、もう相当、疲労困憊の登山にはなってしまったが、山頂までは本当に素晴らしい天気に恵まれ、そういう意味では充実した登山ではあった。

<西穂高登山口。私は左の焼岳登山口へ>

<幻想的な朝靄の樺の森の中を歩いて行く>

<森の中から焼岳がその姿を現す。挑発されているような気分>

<谷の向こう側の焼岳の勇姿。天気がよく見事な山容に感動する>

<梯子は結構、厳しい。緊張して登っていく>
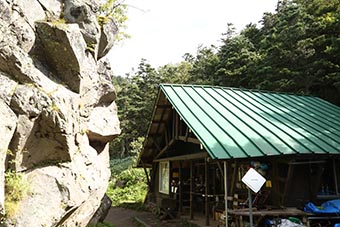
<焼岳小屋にはトイレや飲み物等を販売するキオスクがある>

<焼岳の山頂はすぐ登れそうで結構、遠い>

<ところどころに出ている噴煙から、ここがまだ活火山であることに気づかされる>

<あと少し、あと少しと思っても山頂にはなかなかたどり着けない。コースタイムは短すぎると思う>

<山頂直前にも二つの噴火口があり、風向きによっては相当、硫黄臭がきつい>

<山頂にようやく到着。コースタイムを大幅にオーバー>

<お釜はなかなか神秘的>

<笠ヶ岳のまるで壁のような山容>

<上高地が箱庭のように見える>

<乗鞍岳も展望することができた>

<1時過ぎには急に雲行きが怪しくなり、1時30分から雨が降り始める>
霧ヶ峰(日本百名山43座登頂) [日本百名山]
東京から自動車で京都へ移動する際、諏訪で宿泊した。天気があまり芳しくないということなので、前日は、そのまま車で移動しようと考えていたのだが、朝、起きたら晴天である。これは登山日和、ということで霧ヶ峰、正確には車山登山にチャレンジすることにした。車山肩に駐車をして、車山を目指す。登山道は斜度がそれほどなく、幅も広く歩きやすい。いや、結構、岩があるのだが、利尻岳、後方羊蹄山を歩いた後だと、こんな岩は小石のような気分だ。車山の頂上に着いたのは40分後ぐらいか。ハイキングのような登山であるが、結構、汗をかいている。
車山からの展望はなかなか素晴らしいが、あいにく、蓼科山には雲がかかって全貌をみることはできなかった。さて、そのまま来た道を帰ってもよかったのだが、それも芸がない。そこで、車山乗越を経由して、車山肩に戻る周回ルートを取ることにした。これは、途中まで八島ヶ原湿原に行くルートと同じである。蝶々美山のなだらかな山容を眺めながら、分岐点から車山肩に戻る。野草がいろいろ咲いていて目を楽しませてくれるが、ニッコウキスゲがもう咲いていないのは残念であった。この分岐点からのルートは板敷きの道を歩くので、大変歩きやすい。元に戻ったら11時30分。ということで90分という短い時間の登山であった。
車山は以前、スキーでほぼ頂上までリフトで行ったことがある。夏の今日も平日であるが、リフトは動いていた。このリフトを使えば、おそらく百名山の中でも最も簡単に登頂できるのがこの車山であろう。とはいえ、車山ではなく、霧ヶ峰を百名山として深田久弥が挙げたのは、この車山だけでなく、高原全体を評価してのことだと思われる。しかし、正直、ここより百名山として選考すべきであった山は多くあったのではないかと思う。ニペソツ山とか・・。
私は「簡単な百名山なし」という格言というか戒めのようなものを意識して登山をするようにしている。それは、二週間前に登った磐梯山や、初めて登った瑞牆山とか、いわゆる「初心者向け」と言われる山も、それなりに大変で怪我とか遭難の危険性を伴うからだ。しかし、これまで登った中で、この霧ヶ峰(車山)と八幡平はハイキング気分でスニーカーでも登れる百名山かなとも思ったりもした。

<車山肩の駐車場前から登山道は整備されている>

<霧ヶ峰のたおやかな丘陵>

<40分ぐらいで山頂に着いてしまう>

<山頂から蓼科山を望むも雲で上は見られず>

<山頂付近から白樺湖を望む>

<蝶々美山のなだらかな山容>
車山からの展望はなかなか素晴らしいが、あいにく、蓼科山には雲がかかって全貌をみることはできなかった。さて、そのまま来た道を帰ってもよかったのだが、それも芸がない。そこで、車山乗越を経由して、車山肩に戻る周回ルートを取ることにした。これは、途中まで八島ヶ原湿原に行くルートと同じである。蝶々美山のなだらかな山容を眺めながら、分岐点から車山肩に戻る。野草がいろいろ咲いていて目を楽しませてくれるが、ニッコウキスゲがもう咲いていないのは残念であった。この分岐点からのルートは板敷きの道を歩くので、大変歩きやすい。元に戻ったら11時30分。ということで90分という短い時間の登山であった。
車山は以前、スキーでほぼ頂上までリフトで行ったことがある。夏の今日も平日であるが、リフトは動いていた。このリフトを使えば、おそらく百名山の中でも最も簡単に登頂できるのがこの車山であろう。とはいえ、車山ではなく、霧ヶ峰を百名山として深田久弥が挙げたのは、この車山だけでなく、高原全体を評価してのことだと思われる。しかし、正直、ここより百名山として選考すべきであった山は多くあったのではないかと思う。ニペソツ山とか・・。
私は「簡単な百名山なし」という格言というか戒めのようなものを意識して登山をするようにしている。それは、二週間前に登った磐梯山や、初めて登った瑞牆山とか、いわゆる「初心者向け」と言われる山も、それなりに大変で怪我とか遭難の危険性を伴うからだ。しかし、これまで登った中で、この霧ヶ峰(車山)と八幡平はハイキング気分でスニーカーでも登れる百名山かなとも思ったりもした。

<車山肩の駐車場前から登山道は整備されている>

<霧ヶ峰のたおやかな丘陵>

<40分ぐらいで山頂に着いてしまう>

<山頂から蓼科山を望むも雲で上は見られず>

<山頂付近から白樺湖を望む>

<蝶々美山のなだらかな山容>
羊蹄山(日本百名山42座登頂) [日本百名山]
羊蹄山にチャレンジする。羊蹄山には4つのルートがあるが、そのうちそれほど難しくないのは比羅夫ルートか真狩ルートであるが、我々は比羅夫ルートを選ぶ。宿を4時に出て、途中でセブンイレブンにより、登山口の半月湖野営場の駐車場に車を停める。天気予報が雨ということもあってか、我々以外に登山者はいないようだ。ただ、5時時点では天気は悪くない。羊蹄山の姿も笠雲を被ってはいるがよく見える。その姿はむしろ、我々を挑発するようだ。
5時ちょっと前に登山口を出発する。しばらくはミズナラやシナノキといった広葉樹林の森の中を平坦な道を歩く。たまに倒木が登山道に横たわり行く手を阻むがそれ以外は、軽快に足を進めていける。ただ、一合目(5時30分通過)を過ぎると、すぐ羊蹄山の斜面はきつくなり、そこからはひたすら山頂周りの火口壁までは30度ぐらいの急登が続く。さらに、登り坂になってからすぐに登山道は狭くなり、草が繁茂していることもあり歩きにくい。急坂の泥道であるために、これは雨が降ったら大変なことになるな、という思いは、下りで現実となることを知る。加えて、状況をさらに悪化させるのは虫が多いことだ。これは標高が低いからかもしれないが、蚊の類いや羽虫のようなものがやたら多くて、不快である。ただ、一方で美しい花が多く咲いており(そのせいで虫も多いのかもしれないが)、これが多少はきつい登りを上がっていく中、喜びを与えてくれる。二合目は5時50分、五合目は7時10分。四合目当たりから雨が降り始めたので、五合目ではレインコートを着る。登りがきついので汗が滝のように出るので、レインコートを着るのは躊躇していたが、この雨の強さだと致し方ない。一眼レフのカメラもこの時点でリュックにしまい込む。五合目ぐらいから、さらに斜度がきつくなる。七合目は8時30分。八合目は9時10分。そして九合目に到着したのは9時30分である。本来であれば、ここから広大な展望が得られるのだろうが、まったく雨と霧で視界は得られない。というか、風も強くなってきて寒い。ここで手袋をする。手袋をしないと低体温症になるかというぐらいの風の強さと冷たさである。
九合目に到着したら山頂まではすぐかと思ったら、さにあらず。そこから山頂までも大変な難行であった。どうもここら一帯は「後方羊蹄山の高山植物帯」として天然記念物に指定されているそうだが、その美しさを愛でる余裕はない。急登もそうだが、雨との戦いでそれどころではないからだ。
九合目を40分ほど登ると火口壁に着く(10時10分)。ただ、霧と風でほとんど何も見えない。ただ、瓦礫と岩の荒涼たる場所であることが分かる。どうも、この火口壁からは360度の展望が広がるそうだが、まったく何も見えない。さらに、眼鏡に雨の水滴がこびりついて、目の前もよく見えないような状況だ。羊蹄山の山頂に到達するには岩場を登り上がらないといけない。なかなかハードだ。しかし、それらの苦行を乗り越えて、どうにか山頂に登頂する。11時ちょうどで、登山口から6時間かかったこととなる。ここからの展望は素晴らしいらしいが、何も見えないので、大変残念だが、登頂したという達成感で気持ちは清々しい。
さて昼飯時ではあるのだが、雨ということもあり避難小屋まで移動してそこで食べることにする。帰り道は、来た道を戻るという選択肢もあったが、何も見えないが山頂を廻る形で、真狩ルートの分岐点を経由するコースを取る。ただ、このコース、山頂直下はなかなか凄まじい岩場である。しかも、その岩場が相当、長い間続く。雨でも岩は滑りにくかったが、相当、緊張して通過する。さて、どうにか岩場を通り抜けたのはいいが、その後、安心感からか油断して左の足首を捻ってしまった。これは古傷で、非常に不味いなと思ったのだが、同行者が急いでエアー・サロンパスで救急処置をしてくれたこともあって、どうにか歩くことはできた。ただ、足首は一日経った今、これを書いている現在でもそれほど芳しくはない。左の足首は、もう捻るのは癖になっているのだが、私の登山靴はしっかりと足首をサポートしてくれることもあって、この登山靴を履いて捻ったのは初めてであり、ショックであった。
少し休んだ後、ゆっくりと歩き始め真狩ルートで避難小屋まで向かう。避難小屋への分岐点は真狩ルートの九合目なのだが、そこまで20分はかかった。そして、分岐点からさらに10分はかかる。避難小屋へのアクセスが悪いというのも、羊蹄山のマイナスポイントなのではないかと思う。ただ、この頃から雨が上がり始め、下界が展望できるようになる。山頂の高度からではないが、それなりの雄大なる眺めに心は晴れる。避難小屋に着いたのは13時10分頃。
避難小屋のベンチに座りながら、ゆっくりと食事を取り、捻った足首にサロンパスを貼る。トイレも借りて、避難小屋を発ったのが13時30分。カメラを再び鞄から取り出し、雄大な西北海道の光景を撮影する。日本海が美しい。
さて、再び比羅夫ルートの九合目に着いたのが13時45分。そこからはひたすら急坂を下りていくことになる。捻った直後の足首に、これはなかなか厳しい。とはいえ、登山靴がテーピングをしたかのように足首をしっかりと固定してくれているので、どうにか降りていくことができる。ゴローのしっかりとした登山靴の有り難みが身に染みる。
七合目に到着したのが14時30分。六合目が15時05分。足首を気にしているためかコースタイムより遅い。再び雨が降り始めたので、カメラをまたリュックにしまい、泥道で非常に滑りやすい中、ストックを使いながらどうにか降りていく。ただ、気をつけながらも3回ほど転んでしまった。この比羅夫ルート、決して優れたコースとはいえない。もう少し、整備をしてくれればと強く思う。とはいえ、四つあるコースではこのコースが一番人気らしいので、他のコースはこれより酷いのかと思うと、ちょっと驚きだ。どうにか二合目に着いたのは16時40分。また17時前だが、雨ということもあり、さらには森の中にいるため暗く感じる。日の入りはまだまだということは分かっていても不安になる。
さて、這々の体で登山口に戻ってきたのは17時20分。正味12時間以上の登山であった。披露困憊だ。シャツを4回は着替えるほどの大量の汗を掻き、雨に降られ、泥まみれになり、さらに足首を捻り、しかも登山をしてから初めて脇腹が筋肉痛になるという事態にも陥るなど、どっと疲れるような登山体験であったが、懸念であった「膝痛」もなければ、太股の痙攣もなく、この長丁場をどうにか登り切れたのは自信となった。
羊蹄山に登る前に、ロッグキャビンのような場所に前泊したのだが、そこで隣のキャビンに泊まっていた札幌の人とちょっと話をした。彼は嫌味なく、北海道が本州に比べて、自然がいかに豊かで恵まれているか、という話をした。私はそれを聞いて、そういうものかな、と思っていたが、「自然」をどのように捉えるかは難しいところはあるが、今日の羊蹄山より、先週、登頂した奥白根山の方がはるかに自然のゴージャスさでは勝っているという感想を抱いた。いや、晴れていたら違う感想を抱くと指摘されるかもしれないが、登山口が既に羊蹄山より高い標高2000メートルの奥白根山の高山の魅力、五色沼の美しさは北海道にはなかなかないのではと思ったりもする。いや、まだ幌尻岳とかトムラウシは未踏なので、これはあくまでも現段階での感想ですが。ただ、羊蹄山はその素晴らしく雄大なる姿に比べて、登山体験としては今一つではあることは確かだ。羅臼岳や利尻岳はもちろん、旭岳の方がずっと素晴らしい。

<前泊した宿から展望した羊蹄山。まるで我々を挑発するかのように聳え立っている>

<登山口>

<登山道はまるでジャングルのように木々が生い茂っている>

<イワギキョウ>

<九合目は濃霧の中だ>

<山頂に行くには岩場を登りきらなくてはならない>

<山頂からの展望。濃霧と雨の中、視界は極めて限定されていた>

<火口壁は岩だらけである>


<真狩ルートとの分岐点ぐらいから視界が開け始める>

<避難小屋にアクセスするのは結構、遠回りをしなくてはならない>

<避難小屋周辺から羊蹄山の西側を観る>

<下山時の九合目は、登山時に比べるとずっと視界は開けていた>
5時ちょっと前に登山口を出発する。しばらくはミズナラやシナノキといった広葉樹林の森の中を平坦な道を歩く。たまに倒木が登山道に横たわり行く手を阻むがそれ以外は、軽快に足を進めていける。ただ、一合目(5時30分通過)を過ぎると、すぐ羊蹄山の斜面はきつくなり、そこからはひたすら山頂周りの火口壁までは30度ぐらいの急登が続く。さらに、登り坂になってからすぐに登山道は狭くなり、草が繁茂していることもあり歩きにくい。急坂の泥道であるために、これは雨が降ったら大変なことになるな、という思いは、下りで現実となることを知る。加えて、状況をさらに悪化させるのは虫が多いことだ。これは標高が低いからかもしれないが、蚊の類いや羽虫のようなものがやたら多くて、不快である。ただ、一方で美しい花が多く咲いており(そのせいで虫も多いのかもしれないが)、これが多少はきつい登りを上がっていく中、喜びを与えてくれる。二合目は5時50分、五合目は7時10分。四合目当たりから雨が降り始めたので、五合目ではレインコートを着る。登りがきついので汗が滝のように出るので、レインコートを着るのは躊躇していたが、この雨の強さだと致し方ない。一眼レフのカメラもこの時点でリュックにしまい込む。五合目ぐらいから、さらに斜度がきつくなる。七合目は8時30分。八合目は9時10分。そして九合目に到着したのは9時30分である。本来であれば、ここから広大な展望が得られるのだろうが、まったく雨と霧で視界は得られない。というか、風も強くなってきて寒い。ここで手袋をする。手袋をしないと低体温症になるかというぐらいの風の強さと冷たさである。
九合目に到着したら山頂まではすぐかと思ったら、さにあらず。そこから山頂までも大変な難行であった。どうもここら一帯は「後方羊蹄山の高山植物帯」として天然記念物に指定されているそうだが、その美しさを愛でる余裕はない。急登もそうだが、雨との戦いでそれどころではないからだ。
九合目を40分ほど登ると火口壁に着く(10時10分)。ただ、霧と風でほとんど何も見えない。ただ、瓦礫と岩の荒涼たる場所であることが分かる。どうも、この火口壁からは360度の展望が広がるそうだが、まったく何も見えない。さらに、眼鏡に雨の水滴がこびりついて、目の前もよく見えないような状況だ。羊蹄山の山頂に到達するには岩場を登り上がらないといけない。なかなかハードだ。しかし、それらの苦行を乗り越えて、どうにか山頂に登頂する。11時ちょうどで、登山口から6時間かかったこととなる。ここからの展望は素晴らしいらしいが、何も見えないので、大変残念だが、登頂したという達成感で気持ちは清々しい。
さて昼飯時ではあるのだが、雨ということもあり避難小屋まで移動してそこで食べることにする。帰り道は、来た道を戻るという選択肢もあったが、何も見えないが山頂を廻る形で、真狩ルートの分岐点を経由するコースを取る。ただ、このコース、山頂直下はなかなか凄まじい岩場である。しかも、その岩場が相当、長い間続く。雨でも岩は滑りにくかったが、相当、緊張して通過する。さて、どうにか岩場を通り抜けたのはいいが、その後、安心感からか油断して左の足首を捻ってしまった。これは古傷で、非常に不味いなと思ったのだが、同行者が急いでエアー・サロンパスで救急処置をしてくれたこともあって、どうにか歩くことはできた。ただ、足首は一日経った今、これを書いている現在でもそれほど芳しくはない。左の足首は、もう捻るのは癖になっているのだが、私の登山靴はしっかりと足首をサポートしてくれることもあって、この登山靴を履いて捻ったのは初めてであり、ショックであった。
少し休んだ後、ゆっくりと歩き始め真狩ルートで避難小屋まで向かう。避難小屋への分岐点は真狩ルートの九合目なのだが、そこまで20分はかかった。そして、分岐点からさらに10分はかかる。避難小屋へのアクセスが悪いというのも、羊蹄山のマイナスポイントなのではないかと思う。ただ、この頃から雨が上がり始め、下界が展望できるようになる。山頂の高度からではないが、それなりの雄大なる眺めに心は晴れる。避難小屋に着いたのは13時10分頃。
避難小屋のベンチに座りながら、ゆっくりと食事を取り、捻った足首にサロンパスを貼る。トイレも借りて、避難小屋を発ったのが13時30分。カメラを再び鞄から取り出し、雄大な西北海道の光景を撮影する。日本海が美しい。
さて、再び比羅夫ルートの九合目に着いたのが13時45分。そこからはひたすら急坂を下りていくことになる。捻った直後の足首に、これはなかなか厳しい。とはいえ、登山靴がテーピングをしたかのように足首をしっかりと固定してくれているので、どうにか降りていくことができる。ゴローのしっかりとした登山靴の有り難みが身に染みる。
七合目に到着したのが14時30分。六合目が15時05分。足首を気にしているためかコースタイムより遅い。再び雨が降り始めたので、カメラをまたリュックにしまい、泥道で非常に滑りやすい中、ストックを使いながらどうにか降りていく。ただ、気をつけながらも3回ほど転んでしまった。この比羅夫ルート、決して優れたコースとはいえない。もう少し、整備をしてくれればと強く思う。とはいえ、四つあるコースではこのコースが一番人気らしいので、他のコースはこれより酷いのかと思うと、ちょっと驚きだ。どうにか二合目に着いたのは16時40分。また17時前だが、雨ということもあり、さらには森の中にいるため暗く感じる。日の入りはまだまだということは分かっていても不安になる。
さて、這々の体で登山口に戻ってきたのは17時20分。正味12時間以上の登山であった。披露困憊だ。シャツを4回は着替えるほどの大量の汗を掻き、雨に降られ、泥まみれになり、さらに足首を捻り、しかも登山をしてから初めて脇腹が筋肉痛になるという事態にも陥るなど、どっと疲れるような登山体験であったが、懸念であった「膝痛」もなければ、太股の痙攣もなく、この長丁場をどうにか登り切れたのは自信となった。
羊蹄山に登る前に、ロッグキャビンのような場所に前泊したのだが、そこで隣のキャビンに泊まっていた札幌の人とちょっと話をした。彼は嫌味なく、北海道が本州に比べて、自然がいかに豊かで恵まれているか、という話をした。私はそれを聞いて、そういうものかな、と思っていたが、「自然」をどのように捉えるかは難しいところはあるが、今日の羊蹄山より、先週、登頂した奥白根山の方がはるかに自然のゴージャスさでは勝っているという感想を抱いた。いや、晴れていたら違う感想を抱くと指摘されるかもしれないが、登山口が既に羊蹄山より高い標高2000メートルの奥白根山の高山の魅力、五色沼の美しさは北海道にはなかなかないのではと思ったりもする。いや、まだ幌尻岳とかトムラウシは未踏なので、これはあくまでも現段階での感想ですが。ただ、羊蹄山はその素晴らしく雄大なる姿に比べて、登山体験としては今一つではあることは確かだ。羅臼岳や利尻岳はもちろん、旭岳の方がずっと素晴らしい。

<前泊した宿から展望した羊蹄山。まるで我々を挑発するかのように聳え立っている>

<登山口>

<登山道はまるでジャングルのように木々が生い茂っている>

<イワギキョウ>

<九合目は濃霧の中だ>

<山頂に行くには岩場を登りきらなくてはならない>

<山頂からの展望。濃霧と雨の中、視界は極めて限定されていた>

<火口壁は岩だらけである>


<真狩ルートとの分岐点ぐらいから視界が開け始める>

<避難小屋にアクセスするのは結構、遠回りをしなくてはならない>

<避難小屋周辺から羊蹄山の西側を観る>

<下山時の九合目は、登山時に比べるとずっと視界は開けていた>
タグ:羊蹄山
赤城山(日本百名山:二回目登頂) [日本百名山]
奥白根山に登った翌日、苗場山にチャレンジしようと苗場山の麓の越後湯沢の宿に泊まる。もちろん、天気予報を確認した後での行動だ。さて、しかし二日前はほぼばっちりであった天気が、前日は9時から15時までのみが晴天となっている。これは、登山の最初の時間帯は雨かな、とちょっと嫌な気分になりながらも眠りに就く。さて、朝の3時に目を覚まし、行動を開始しようと天気予報をチェックすると、なんと晴天は12時から15時のみとなっている。そして、宿の窓の外は雨が降っている。これはアカン。雨が降っている中、苗場山にチャレンジする気はまったくない。とはいえ、宿でゴロゴロしているのも時間の無駄なので4時頃には宿を発った。どうせなら、登山口ぐらいを見ていこう、と敢えて高速道路ではなく国道17号で帰路に着く。さて、苗場山の登山口付近は雨こそ降っていなかったが、山の中腹以上はもう雨雲に覆われている。これはどうしょうもない、とそのまま17号を東京に向けて走って行くと、なんと県境を越えたトンネルを抜けたら晴天であった。なんだなんだ、と思うと同時に、これならどっか登れるな、ということに気づく。どこに行くか、ということだが、これは赤城山だな、と気づく。ちなみに、赤城山は以前、登ったことがあるのだが山頂は雲に覆われていてまったく展望が得られなかったので、そういう意味ではリベンジとしてもいいかなと思ったのである。
さて、沼田から赤城山へと向かう。黒檜山の登山口に着いたのは7時前。早起きは三文の得、という諺を思い出す。さて、黒檜山登山口から赤城山最高峰の黒檜山までの道のりは険しい。岩だらけで、しかも急勾配である。ということで、私がいつも携帯するストックを敢えて持たずにチャレンジする。加えて、手袋をするべきだったのだが、これはし忘れてしまい、あとで後悔する。
黒檜山までは、森の中をひたすら登っていく。あまり楽しくない。しかし、たまに大沼の素晴らしい展望が得られて、これが単調な上り坂にいいアクセントを与えてくれる。天気に恵まれ、これは黒檜山からの360度の素晴らしいパノラマが見られるぞ、と期待に胸を膨らませていたら、なんと山頂への分岐点に着いた時に、雲が舞い上がってきて、まったく東側の展望が得られない。と思っていたら、西側も雲に覆われてしまった。なんてついていない、というか赤城山とはつくづく相性が悪いと思わされた。山頂に着いたのは1時間20分後であった。
ここで軽くお握りを食べながら、さて、ここで待つか、すぐ帰るかと悩むが、すぐ帰ることにした。これは、結果的にいい判断であった。というのは、下山時には、山頂を覆う雲が灰色になりつつあり、下手したら雨に降られる可能性さえあったからだ。黒檜山の登山のポイントは下山も全然、楽じゃないことだ。私が注意深かったからかもしれないが、下山は登山よりむしろ時間がかかったぐらいである。昨日の奥白根山とはもちろんのこと、一週間前の磐梯山と比べても、相当今ひとつな百名山である。まあ、展望が得られたら別の印象を持ったかもしれないが、それを除いても、登山路の整備のされ無さ、その大変さ、登山途中の楽しみの無さ、ワイルド・フラワーが少ないこと、標高がそれほど高くないこと、などを考慮すると、近場にいい山があるのにわざわざチャレンジする必要性があるかなとも思ったりする。いや、唯一いい点は距離が短く、短時間で登って降りてこられることである。あと、東京からのアクセスは他の百名山よりはずっとよい。そういう点からはトレーニングとしては向いているかもしれない。私も展望が得られなかったことで、もう一度、チャレンジするような気もする。二度あることは三度ある、か三度目の正直か、どちらに出るかは分からないが。

<黒檜山の登山口>

<途中、大沼への美しい展望が楽しめる。晴天で素晴らしい天候だ>

<黒檜山登山ルートの険しい岩道。この岩道がほとんどずっと続く。全然、この岩登り、楽しくない>

<黒檜山の頂上は雲でほとんど何も見られず。あと30分、いや15分早く着いていれば・・・と悔やまれる>

<帰路でも大沼は展望できたが、一時間前と比べるとずっと曇っている>
さて、沼田から赤城山へと向かう。黒檜山の登山口に着いたのは7時前。早起きは三文の得、という諺を思い出す。さて、黒檜山登山口から赤城山最高峰の黒檜山までの道のりは険しい。岩だらけで、しかも急勾配である。ということで、私がいつも携帯するストックを敢えて持たずにチャレンジする。加えて、手袋をするべきだったのだが、これはし忘れてしまい、あとで後悔する。
黒檜山までは、森の中をひたすら登っていく。あまり楽しくない。しかし、たまに大沼の素晴らしい展望が得られて、これが単調な上り坂にいいアクセントを与えてくれる。天気に恵まれ、これは黒檜山からの360度の素晴らしいパノラマが見られるぞ、と期待に胸を膨らませていたら、なんと山頂への分岐点に着いた時に、雲が舞い上がってきて、まったく東側の展望が得られない。と思っていたら、西側も雲に覆われてしまった。なんてついていない、というか赤城山とはつくづく相性が悪いと思わされた。山頂に着いたのは1時間20分後であった。
ここで軽くお握りを食べながら、さて、ここで待つか、すぐ帰るかと悩むが、すぐ帰ることにした。これは、結果的にいい判断であった。というのは、下山時には、山頂を覆う雲が灰色になりつつあり、下手したら雨に降られる可能性さえあったからだ。黒檜山の登山のポイントは下山も全然、楽じゃないことだ。私が注意深かったからかもしれないが、下山は登山よりむしろ時間がかかったぐらいである。昨日の奥白根山とはもちろんのこと、一週間前の磐梯山と比べても、相当今ひとつな百名山である。まあ、展望が得られたら別の印象を持ったかもしれないが、それを除いても、登山路の整備のされ無さ、その大変さ、登山途中の楽しみの無さ、ワイルド・フラワーが少ないこと、標高がそれほど高くないこと、などを考慮すると、近場にいい山があるのにわざわざチャレンジする必要性があるかなとも思ったりする。いや、唯一いい点は距離が短く、短時間で登って降りてこられることである。あと、東京からのアクセスは他の百名山よりはずっとよい。そういう点からはトレーニングとしては向いているかもしれない。私も展望が得られなかったことで、もう一度、チャレンジするような気もする。二度あることは三度ある、か三度目の正直か、どちらに出るかは分からないが。

<黒檜山の登山口>

<途中、大沼への美しい展望が楽しめる。晴天で素晴らしい天候だ>

<黒檜山登山ルートの険しい岩道。この岩道がほとんどずっと続く。全然、この岩登り、楽しくない>

<黒檜山の頂上は雲でほとんど何も見られず。あと30分、いや15分早く着いていれば・・・と悔やまれる>

<帰路でも大沼は展望できたが、一時間前と比べるとずっと曇っている>
奥白根山(日本百名山40座登頂) [日本百名山]
奥白根山にチャレンジする。朝の4時過ぎに目黒区の自宅を自家用車で発つ。白根山のゴンドラの麓駅に着いたのは7時30分ぐらいである。7時30分はちょうどゴンドラの始発の時間であるので、タイミング的には絶妙であると言えるであろう。この日は晴天で、逆光であるが白根山の雄壮たる姿が見える。丸沼高原はスキー場が気に入っているので何回か来たことがあり、このゴンドラも随分と乗ったことがあるのだが、夏に来るのは初めてである。
さて、MarunumaではなくてMalnumaと書かれたゴンドラに乗って登山口まで一挙に上る。MalnumaのMalはスペイン語で「悪い」という意味なので、なんでMaruにしなくてMalなのか昔、気になっていたことを思い出した。しかし、その理由は今日になっても知らない。
ゴンドラで一挙に標高2000㍍地点まで上る。先週登った磐梯山の山頂より既に高い。標高が高いこともあり、空気が澄んでいて、フィトンチッドに溢れているような清涼さを感じる。さて、このゴンドラの駅からは、しばらくしっかりと整備された自然散策路で、牧歌的に歩いて行く。出発したのは8時ちょうどである。1時間弱で、自然散策路とは分岐し、本格的な登山路になる。いきなり斜面は急になり、呼吸も荒くなる。ただし、登山道はダケカンバの森の中を行くのだが、その美しさに息を呑むぐらいだ。日本は素晴らしい自然に恵まれていることを再確認する。しかも、東京から自動車で三時間ちょっとでこんな大自然にアクセスできるなんて、よく考えたら凄いことだ。ロンドンでもパリでもベルリンでも、このような大自然に自動車で三時間以内では行くことはできない。このダケカンバの森を一時間ぐらい歩くと、森林限界に達し、白根山が目の前に聳え立つ。ここからはガレ場である。それにしても百名山はガレ場を登らせる山が多い。いかに、日本の山が火山活動でつくられたかを思い知らされる。ガレ場を歩くポイントは、足もとをしっかりと確認して、浮き石に足を取られないようにすることだ。あせらず一歩一歩前に進んでいく。ふと振り返ると、富士山がその姿を現している。周辺の山々から図抜けて高いのでよく目立つ。富士山はその美しさだけでなく、圧倒的な高さによっても他の山々から飛び抜けた存在であることを、標高2500㍍ぐらいから望むとよく理解できる。さて、富士山の姿に勇気づけられ、ガレ場を前進していくと、無事、白根山の山頂の一角に着く。ただ、本当の頂上はもう一つの山頂であり、一度、窪地のようなところに降りて再び登る。山頂に着いたのは10時ちょうどであった。二時間で登れたことになる。
山頂からは360度の展望が得られ、白根山がひときわ周辺の山より高いこともあって、本当に感動的な景色を楽しむことができる。東側のすぐ隣には男体山と中禅寺湖、そして北に目を向けると会津駒ヶ岳、その左隣には燧ヶ岳の特徴的な山容がどんと構える。燧ヶ岳の左方向には至仏山が見られるが、燧ヶ岳からは意外と離れており、尾瀬湿原の大きさにちょっと驚かされる。そして、武尊山や皇海山も見える。さらには、前述した富士山もくっきりとその勇姿を現している。そして何より眼下に見られるエメラルドグリーンの五色沼の美しさが目を引く。北海道の阿寒国立公園にあるオンネトーよりもさらに心を惹かれる色彩だ。ちょっと宝石のような輝きを放っている。いやはや、こういう体験をすると登山をしたことのご褒美をもらえたような気分だ。簡単な昼食もこの山頂で取る。
そのまま、矢陀カ池を通って下山しようと思ったが、思いのほか早く登頂できたので、せっかくなので五色沼に寄ることにする。こちらのルートもガレ場なので降りるには足もとを注意しなくてはならない。マルバダケブキの黄色の中を歩いていくのは心躍る気分だ。マルバダケブキの黄色と五色沼のエメラルドグリーンとのコントラストが美しい。五色沼に着いたのは12時ちょっと前。思ったよりも時間はかかった。五色沼は遠くからだけでなく、畔からでもその美しさは変わらない。太陽が雲に隠れると、その色がエメラルドグリーンから藍色へと変わっていく。そして、その背景に見える白根山の堂々とした山容が素晴らしい。アメリカのシエラネバダ山脈の山々で感じるような荘厳さ、自然の素晴らしさを感じる。こんなところが北関東にあったのは驚きである。
しばらく五色沼の素晴らしさを堪能して、下山に入る。とはいえ、そこから矢陀カ池までは80㍍の高さを登らなくてはならない。矢陀カ池までは25分ぐらいで着いた。さて、ここは菅沼新道とロープウェイ駅との分岐点なのだが、ロープウェイ駅へのルートは「白根山」とだけ書いてあった。いや、ちょっと気をつければ「ロープウェイ駅もこちら」と書いてあったのだが、その時は、他の登山客がちょうど案内板の前にいたこともあり、遠目でチェックをした私は見落としてしまった。「白根山にはもう登らないよな」と思って、そのまま「菅沼登山口」に向かって下山をし始めた。この登山口も苔の緑が美しく、下山でもあり、楽しい気分で歩いていたのだが20分ぐらい歩いたところで「菅沼登山口まであと2.1キロメートル」の看板をみて、嫌な予感がして地図を確認するとまったくルートを間違っていることに気づく。既に結構、疲れていたので900㍍の来た道をまた登ると考えるとゾッとしたが他の選択肢はないので来た道を戻る。矢陀カ池には20分ほどで戻る。時間としては14時になっていた。そこから「白根山」に向かう道を行き、ちょっと登ると白根山とロープウェイ駅との分岐点に達する。右側のルートを取って、ロープウェイ駅へと向かう。急勾配の坂をゆっくりと歩いて降りていく。約1時間で自然散策路に合流し、せっかくなので「血の池地獄」という場所を見に行ったのだが、これはたいへん今ひとつであった。今日の登山で、唯一がっかりしたのはこれであった。というか、ネーミングと池のギャップが凄すぎる。あまりにがっかりしたので写真を撮る気力も出てこなかった。
登山口に戻ったのは15時20分。いらぬところで40分ほど損したので、思ったよりも遅くなってしまった。全行程で7時間ちょっと。
これまで北関東・南東北の山は結構、登ってきたが、この奥白根山はそれらの中でも別格の素晴らしさであった。寿司屋でいうと、先週の磐梯山が1500円ぐらいのランチ握りであるとすると、奥白根山は10000円の高級店でのランチ握りという感じである。これまでの登山の中でもベスト5に入る素晴らしい山であった。

<朝8時のロープウェイの山頂駅からみる奥白根山>

<ダケカンバの森を歩いて行く>

<朝の木漏れ日が美しい>

<登山途中から武尊山の雄壮たる山容が望める>

<森林限界を越えるとガレ場が広がる。と同時に白根山がその姿を現す>

<振り返ると、富士山がその姿をはっきりと見ることができた>

<白根山の山頂から北側への展望。燧ヶ岳を見ることができる>

<白根山の山頂からの展望。男体山と中禅寺湖がすぐ目の前に広がる>

<山頂からの五色沼の展望>

<マルバダケブキの黄色と五色沼のエメラルドグリーンとのコントラストが美しい>

<五色沼からの白根山の展望>

<五色沼の息を呑むようなエメラルドグリーン>

<矢陀カ池>

<矢陀カ池から白根山を展望する>

<下山時にロープウェイ駅から白根山を望んだところ>
さて、MarunumaではなくてMalnumaと書かれたゴンドラに乗って登山口まで一挙に上る。MalnumaのMalはスペイン語で「悪い」という意味なので、なんでMaruにしなくてMalなのか昔、気になっていたことを思い出した。しかし、その理由は今日になっても知らない。
ゴンドラで一挙に標高2000㍍地点まで上る。先週登った磐梯山の山頂より既に高い。標高が高いこともあり、空気が澄んでいて、フィトンチッドに溢れているような清涼さを感じる。さて、このゴンドラの駅からは、しばらくしっかりと整備された自然散策路で、牧歌的に歩いて行く。出発したのは8時ちょうどである。1時間弱で、自然散策路とは分岐し、本格的な登山路になる。いきなり斜面は急になり、呼吸も荒くなる。ただし、登山道はダケカンバの森の中を行くのだが、その美しさに息を呑むぐらいだ。日本は素晴らしい自然に恵まれていることを再確認する。しかも、東京から自動車で三時間ちょっとでこんな大自然にアクセスできるなんて、よく考えたら凄いことだ。ロンドンでもパリでもベルリンでも、このような大自然に自動車で三時間以内では行くことはできない。このダケカンバの森を一時間ぐらい歩くと、森林限界に達し、白根山が目の前に聳え立つ。ここからはガレ場である。それにしても百名山はガレ場を登らせる山が多い。いかに、日本の山が火山活動でつくられたかを思い知らされる。ガレ場を歩くポイントは、足もとをしっかりと確認して、浮き石に足を取られないようにすることだ。あせらず一歩一歩前に進んでいく。ふと振り返ると、富士山がその姿を現している。周辺の山々から図抜けて高いのでよく目立つ。富士山はその美しさだけでなく、圧倒的な高さによっても他の山々から飛び抜けた存在であることを、標高2500㍍ぐらいから望むとよく理解できる。さて、富士山の姿に勇気づけられ、ガレ場を前進していくと、無事、白根山の山頂の一角に着く。ただ、本当の頂上はもう一つの山頂であり、一度、窪地のようなところに降りて再び登る。山頂に着いたのは10時ちょうどであった。二時間で登れたことになる。
山頂からは360度の展望が得られ、白根山がひときわ周辺の山より高いこともあって、本当に感動的な景色を楽しむことができる。東側のすぐ隣には男体山と中禅寺湖、そして北に目を向けると会津駒ヶ岳、その左隣には燧ヶ岳の特徴的な山容がどんと構える。燧ヶ岳の左方向には至仏山が見られるが、燧ヶ岳からは意外と離れており、尾瀬湿原の大きさにちょっと驚かされる。そして、武尊山や皇海山も見える。さらには、前述した富士山もくっきりとその勇姿を現している。そして何より眼下に見られるエメラルドグリーンの五色沼の美しさが目を引く。北海道の阿寒国立公園にあるオンネトーよりもさらに心を惹かれる色彩だ。ちょっと宝石のような輝きを放っている。いやはや、こういう体験をすると登山をしたことのご褒美をもらえたような気分だ。簡単な昼食もこの山頂で取る。
そのまま、矢陀カ池を通って下山しようと思ったが、思いのほか早く登頂できたので、せっかくなので五色沼に寄ることにする。こちらのルートもガレ場なので降りるには足もとを注意しなくてはならない。マルバダケブキの黄色の中を歩いていくのは心躍る気分だ。マルバダケブキの黄色と五色沼のエメラルドグリーンとのコントラストが美しい。五色沼に着いたのは12時ちょっと前。思ったよりも時間はかかった。五色沼は遠くからだけでなく、畔からでもその美しさは変わらない。太陽が雲に隠れると、その色がエメラルドグリーンから藍色へと変わっていく。そして、その背景に見える白根山の堂々とした山容が素晴らしい。アメリカのシエラネバダ山脈の山々で感じるような荘厳さ、自然の素晴らしさを感じる。こんなところが北関東にあったのは驚きである。
しばらく五色沼の素晴らしさを堪能して、下山に入る。とはいえ、そこから矢陀カ池までは80㍍の高さを登らなくてはならない。矢陀カ池までは25分ぐらいで着いた。さて、ここは菅沼新道とロープウェイ駅との分岐点なのだが、ロープウェイ駅へのルートは「白根山」とだけ書いてあった。いや、ちょっと気をつければ「ロープウェイ駅もこちら」と書いてあったのだが、その時は、他の登山客がちょうど案内板の前にいたこともあり、遠目でチェックをした私は見落としてしまった。「白根山にはもう登らないよな」と思って、そのまま「菅沼登山口」に向かって下山をし始めた。この登山口も苔の緑が美しく、下山でもあり、楽しい気分で歩いていたのだが20分ぐらい歩いたところで「菅沼登山口まであと2.1キロメートル」の看板をみて、嫌な予感がして地図を確認するとまったくルートを間違っていることに気づく。既に結構、疲れていたので900㍍の来た道をまた登ると考えるとゾッとしたが他の選択肢はないので来た道を戻る。矢陀カ池には20分ほどで戻る。時間としては14時になっていた。そこから「白根山」に向かう道を行き、ちょっと登ると白根山とロープウェイ駅との分岐点に達する。右側のルートを取って、ロープウェイ駅へと向かう。急勾配の坂をゆっくりと歩いて降りていく。約1時間で自然散策路に合流し、せっかくなので「血の池地獄」という場所を見に行ったのだが、これはたいへん今ひとつであった。今日の登山で、唯一がっかりしたのはこれであった。というか、ネーミングと池のギャップが凄すぎる。あまりにがっかりしたので写真を撮る気力も出てこなかった。
登山口に戻ったのは15時20分。いらぬところで40分ほど損したので、思ったよりも遅くなってしまった。全行程で7時間ちょっと。
これまで北関東・南東北の山は結構、登ってきたが、この奥白根山はそれらの中でも別格の素晴らしさであった。寿司屋でいうと、先週の磐梯山が1500円ぐらいのランチ握りであるとすると、奥白根山は10000円の高級店でのランチ握りという感じである。これまでの登山の中でもベスト5に入る素晴らしい山であった。

<朝8時のロープウェイの山頂駅からみる奥白根山>

<ダケカンバの森を歩いて行く>

<朝の木漏れ日が美しい>

<登山途中から武尊山の雄壮たる山容が望める>

<森林限界を越えるとガレ場が広がる。と同時に白根山がその姿を現す>

<振り返ると、富士山がその姿をはっきりと見ることができた>

<白根山の山頂から北側への展望。燧ヶ岳を見ることができる>

<白根山の山頂からの展望。男体山と中禅寺湖がすぐ目の前に広がる>

<山頂からの五色沼の展望>

<マルバダケブキの黄色と五色沼のエメラルドグリーンとのコントラストが美しい>

<五色沼からの白根山の展望>

<五色沼の息を呑むようなエメラルドグリーン>

<矢陀カ池>

<矢陀カ池から白根山を展望する>

<下山時にロープウェイ駅から白根山を望んだところ>
磐梯山(日本百名山39座登頂) [日本百名山]
ちょうど1年ぶりに百名山に挑戦する。このように時間が空いてしまったのは昨年の秋が忙しかったのと、今年前半はコロナで山登りという気分にもなれなかったからである。さて、一年ぶりに挑戦したのは日帰りでも行ける磐梯山。東京の自宅を7時ちょっと前に出発。道路は混んでいなかったし、それなりに飛ばしたのだが八方台に到着したのは11時。八方台の駐車場はそれなりのスペースがあるのだが、さすが11時だとほぼ満車状態で私はちょうど最後のスペースに停められることができた。ただ、ここが満車でも近くにもまだ駐車場はある。
さて、八方台で既に標高が1200㍍ほどあるので、600㍍ちょっと登るだけである。距離的にも短く、大したことがないと思っていたのだが、なかなかの急勾配の厳しい登山であった。というか距離が短かったために助かった。この急勾配で距離が長いと相当、バテる。
駐車場からすぐ美しいブナ林が広がる。これらのブナ林は明治時代の噴火以降に形成されたので100年ぐらいの若いブナ林である。このブナ林を抜けてしばらく歩くと中ノ湯跡という、元いで湯の跡地がある。周辺は硫黄臭が強い。
中ノ湯では裏磐梯からのコースと合流するが、ここらへんから急登となる。土砂崩れの跡などを注意深く歩いて行くと、弘法清水に着く。弘法清水では湧き水が出ていて、その冷たさと美味しさに感動する。想像以上の急坂ということもあって、随分と水分補給をしたので、ここで冷たい水を確保できたのは大きい。ここで元気を回復して、最後の30分ほどのアプローチに臨む。さて、このアプローチ、メチャクチャ急坂である。わずか500㍍ぐらいの距離だが、息が上がり、なかなか前に進めない。一年ぶりの登山ということもあり、この坂は堪えた。
しかし、頑張って30分ほど踏ん張ると磐梯山の山頂に着く。ちょうど14時だったので3時間弱かかったことになる。山頂からは、まさに360度の大展望が得られる。南には猪苗代湖、そして北には桧原湖が展望できる。ちょうど私が登頂した時には雲も周りになく、すばらしい展望を愉しむことができた。ただ、トンボやブヨがたくさんいるので、食事を落ち着いて取ることはかなわなかった。
行きはあまりの急坂にそのような余裕はなかったが、帰りはカメラを取り出し、山頂と弘法清水の登山路に咲くワイルド・フラワーを撮影する。オニユリを初めとして、目を楽しませてくれる花々が多く咲いている。
帰りも坂が急なので、注意深く降りていかなくてはならない。とはいえ、登りのような心肺機能に来る負担は全然、ない。ただ、膝には気をつけないといけないぐらいの急坂である。駐車場に戻ったのは16時。自分の体力の衰えを自覚させてくれた厳しい登山であったが、その素晴らしい展望、登山道沿いのワイルド・フラワーの美しさは、登ってよかったと強く思わせる。8月の晴天日であったが、あまり直射日光を浴びるところが多くないこともプラスであった。
【登山口にいきなり「熊注意」の看板。若干、緊張が走る】

【登山口からは美しいブナ林の中を歩いて行く】

【中ノ湯からは磐梯山の雄姿を眺めることができる】

【中ノ湯の廃墟跡】

【桧原湖の素晴らしい景色が望める】

【弘法清水から山頂を望む】

【弘法清水の冷たく、美味しい水で英気を養う】

【山頂から猪苗代湖を望む】

【山頂から秋元湖を望む】

【山頂には磐梯明神の石祠が祀られている】

【ホタルブクロ】

【ウスユキソウ】

【オニユリ】


さて、八方台で既に標高が1200㍍ほどあるので、600㍍ちょっと登るだけである。距離的にも短く、大したことがないと思っていたのだが、なかなかの急勾配の厳しい登山であった。というか距離が短かったために助かった。この急勾配で距離が長いと相当、バテる。
駐車場からすぐ美しいブナ林が広がる。これらのブナ林は明治時代の噴火以降に形成されたので100年ぐらいの若いブナ林である。このブナ林を抜けてしばらく歩くと中ノ湯跡という、元いで湯の跡地がある。周辺は硫黄臭が強い。
中ノ湯では裏磐梯からのコースと合流するが、ここらへんから急登となる。土砂崩れの跡などを注意深く歩いて行くと、弘法清水に着く。弘法清水では湧き水が出ていて、その冷たさと美味しさに感動する。想像以上の急坂ということもあって、随分と水分補給をしたので、ここで冷たい水を確保できたのは大きい。ここで元気を回復して、最後の30分ほどのアプローチに臨む。さて、このアプローチ、メチャクチャ急坂である。わずか500㍍ぐらいの距離だが、息が上がり、なかなか前に進めない。一年ぶりの登山ということもあり、この坂は堪えた。
しかし、頑張って30分ほど踏ん張ると磐梯山の山頂に着く。ちょうど14時だったので3時間弱かかったことになる。山頂からは、まさに360度の大展望が得られる。南には猪苗代湖、そして北には桧原湖が展望できる。ちょうど私が登頂した時には雲も周りになく、すばらしい展望を愉しむことができた。ただ、トンボやブヨがたくさんいるので、食事を落ち着いて取ることはかなわなかった。
行きはあまりの急坂にそのような余裕はなかったが、帰りはカメラを取り出し、山頂と弘法清水の登山路に咲くワイルド・フラワーを撮影する。オニユリを初めとして、目を楽しませてくれる花々が多く咲いている。
帰りも坂が急なので、注意深く降りていかなくてはならない。とはいえ、登りのような心肺機能に来る負担は全然、ない。ただ、膝には気をつけないといけないぐらいの急坂である。駐車場に戻ったのは16時。自分の体力の衰えを自覚させてくれた厳しい登山であったが、その素晴らしい展望、登山道沿いのワイルド・フラワーの美しさは、登ってよかったと強く思わせる。8月の晴天日であったが、あまり直射日光を浴びるところが多くないこともプラスであった。
【登山口にいきなり「熊注意」の看板。若干、緊張が走る】

【登山口からは美しいブナ林の中を歩いて行く】

【中ノ湯からは磐梯山の雄姿を眺めることができる】

【中ノ湯の廃墟跡】

【桧原湖の素晴らしい景色が望める】

【弘法清水から山頂を望む】

【弘法清水の冷たく、美味しい水で英気を養う】

【山頂から猪苗代湖を望む】

【山頂から秋元湖を望む】

【山頂には磐梯明神の石祠が祀られている】

【ホタルブクロ】

【ウスユキソウ】

【オニユリ】


常念岳(日本百名山38座登頂) [日本百名山]
常念岳に挑戦した。前日に松本市内のビジネスホテルに泊まり、3時15分に起床。4時前にチェックアウトして、一ノ沢の駐車場へ向かう。5時前に駐車場に到着。ちょうど一両分の空きスペースがあったので、そこに駐車する。ついている。そして、5時10分頃、登山開始。ここから一ノ沢の登山口までは1200メートル。ここにはトイレなどもある。ここは5時40分に出発。出発して500メートルぐらいで山の神の神社があり、登山の無事を祈って出発。烏帽子沢の渓流を左手にみつつ、緩やかに高度を上げていく。途中、沢を通るところもあり、泥濘みのところもあったりしたが、倒木をうまく使って歩けば問題はない。烏帽子沢の渓流は美しく、歩いていて楽しい。7時前ぐらいに大滝に着く。登山口から2.1 キロ、標高として300メートル稼いだが、常念小屋まではまだまだだ。さらに一時間、丸太橋を渡り、烏帽子沢の右へ行ったり左を行ったりして、笠原沢に到達したのがちょうど8時。この笠原沢は標高的には1900メートルで登山口からは600メートル標高を稼いだことになり、ちょうど半分ぐらい登ったことになる。そして、しばらく行くと胸突き八丁に差し掛かる。ここからはジグザグに高度を上げていく。烏帽子沢にはまだ長大な雪渓が残っている。常念岳もこちらから望めるのだが、ガスがかかっていてその全容はみることはできない。
そして烏帽子沢を丸太橋で渡ると、最終水場に9時15分頃に到着する。ここまで来ると、あと常念小屋まで1キロメートル。高さも200メートルだけだ。難所と言われる胸突き八丁も越えたし、もうあと一息と思ったのだが、実はここから常念小屋までがとても困難であった。最終水場から常念小屋までの方が、むしろ胸突き八丁とかわらぬほどの急坂。最近はあまりなかった大腿筋が痙攣し始め、これは攣るかもしれないと緊張する。攣ると面倒なので休み、休みゆっくりと登っていくことにする。途中、三箇所、ベンチがあるのだが、三箇所ともゆっくりと休んで上がっていった。その結果、常念小屋に着いたのは10時30分と最終水場から1時間15分もかかった。これはコースタイムの50分より大幅に遅い。とはいえ、攣らずにどうにか到着できたのはよかった。
そのまま常念小屋でチェックインをする。常念小屋は定員200名で、3日前に予約した時は既に250名が予約しているので、一畳を二人で共有して下さいと言われ、覚悟をしていたのだが、3階の部屋は天井が低いので一畳を一人で使うことができた。常念小屋で早い昼食を取る。私が注文したのは牛丼で1000円だった。なかなか山小屋としては味のクオリティは高い。ここで荷物を置き、水とカメラだけを入れたザックを担いで常念岳を覆い被さっていたガスが晴れたのを確認して12時頃から登山にチャレンジする。
常念岳まではジグザグに礫の道を歩いていく。展望は抜群で、槍ヶ岳から涸沢、穂高岳と素晴らしい展望を右手に見つつ、左手には安曇野市の美しい田園風景を見つつ、登っていく。この坂も相当、厳しいが、常念小屋で休んだこともあり、大腿筋はどうにか我慢してくれている。展望の素晴らしさが、また疲れを吹き飛ばしてもくれる。
常念岳に到着したのは13時30分。これもコースタイムを20分もオーバーしてしまった。大腿筋の痙攣だけではなく、なんか登りながら立ちくらみにもなりそうで、もう満身創痍での登頂であった。そういう意味では、これまでの登山の中でも今回の常念岳登頂は相当、厳しいものであったと考えられる。
とはいえ、常念岳からの展望はまさに360度の絶景で、なぜ多くの人々が北アルプスに魅了されるのかがよく理解できた。この素晴らしい絶景を見るためなら、身体が多少、悲鳴を上げてもその価値があると思われる。槍岳は雲に姿を隠して、なかなかその全貌を見せなかったが、小屋に着いた頃に、その素晴らしくもユニークな偉容を我々に見せてくれる。
絶景を堪能した後、ゆっくりと常念小屋まで下山をし、5時の夕食まで食堂にて生ビールを飲み、時間を潰す。ちなみに、このビール、身体が欲していたのだろうか、人生でも5本の指に入るぐらいの美味しさであった。夕食はハンバーグ定食。
夕食を食べた後、6時にはもう就寝し、一度起きるが次に気づいたら3時。ゆっくりと身支度をして、4時30分頃に朝食を食べる。朝食は鮎煮と卵焼き、ソーセージなどでなかなか美味しかった。夕食よりも美味しいような気もする。5時にご来光を見て、下山開始は5時30分。胸突き八丁に差し掛かったのは6時18分。登りとは偉い違うインターバル・タイム。登山口に到着は9時であった。登りと違って、下りは特に問題もなかった。

(登山口の手前にある駐車場。ぎりぎり一車輌分が空いていて助かった)

(山の神の神社で登山の無事を祈る)

(登山道にはワイルド・フラワーが咲き誇っているが、その中でもその優雅さで目立つのはクルマユリである)

(胸突き八丁からは烏帽子沢の雪渓を展望できる)

(常念小屋に着いた時は常念岳も小屋もガスに覆われていた)

(常念小屋での昼食。1000円の牛丼は山小屋としては相当のクオリティであったかと思われる)

(常念小屋から常念岳の肩の部分を展望する。これは、常念岳の山頂ではない)

(常念岳への登山道はなかなか厳しい)

(常念岳の登山途中から常念小屋を振り返って望む。キャンプ場のテントの色彩が美しい)

(常念岳の肩から常念岳の山頂を望む)

(常念岳の山頂までの道は険しいが左右に展開する素晴らしい絶景が疲れを吹き飛ばしてくれる)

(登山途上に咲くしゃくなげの花)

(登山道から安曇野市側を展望する)

(常念岳の山頂)

(常念岳の山頂から涸沢、穂高岳を展望する)

(常念岳から大天井岳の方を展望する)

(常念岳から横通岳の方を展望する)

(常念小屋に近づいた時、それまで雲に見え隠れした槍岳が全貌を見させる)

(常念小屋での朝食)

(常念小屋からのご来光)

(朝日によって赤く染まった槍岳)

(胸突き八丁沿道に見られるワイルド・フラワー)


(烏帽子沢の美しい渓流)
そして烏帽子沢を丸太橋で渡ると、最終水場に9時15分頃に到着する。ここまで来ると、あと常念小屋まで1キロメートル。高さも200メートルだけだ。難所と言われる胸突き八丁も越えたし、もうあと一息と思ったのだが、実はここから常念小屋までがとても困難であった。最終水場から常念小屋までの方が、むしろ胸突き八丁とかわらぬほどの急坂。最近はあまりなかった大腿筋が痙攣し始め、これは攣るかもしれないと緊張する。攣ると面倒なので休み、休みゆっくりと登っていくことにする。途中、三箇所、ベンチがあるのだが、三箇所ともゆっくりと休んで上がっていった。その結果、常念小屋に着いたのは10時30分と最終水場から1時間15分もかかった。これはコースタイムの50分より大幅に遅い。とはいえ、攣らずにどうにか到着できたのはよかった。
そのまま常念小屋でチェックインをする。常念小屋は定員200名で、3日前に予約した時は既に250名が予約しているので、一畳を二人で共有して下さいと言われ、覚悟をしていたのだが、3階の部屋は天井が低いので一畳を一人で使うことができた。常念小屋で早い昼食を取る。私が注文したのは牛丼で1000円だった。なかなか山小屋としては味のクオリティは高い。ここで荷物を置き、水とカメラだけを入れたザックを担いで常念岳を覆い被さっていたガスが晴れたのを確認して12時頃から登山にチャレンジする。
常念岳まではジグザグに礫の道を歩いていく。展望は抜群で、槍ヶ岳から涸沢、穂高岳と素晴らしい展望を右手に見つつ、左手には安曇野市の美しい田園風景を見つつ、登っていく。この坂も相当、厳しいが、常念小屋で休んだこともあり、大腿筋はどうにか我慢してくれている。展望の素晴らしさが、また疲れを吹き飛ばしてもくれる。
常念岳に到着したのは13時30分。これもコースタイムを20分もオーバーしてしまった。大腿筋の痙攣だけではなく、なんか登りながら立ちくらみにもなりそうで、もう満身創痍での登頂であった。そういう意味では、これまでの登山の中でも今回の常念岳登頂は相当、厳しいものであったと考えられる。
とはいえ、常念岳からの展望はまさに360度の絶景で、なぜ多くの人々が北アルプスに魅了されるのかがよく理解できた。この素晴らしい絶景を見るためなら、身体が多少、悲鳴を上げてもその価値があると思われる。槍岳は雲に姿を隠して、なかなかその全貌を見せなかったが、小屋に着いた頃に、その素晴らしくもユニークな偉容を我々に見せてくれる。
絶景を堪能した後、ゆっくりと常念小屋まで下山をし、5時の夕食まで食堂にて生ビールを飲み、時間を潰す。ちなみに、このビール、身体が欲していたのだろうか、人生でも5本の指に入るぐらいの美味しさであった。夕食はハンバーグ定食。
夕食を食べた後、6時にはもう就寝し、一度起きるが次に気づいたら3時。ゆっくりと身支度をして、4時30分頃に朝食を食べる。朝食は鮎煮と卵焼き、ソーセージなどでなかなか美味しかった。夕食よりも美味しいような気もする。5時にご来光を見て、下山開始は5時30分。胸突き八丁に差し掛かったのは6時18分。登りとは偉い違うインターバル・タイム。登山口に到着は9時であった。登りと違って、下りは特に問題もなかった。

(登山口の手前にある駐車場。ぎりぎり一車輌分が空いていて助かった)

(山の神の神社で登山の無事を祈る)

(登山道にはワイルド・フラワーが咲き誇っているが、その中でもその優雅さで目立つのはクルマユリである)

(胸突き八丁からは烏帽子沢の雪渓を展望できる)

(常念小屋に着いた時は常念岳も小屋もガスに覆われていた)

(常念小屋での昼食。1000円の牛丼は山小屋としては相当のクオリティであったかと思われる)

(常念小屋から常念岳の肩の部分を展望する。これは、常念岳の山頂ではない)

(常念岳への登山道はなかなか厳しい)

(常念岳の登山途中から常念小屋を振り返って望む。キャンプ場のテントの色彩が美しい)

(常念岳の肩から常念岳の山頂を望む)

(常念岳の山頂までの道は険しいが左右に展開する素晴らしい絶景が疲れを吹き飛ばしてくれる)

(登山途上に咲くしゃくなげの花)

(登山道から安曇野市側を展望する)

(常念岳の山頂)

(常念岳の山頂から涸沢、穂高岳を展望する)

(常念岳から大天井岳の方を展望する)

(常念岳から横通岳の方を展望する)

(常念小屋に近づいた時、それまで雲に見え隠れした槍岳が全貌を見させる)

(常念小屋での朝食)

(常念小屋からのご来光)

(朝日によって赤く染まった槍岳)

(胸突き八丁沿道に見られるワイルド・フラワー)


(烏帽子沢の美しい渓流)
蔵王山(日本百名山37座登頂) [日本百名山]
鶴岡市に月曜日に用事がある。ということで、日曜日に蔵王山に登ってから鶴岡市に向かうことにした。早朝、蔵王に向かおうとしたが、始発に乗る時間に起きれる自信がなかったので、土曜日の夜に白石蔵王にまで向かう。駅そばのホテルに泊まり、レンタカー会社が開業する8時ちょうどに車を借りて蔵王山のトレイルヘッドでもある刈田峠に行く。道は結構、幅が狭いワインディング・ロードで刈田峠の駐車場に着いたのは9時30分近くであった。ちなみに、この刈田峠の駐車場に入るには540円を支払わなくてはならない。
さて、刈田峠周辺は霧が出ており、お釜もまったく見えなかったが、しばらく登山をすると霧も晴れ、緑色の見事なお釜を望むことができた。この緑色は抹茶色であったが、隣でそれを見ていた人は、今日は抹茶色だが、エメラルドグリーンになったり、色々と天気によって変わると説明してくれる。ちなみに抹茶色の時は珍しいようだ。
その後、活火山特有の岩と砂、時々ちょっとした緑、といった馬の背といわれる尾根道の登山道を歩いて行くと1時間もしないうちに、蔵王では最高峰の熊野岳に登頂する。山形盆地の方は雲が発達していたが、太平洋側は素晴らしい展望が得られることができた。山形盆地も北部は展望することができた。なかなかの絶景だ。
熊野岳には斎藤茂吉の歌碑、熊野神社と避難小屋がある。火山ではあるが、蓼科山、岩木山などと違い、頂上が礫ではなく平らなので足に優しい。そこで、おにぎりなど消費したカロリー分を吸収していると、雲がどんどんと迫ってくるので、そのまま帰路に着く。帰路に着き始めたら、もうほとんど登山道は霧の中で、帰りの駐車場までほとんど視界はないに等しかった。ただ、登山道に沿って、電信柱のようなものが立っているので道を迷わずに戻ることができた。帰路はお釜もまったく霧で見ることができなかった。たかだか1時間もないほどの差だが、1時間遅れて登山を開始したらまったく蔵王山の印象は変わったものとなったであろう。本当、登山はタイミングが大事であることを思い知る。
刈田峠の駐車場に戻ったのは11時30分。休憩を入れても2時間で、これまでの百名山登山でも最も簡単な部類であったが、霧に覆われる前に登頂できたので、満足のいく登山となった。

(駐車場から山形方面を望む)

(駐車場からしばらくは舗装された極めて歩きやすい道を行く)

(お釜の見事な姿。今日は抹茶色であったが、色は天気や太陽の光によって大きく変わるとのこと)

(1時間もしないうちに山頂が見えてくる)

(山頂手前で山形方面を望む)

(熊野岳山頂)

(山頂)

(帰路は濃霧の中を歩く。電信柱のような柱があるので迷わず戻れたが、これがなかったら結構、不安になったかもしれない)

(帰りはお釜もまったく見えず。1時間足らずの差でこの違い)

(駐車場からの展望も2時間弱でこんなに違った)
さて、刈田峠周辺は霧が出ており、お釜もまったく見えなかったが、しばらく登山をすると霧も晴れ、緑色の見事なお釜を望むことができた。この緑色は抹茶色であったが、隣でそれを見ていた人は、今日は抹茶色だが、エメラルドグリーンになったり、色々と天気によって変わると説明してくれる。ちなみに抹茶色の時は珍しいようだ。
その後、活火山特有の岩と砂、時々ちょっとした緑、といった馬の背といわれる尾根道の登山道を歩いて行くと1時間もしないうちに、蔵王では最高峰の熊野岳に登頂する。山形盆地の方は雲が発達していたが、太平洋側は素晴らしい展望が得られることができた。山形盆地も北部は展望することができた。なかなかの絶景だ。
熊野岳には斎藤茂吉の歌碑、熊野神社と避難小屋がある。火山ではあるが、蓼科山、岩木山などと違い、頂上が礫ではなく平らなので足に優しい。そこで、おにぎりなど消費したカロリー分を吸収していると、雲がどんどんと迫ってくるので、そのまま帰路に着く。帰路に着き始めたら、もうほとんど登山道は霧の中で、帰りの駐車場までほとんど視界はないに等しかった。ただ、登山道に沿って、電信柱のようなものが立っているので道を迷わずに戻ることができた。帰路はお釜もまったく霧で見ることができなかった。たかだか1時間もないほどの差だが、1時間遅れて登山を開始したらまったく蔵王山の印象は変わったものとなったであろう。本当、登山はタイミングが大事であることを思い知る。
刈田峠の駐車場に戻ったのは11時30分。休憩を入れても2時間で、これまでの百名山登山でも最も簡単な部類であったが、霧に覆われる前に登頂できたので、満足のいく登山となった。

(駐車場から山形方面を望む)

(駐車場からしばらくは舗装された極めて歩きやすい道を行く)

(お釜の見事な姿。今日は抹茶色であったが、色は天気や太陽の光によって大きく変わるとのこと)

(1時間もしないうちに山頂が見えてくる)

(山頂手前で山形方面を望む)

(熊野岳山頂)

(山頂)

(帰路は濃霧の中を歩く。電信柱のような柱があるので迷わず戻れたが、これがなかったら結構、不安になったかもしれない)

(帰りはお釜もまったく見えず。1時間足らずの差でこの違い)

(駐車場からの展望も2時間弱でこんなに違った)
祖母山(日本百名山36座登頂) [日本百名山]
祖母山にチャレンジする。祖母山には3つの主要な登山口がある。神原登山口と尾平登山口、そして北谷登山口である。標高はそれぞれ390メートル、590メートル、1111メートル。これは絶対、北谷登山口であろう。町のホームページによると、北谷登山口の駐車場は使用できず、2.4キロメートル手前の一の鳥居の駐車場を使えとのこと。これもゴールデンウィークのみだけ開いているそうだ。これは、往復4.8キロメートルも余計に歩かなくてはならないが、標高は100メートル下がるだけなので、それでも北谷登山口に向かう。
さて、ゴールデンウィーク中であったので、これは相当、駐車場が混むことを予測した。昨日、久住山の登山口の牧ノ戸登山口が6時過ぎで200台のキャパを越えていたことを考えると、15台しか駐車できない北谷登山口の一の鳥居の駐車場はあっという間に満車になるだろう。
(その情報源となった高千穂町のHP。http://takachiho-kanko.info/sightseeing/detail.php?log=1381220521)
ということで、熊本空港そばのホテルは2時ちょっと過ぎに起き、3時にはチェックアウトをした。北谷登山口は東へ60キロメートルちょっと。昨日の牧ノ戸登山口とほぼ距離は一緒である。私のレンタカーのナビは古くて、道路が工事中で通行止めの情報を反映させていないが、昨日、失敗したので同じ轍を二度は踏まない。スムーズに移動していく。北谷登山口の入り口が分からないのではと不安に思ったが、看板がしっかりと出ていたので、迷わず、そちらに向かうことができた。
ホームページ等は登山口までの林道は車高が低いと気をつけろなどの注意をしていたが、それほどの悪路ではなかった。むしろ、拍子抜けしたぐらいだ。さて、一の鳥居の駐車場には5時過ぎ頃に着いたが誰一人、駐車していない。これは何だ。もしかして、一番乗り。そんな筈はないだろうと戸惑っていると、私の後ろから車が来て、そのまま真っ直ぐと進んでいく。これは、もしかして北谷登山口の駐車場まで行けるのか、とその車を追いかけていくと、果たして、北谷登山口の駐車場に多くの車が駐車していた。悔しいことに、私の前を走っていた車が最後のスポットを取ってしまったが、それから200メートルぐらい下りると、また10台以上は駐まれる駐車スペースがあった。しかも、さらにその下に駐車スペースがある。最近、増設したのであろうか。駐車スペースに関しては、北谷登山口、それほどホームページ等で言うほど心配しなくてもいいかもしれない。

(5時30分頃、ちょうど満車になった北谷登山口の駐車場。というか、駐車できるのであれば早くいってよ、みたいな気分。それとも平成31年ではなくて令和元年になったので、情報は古いとでも言い訳をするのだろうか)
ということで、5時45分には登山を始めた。北谷登山口から祖母山までには二つのルートがあるが、千間平、三県界を通る尾根ルートを取ることにした。このルートはそれぞれの合目に看板が設置され、さらには標高を示す看板も置かれているので、安心して登っていくことができる。ちなみに、それぞれの通過時間は、一合目が5時46分、二合目は6時17分、三合目は6時29分、四合目は6時41分、五合目は6時54分、六合目は7時17分、七合目は7時25分、八合目は7時38分、九合目は7時59分、山頂は8時20分であった。一合目から二合目まで時間がかかったのは、ストックが壊れたので、それを直そうとするのに時間がかかったからだ。一合目から四合目までは、結構、標高を稼ぐために登り坂は比較的厳しいが、それから七合目と八合目の中間にある国観峠までは尾根沿いのなだらかな登山道となる。ただ、展望は決してよくない。ただ、三合目ぐらいまでは植林の杉林が多く、緑のコンクリートのような無粋な森の中を歩いていくが、それ以降は広葉樹林が発達してきて目には優しい。国観峠から山頂までは、滑りやすい道が続く。ところどころに紐があり、これに頼って登っていく感じになる。登りはまだしも、下りは厳しいだろう。ただ、最近、雨が降っていないのか、事前にホームページ等で収集した情報に比べると、それほど困らずに山頂まで行くことができた。
山頂は九重連山、阿蘇山を含む360度の大展望を楽しむことができる。今日も天気はよかったので、展望には恵まれた。
さて、復路は往路と同じ道をと考えていたのだが、あまり面白くなかったので、「危険箇所あり、注意」との看板があり、単独行なのでちょっと怯んだが、幸い、比較的よくある太股の張りや膝の痛みがないのと、下山開始時が8時30分ということもあり、思い切って「風穴コース」を取ることにした。風穴コースは、急な窪地を下りていくため、ロープや梯子も多くある。ただ、昔は梯子をみると、ゲゲッと思ったが、最近ではむしろ楽なのでラッキーと思うようになっているので、そんなに苦にはしなかった。とはいえ、ちょっと段差があるところの着地で滑ったのと、木に足をかけたら、それが滑ったので、二回ほど尻餅をついた。幸い、怪我にはならなかったが、気をつけていてもこの泥のような登山道は滑る。さて、まあ、登山ルート的には往路に比べて、風穴コースは難度は高かったが、周辺の景観はとてもよく、こちらを選んで大正解であった。まず、往路ではほとんど見られなかった「ツクシアケボノツツジ」が蕾から、咲き始めているものまで多くあり、その派手でいて上品なピンク色が目を楽しませてくれた。風穴はただの洞穴にしか見えず、全然、感心しなかったが、登山口そばでは渓流沿いに歩いていき、その渓流美もなかなかのものであった。変化もあり、こちらの方がずっと楽しめる。往路は、国観峠の展望は悪くないし、八合目までなだらかな登山道であることや、看板が充実していて安心して登山できることはプラスではあるが、登山自体の楽しみは風穴コースの方が数倍優れているのではないかと思われる。
とはいえ、初めて祖母山を登るのであれば、いきなり風穴コースはびびるかもしれない。
さて、風穴コースで一番迷ったのが、登山口そばの林道に出たところ。左に行けばいいのか、右に行けばいいのか分からない。正解は左なのだが、私は携帯電話でチェックしようとしたがグーグルマップが使えず、結局、町のホームページの拡大地図を見て確認した。看板を設置した人は、ここは置かなくてもいいだろうと思ったのかもしれないが、一番、重要な分岐点であるような気がしないでもない。
登山口に戻ったのは10時45分。ということで5時間の行程であった。

(しばらくは緑のコンクリートのような生態系的にもいびつな自然の中を歩いて行く。無粋)

(ただ、3合目を越えたあたりから、広葉樹林が発達してくる)

(祖母山登山の敵が、この滑りやすい登山道)

(尾根沿いの登山ルートは合目ごとに貴重な情報が提供されていて有り難い)

(合目ごとの情報だけでなく、節目の標高となる場所でも看板が設置されている)

(国観峠から祖母山を仰ぐ)

(八合目から山頂までは、さらに登山道が滑りやすくなる。雨が降ると、本当、悲惨な登山になるだろう。よかった、晴れていて)

(山頂)

(山頂からの素晴らしい展望。これは南側をみたところ)

(山頂から九重連山を見る)

(山頂から阿蘇連山を見る)

(ツクシアケボノツツジがちょうど咲いていた)

(ツクシアケボノツツジの見事なピンク)

(ツクシアケボノツツジと祖母山周辺の山の見事なコントラスト)

(風穴コースは「危険」看板が多い)

(梯子や紐なども多く備え付けられている)

(またツクシアケボノツツジ。ツツジというよりかは桜のよう)

(巨大な岩がある場所から祖母山を見る)

(またまたツクシアケボノツツジ。これを見ただけでも風穴コースを選んで大正解)

(風穴コースの目玉である風穴は、その有り難みがよく分からなかった)

(ツクシアケボノツツジ以外にも可憐な紫のスミレが登山道沿いに咲いていた。可憐だ)


(風穴コースは登山口近くでは渓流沿いに歩いて行く。これもなかなかよかった)
さて、ゴールデンウィーク中であったので、これは相当、駐車場が混むことを予測した。昨日、久住山の登山口の牧ノ戸登山口が6時過ぎで200台のキャパを越えていたことを考えると、15台しか駐車できない北谷登山口の一の鳥居の駐車場はあっという間に満車になるだろう。
(その情報源となった高千穂町のHP。http://takachiho-kanko.info/sightseeing/detail.php?log=1381220521)
ということで、熊本空港そばのホテルは2時ちょっと過ぎに起き、3時にはチェックアウトをした。北谷登山口は東へ60キロメートルちょっと。昨日の牧ノ戸登山口とほぼ距離は一緒である。私のレンタカーのナビは古くて、道路が工事中で通行止めの情報を反映させていないが、昨日、失敗したので同じ轍を二度は踏まない。スムーズに移動していく。北谷登山口の入り口が分からないのではと不安に思ったが、看板がしっかりと出ていたので、迷わず、そちらに向かうことができた。
ホームページ等は登山口までの林道は車高が低いと気をつけろなどの注意をしていたが、それほどの悪路ではなかった。むしろ、拍子抜けしたぐらいだ。さて、一の鳥居の駐車場には5時過ぎ頃に着いたが誰一人、駐車していない。これは何だ。もしかして、一番乗り。そんな筈はないだろうと戸惑っていると、私の後ろから車が来て、そのまま真っ直ぐと進んでいく。これは、もしかして北谷登山口の駐車場まで行けるのか、とその車を追いかけていくと、果たして、北谷登山口の駐車場に多くの車が駐車していた。悔しいことに、私の前を走っていた車が最後のスポットを取ってしまったが、それから200メートルぐらい下りると、また10台以上は駐まれる駐車スペースがあった。しかも、さらにその下に駐車スペースがある。最近、増設したのであろうか。駐車スペースに関しては、北谷登山口、それほどホームページ等で言うほど心配しなくてもいいかもしれない。

(5時30分頃、ちょうど満車になった北谷登山口の駐車場。というか、駐車できるのであれば早くいってよ、みたいな気分。それとも平成31年ではなくて令和元年になったので、情報は古いとでも言い訳をするのだろうか)
ということで、5時45分には登山を始めた。北谷登山口から祖母山までには二つのルートがあるが、千間平、三県界を通る尾根ルートを取ることにした。このルートはそれぞれの合目に看板が設置され、さらには標高を示す看板も置かれているので、安心して登っていくことができる。ちなみに、それぞれの通過時間は、一合目が5時46分、二合目は6時17分、三合目は6時29分、四合目は6時41分、五合目は6時54分、六合目は7時17分、七合目は7時25分、八合目は7時38分、九合目は7時59分、山頂は8時20分であった。一合目から二合目まで時間がかかったのは、ストックが壊れたので、それを直そうとするのに時間がかかったからだ。一合目から四合目までは、結構、標高を稼ぐために登り坂は比較的厳しいが、それから七合目と八合目の中間にある国観峠までは尾根沿いのなだらかな登山道となる。ただ、展望は決してよくない。ただ、三合目ぐらいまでは植林の杉林が多く、緑のコンクリートのような無粋な森の中を歩いていくが、それ以降は広葉樹林が発達してきて目には優しい。国観峠から山頂までは、滑りやすい道が続く。ところどころに紐があり、これに頼って登っていく感じになる。登りはまだしも、下りは厳しいだろう。ただ、最近、雨が降っていないのか、事前にホームページ等で収集した情報に比べると、それほど困らずに山頂まで行くことができた。
山頂は九重連山、阿蘇山を含む360度の大展望を楽しむことができる。今日も天気はよかったので、展望には恵まれた。
さて、復路は往路と同じ道をと考えていたのだが、あまり面白くなかったので、「危険箇所あり、注意」との看板があり、単独行なのでちょっと怯んだが、幸い、比較的よくある太股の張りや膝の痛みがないのと、下山開始時が8時30分ということもあり、思い切って「風穴コース」を取ることにした。風穴コースは、急な窪地を下りていくため、ロープや梯子も多くある。ただ、昔は梯子をみると、ゲゲッと思ったが、最近ではむしろ楽なのでラッキーと思うようになっているので、そんなに苦にはしなかった。とはいえ、ちょっと段差があるところの着地で滑ったのと、木に足をかけたら、それが滑ったので、二回ほど尻餅をついた。幸い、怪我にはならなかったが、気をつけていてもこの泥のような登山道は滑る。さて、まあ、登山ルート的には往路に比べて、風穴コースは難度は高かったが、周辺の景観はとてもよく、こちらを選んで大正解であった。まず、往路ではほとんど見られなかった「ツクシアケボノツツジ」が蕾から、咲き始めているものまで多くあり、その派手でいて上品なピンク色が目を楽しませてくれた。風穴はただの洞穴にしか見えず、全然、感心しなかったが、登山口そばでは渓流沿いに歩いていき、その渓流美もなかなかのものであった。変化もあり、こちらの方がずっと楽しめる。往路は、国観峠の展望は悪くないし、八合目までなだらかな登山道であることや、看板が充実していて安心して登山できることはプラスではあるが、登山自体の楽しみは風穴コースの方が数倍優れているのではないかと思われる。
とはいえ、初めて祖母山を登るのであれば、いきなり風穴コースはびびるかもしれない。
さて、風穴コースで一番迷ったのが、登山口そばの林道に出たところ。左に行けばいいのか、右に行けばいいのか分からない。正解は左なのだが、私は携帯電話でチェックしようとしたがグーグルマップが使えず、結局、町のホームページの拡大地図を見て確認した。看板を設置した人は、ここは置かなくてもいいだろうと思ったのかもしれないが、一番、重要な分岐点であるような気がしないでもない。
登山口に戻ったのは10時45分。ということで5時間の行程であった。

(しばらくは緑のコンクリートのような生態系的にもいびつな自然の中を歩いて行く。無粋)

(ただ、3合目を越えたあたりから、広葉樹林が発達してくる)

(祖母山登山の敵が、この滑りやすい登山道)

(尾根沿いの登山ルートは合目ごとに貴重な情報が提供されていて有り難い)

(合目ごとの情報だけでなく、節目の標高となる場所でも看板が設置されている)

(国観峠から祖母山を仰ぐ)

(八合目から山頂までは、さらに登山道が滑りやすくなる。雨が降ると、本当、悲惨な登山になるだろう。よかった、晴れていて)

(山頂)

(山頂からの素晴らしい展望。これは南側をみたところ)

(山頂から九重連山を見る)

(山頂から阿蘇連山を見る)

(ツクシアケボノツツジがちょうど咲いていた)

(ツクシアケボノツツジの見事なピンク)

(ツクシアケボノツツジと祖母山周辺の山の見事なコントラスト)

(風穴コースは「危険」看板が多い)

(梯子や紐なども多く備え付けられている)

(またツクシアケボノツツジ。ツツジというよりかは桜のよう)

(巨大な岩がある場所から祖母山を見る)

(またまたツクシアケボノツツジ。これを見ただけでも風穴コースを選んで大正解)

(風穴コースの目玉である風穴は、その有り難みがよく分からなかった)

(ツクシアケボノツツジ以外にも可憐な紫のスミレが登山道沿いに咲いていた。可憐だ)


(風穴コースは登山口近くでは渓流沿いに歩いて行く。これもなかなかよかった)
九重山((日本百名山35座登頂) [日本百名山]
ゴールデンウィークに百名山の久住山に挑戦する。大型連休ということもあり、九重山(ちなみに久住山と九重山の違いであるが、前者は百名山の山、後者はこれを含む連山を指す時に使うようだ)周辺のホテルは料金がべらぼうに高いものを除けば満室。しかたがないので、熊本空港そばの宿を取る。登山口から60キロほど離れている。早朝、4時30分に出発。5時30分過ぎには着くだろうと思っていたら、なんと国道が工事で通行止め。阿蘇の山麓の道を迂回していくことになり、大幅な時間のロス。結局、牧ノ戸登山口に着いたのは6時過ぎであった。
さて、この駐車場は200台分あるので、私は流石に駐車できるだろうと高を括っていたのだが、すでに満車であった。恐るべき、ゴールデンウィーク。仕方がないので路駐。さて、結局、登山口から登山をし始めたのは、6時30分くらい。最初はいきなり階段が続く。この階段がアスファルトの絨毯のようなもので覆われていてとても風情がない。とはいえ、おかげで急坂であるにも関わらず歩きやすい。

(6時30分ちょっと前の牧ノ戸登山口の駐車場)

(牧ノ戸登山口)

(牧ノ戸登山口からはアスファルトが絨毯のように敷かれた階段状の坂道を上っていく)

(朝日を反射して輝くような九重山をみながら標高を稼いでいく)
この急坂は、沓掛山まで続く。沓掛山は牧ノ戸登山口からは30分ぐらい。ここからは九重連山が展望できる。沓掛山からは梯子などで坂を今度は下りる。ここらへんは上りと下りとでルートが分かれている(左通行)ようなのだが、あまり守られていない。私も下る時にそうであることに気づいた。
さて、この坂を下りた後は、しばらくなだらかな登り坂が続く。楽ではあるが、逆にアスファルト舗装がなくなり、若干、滑りにくい泥道になるので、その点は留意した方がいいかもしれない。扇ヶ鼻との分岐点にたどり着くと、本当に平坦でなだらかな草原を通っていく。この草原は西千里が浜と呼ばれており、夏になるとコスモスなどの高原植物が美しいようなのだが、今日はまったくそのような色彩的な美しさとは無縁であった。クマザサの緑が目に新しいくらいの色彩の貧困さである。左手に星生山を見ながら歩くと、展望が広がり、久住山をはじめとした九重連山が見える。とはいえ、中岳は見えない。坂を下りると、避難小屋とトイレがある。そのまま、まっすぐ礫の坂を登っていき、中岳との分岐点を右に行くと、久住山に辿りつくことができる。下からみると結構、遠くに見えたが、実際、登っているとそれほどきつくはなかった。避難小屋からおよそ30分ぐらいだろうか。

(7時30分には扇ヶ鼻との分岐点に着く)

(西千里が浜は平で歩きやすい)

(雄大な西千里が浜は歩いていて快適である。大体、ここを下りで通り過ぎたのは10時30分)

(西千里が浜を過ぎると、九重山の山々の雄大な展望が開ける)
幸い、天気に恵まれたこともあり、久住山からは見事な360度の展望を楽しむことができた。特に阿蘇山の優大な姿が印象に残っている。祖母山も見えた。ここで、簡単におにぎりなどを頬張る。空腹を満たすというよりかは荷物を軽くしたかったからだ。

(久住山の山頂から三俣山の方を展望する。山頂に登ったのは8時30分ほど。ほぼ2時間の行程)

(久住山の山頂から阿蘇山の方面を展望する)
その後、中岳分岐点まで戻り、中岳にチャレンジする。これは、九重連山の最高峰は中岳であるからだ。中岳への道は遠いが、それまでまったく姿が見えなかった御池という小さなカルデラ湖を展望することができたのは嬉しかった。というのも、この時期の久住山というか、九重連山は、色彩が貧相だ。黒と白と黄色の絵の具で表現できるような風景となっている。まるで、老いたライオンのような色なのだ。これは、あとひと月もすれば花も咲き、様変わりするのかもしれないが、ゴールデンウィークの九重山は岩だらけの、イメージ的にはまるで火星のような風景の山であった。もっと、女性的というかたおやかな山のイメージがあったので、これは意外であったが、活火山であることを考えればこのような風景であることは当然かもしれない。これまでに登った百名山では十勝岳をちょっと連想させた。まあ、そういうこともあって、御池の水の色はちょっと景色の変化をもたらしてくれて登山をする身にとっては有り難かった。御池はカルデラ湖(カルデラ池?)であることもあり、澄んでいて美しい色を放っていた。

(中岳に行く登山道は御池を迂回していくことになる)
さて、中岳に登頂するのは九重山よりかはちょっと難儀であった。そこからの展望は九重山がどっしりと見えるのと、九重山からは見えなかった御池が見えるので、より優れているかもしれない。避難小屋から山頂までの時間は久住山より中岳の方が倍とは言わないが、1.5倍は長いと思われる。ちなみに避難小屋から中岳に直接、行く場合はちょっとしたショートカットがあるので、それを使われるといいかと思う。

(登山口から中岳の山頂を望む)

(中岳の山頂。9時30分に登頂。出発してからほぼ3時間)

(噴煙を目撃すると、ここが依然として活火山であることを再確認する)
帰りは楽ではあるが、私は得意になって速く下りると膝を痛める癖があるので、今日は逸る気持ちを抑えてゆっくりと下りた。お陰で心地よい疲労以外、特に身体を痛めずに下山することができた。下山したのは11時30分をちょっと回っていた。総じて5時間ちょっとの登山であった。
沓掛山から下りる途中、牧ノ戸登山口周辺の道路をみると、長蛇の路駐の列が繋がっていた。どれだけの人が今日、九重山の登山に参加したのだろうか。私は二年前、ゴールデンウィークに筑波山に登ったことがあるのだが、その時はもう大渋滞で、まともに歩けないほどであった。それを体験したこともあったので、今日の人数ぐらいでは驚かなかったが、はしごのところなどでは待ち行列ができていたし、狭い登山道では随分と人を待ったり、待たせたりもした。小さな子供なども登山にチャレンジさせられたり、また赤ちゃんや犬を背負って登山していた人などもいたが、そんなに簡単な登山ではないような印象も受けた。

(帰りに目撃した駐車場に駐車できない自動車がつくった長蛇の路駐の列)

(多くの登山客が久住山へ続く礫の登山道を登っていく)
さて、この駐車場は200台分あるので、私は流石に駐車できるだろうと高を括っていたのだが、すでに満車であった。恐るべき、ゴールデンウィーク。仕方がないので路駐。さて、結局、登山口から登山をし始めたのは、6時30分くらい。最初はいきなり階段が続く。この階段がアスファルトの絨毯のようなもので覆われていてとても風情がない。とはいえ、おかげで急坂であるにも関わらず歩きやすい。

(6時30分ちょっと前の牧ノ戸登山口の駐車場)

(牧ノ戸登山口)

(牧ノ戸登山口からはアスファルトが絨毯のように敷かれた階段状の坂道を上っていく)

(朝日を反射して輝くような九重山をみながら標高を稼いでいく)
この急坂は、沓掛山まで続く。沓掛山は牧ノ戸登山口からは30分ぐらい。ここからは九重連山が展望できる。沓掛山からは梯子などで坂を今度は下りる。ここらへんは上りと下りとでルートが分かれている(左通行)ようなのだが、あまり守られていない。私も下る時にそうであることに気づいた。
さて、この坂を下りた後は、しばらくなだらかな登り坂が続く。楽ではあるが、逆にアスファルト舗装がなくなり、若干、滑りにくい泥道になるので、その点は留意した方がいいかもしれない。扇ヶ鼻との分岐点にたどり着くと、本当に平坦でなだらかな草原を通っていく。この草原は西千里が浜と呼ばれており、夏になるとコスモスなどの高原植物が美しいようなのだが、今日はまったくそのような色彩的な美しさとは無縁であった。クマザサの緑が目に新しいくらいの色彩の貧困さである。左手に星生山を見ながら歩くと、展望が広がり、久住山をはじめとした九重連山が見える。とはいえ、中岳は見えない。坂を下りると、避難小屋とトイレがある。そのまま、まっすぐ礫の坂を登っていき、中岳との分岐点を右に行くと、久住山に辿りつくことができる。下からみると結構、遠くに見えたが、実際、登っているとそれほどきつくはなかった。避難小屋からおよそ30分ぐらいだろうか。

(7時30分には扇ヶ鼻との分岐点に着く)

(西千里が浜は平で歩きやすい)

(雄大な西千里が浜は歩いていて快適である。大体、ここを下りで通り過ぎたのは10時30分)

(西千里が浜を過ぎると、九重山の山々の雄大な展望が開ける)
幸い、天気に恵まれたこともあり、久住山からは見事な360度の展望を楽しむことができた。特に阿蘇山の優大な姿が印象に残っている。祖母山も見えた。ここで、簡単におにぎりなどを頬張る。空腹を満たすというよりかは荷物を軽くしたかったからだ。

(久住山の山頂から三俣山の方を展望する。山頂に登ったのは8時30分ほど。ほぼ2時間の行程)

(久住山の山頂から阿蘇山の方面を展望する)
その後、中岳分岐点まで戻り、中岳にチャレンジする。これは、九重連山の最高峰は中岳であるからだ。中岳への道は遠いが、それまでまったく姿が見えなかった御池という小さなカルデラ湖を展望することができたのは嬉しかった。というのも、この時期の久住山というか、九重連山は、色彩が貧相だ。黒と白と黄色の絵の具で表現できるような風景となっている。まるで、老いたライオンのような色なのだ。これは、あとひと月もすれば花も咲き、様変わりするのかもしれないが、ゴールデンウィークの九重山は岩だらけの、イメージ的にはまるで火星のような風景の山であった。もっと、女性的というかたおやかな山のイメージがあったので、これは意外であったが、活火山であることを考えればこのような風景であることは当然かもしれない。これまでに登った百名山では十勝岳をちょっと連想させた。まあ、そういうこともあって、御池の水の色はちょっと景色の変化をもたらしてくれて登山をする身にとっては有り難かった。御池はカルデラ湖(カルデラ池?)であることもあり、澄んでいて美しい色を放っていた。

(中岳に行く登山道は御池を迂回していくことになる)
さて、中岳に登頂するのは九重山よりかはちょっと難儀であった。そこからの展望は九重山がどっしりと見えるのと、九重山からは見えなかった御池が見えるので、より優れているかもしれない。避難小屋から山頂までの時間は久住山より中岳の方が倍とは言わないが、1.5倍は長いと思われる。ちなみに避難小屋から中岳に直接、行く場合はちょっとしたショートカットがあるので、それを使われるといいかと思う。

(登山口から中岳の山頂を望む)

(中岳の山頂。9時30分に登頂。出発してからほぼ3時間)

(噴煙を目撃すると、ここが依然として活火山であることを再確認する)
帰りは楽ではあるが、私は得意になって速く下りると膝を痛める癖があるので、今日は逸る気持ちを抑えてゆっくりと下りた。お陰で心地よい疲労以外、特に身体を痛めずに下山することができた。下山したのは11時30分をちょっと回っていた。総じて5時間ちょっとの登山であった。
沓掛山から下りる途中、牧ノ戸登山口周辺の道路をみると、長蛇の路駐の列が繋がっていた。どれだけの人が今日、九重山の登山に参加したのだろうか。私は二年前、ゴールデンウィークに筑波山に登ったことがあるのだが、その時はもう大渋滞で、まともに歩けないほどであった。それを体験したこともあったので、今日の人数ぐらいでは驚かなかったが、はしごのところなどでは待ち行列ができていたし、狭い登山道では随分と人を待ったり、待たせたりもした。小さな子供なども登山にチャレンジさせられたり、また赤ちゃんや犬を背負って登山していた人などもいたが、そんなに簡単な登山ではないような印象も受けた。

(帰りに目撃した駐車場に駐車できない自動車がつくった長蛇の路駐の列)

(多くの登山客が久住山へ続く礫の登山道を登っていく)
八幡平に登る(日本百名山34座登頂) [日本百名山]
早池峰山に登り、下山したのが12時ちょっと前。そこから八幡平に車で移動する。紫波町で蕎麦冷麺という変わった創作料理を食べ、八幡平の見返峠に到着したのが15時。八幡平には登山道というかハイキング・ルートの前にトイレやお土産物屋が入っているビルの駐車場がある。ここは駐車料金が500円である。しかし、その手前200メートルぐらいのところにある駐車場は無料である。ということで、こちらに駐車する。天気は見事で、昨日、我々が山頂アタックを断念させられた岩手山がその雄大な山容を惜しげもなく晒している。ちょっと悔しい。
八幡平の見返峠からの登山道は、しっかりと舗装がされており、登山というよりかはハイキングのようなものである。途中、鏡沼、めがね沼という美しい火山湖を見つつ、八幡平の頂上に着く。頂上であるのは、ここが一番標高が高いからであるが、平坦で見晴らしはきかず、山頂にある展望台に登って周りを見渡すというちょっと間抜け感がする。どうも、この展望台をつくった人もそう思ったのか、言い訳のように深田久弥の『日本百名山』がなぜ、ここを百名山に選定したかの文章を引用した看板が立てられている。そこで何が書いているかは覚えていないので、ちょっと私もここに深田久弥から引用させてもらう。
「しかし八幡平の真価は、やはり高原逍遥にあるだろう。一枚の大きな平坦な原ではなく、ゆるい傾斜を持った高低のある高原で、気持ちのいい岱を一つ横切るとみごとな原始林へ入ったり、一つの丘を越すと思いがけなく沼があったりして、その変化のある風景がおもしろい」。
確かに、帰り際にみた八幡沼やがま沼なども美しく、その高原的風土は日本の自然の美しさを表している。ただ、往復で1時間もせずに駐車場から山頂までアクセスできる利便性と引き替えに、その自然の懐の深さなどが失われているような印象を受けた。特に午前中に早池峰山に登ったのでなおさら、その差が大きく感じられた。おそらく、八幡平も早池峰山のようにしっかりと自然環境、エコシステムを保全するというアプローチを採っていれば、現在よりもさらに素晴らしい場所として存在していたのではないかと思われる。多くの人が楽にアクセスできるようにすることによって、利益を享受する人も増えるが、それによって失われるものも多い。特に道路を整備することは、益も多いが、マイナス面も少なくない。道路が不便でアクセスが悪いゆえの素晴らしさを早池峰山で実感したので、八幡平はちょっと気になった。
駐車場に戻ったのは16時ちょっと過ぎ。おそらく、これまでの34座で最も楽な日本百目山であった。初めて一日で二つの百名山を登った。

(登山口のそばの駐車場から岩手山を望む。見事な山容である)

(八幡平への登山道はしっかりと整備されている)

(鏡沼は雪解け時にはドラゴンアイと呼ばれる美しい自然現象がみられる)

(めがね沼)

(八幡平の山頂)

(がま沼。後ろに見えるのは岩手山)

(八幡沼)
八幡平の見返峠からの登山道は、しっかりと舗装がされており、登山というよりかはハイキングのようなものである。途中、鏡沼、めがね沼という美しい火山湖を見つつ、八幡平の頂上に着く。頂上であるのは、ここが一番標高が高いからであるが、平坦で見晴らしはきかず、山頂にある展望台に登って周りを見渡すというちょっと間抜け感がする。どうも、この展望台をつくった人もそう思ったのか、言い訳のように深田久弥の『日本百名山』がなぜ、ここを百名山に選定したかの文章を引用した看板が立てられている。そこで何が書いているかは覚えていないので、ちょっと私もここに深田久弥から引用させてもらう。
「しかし八幡平の真価は、やはり高原逍遥にあるだろう。一枚の大きな平坦な原ではなく、ゆるい傾斜を持った高低のある高原で、気持ちのいい岱を一つ横切るとみごとな原始林へ入ったり、一つの丘を越すと思いがけなく沼があったりして、その変化のある風景がおもしろい」。
確かに、帰り際にみた八幡沼やがま沼なども美しく、その高原的風土は日本の自然の美しさを表している。ただ、往復で1時間もせずに駐車場から山頂までアクセスできる利便性と引き替えに、その自然の懐の深さなどが失われているような印象を受けた。特に午前中に早池峰山に登ったのでなおさら、その差が大きく感じられた。おそらく、八幡平も早池峰山のようにしっかりと自然環境、エコシステムを保全するというアプローチを採っていれば、現在よりもさらに素晴らしい場所として存在していたのではないかと思われる。多くの人が楽にアクセスできるようにすることによって、利益を享受する人も増えるが、それによって失われるものも多い。特に道路を整備することは、益も多いが、マイナス面も少なくない。道路が不便でアクセスが悪いゆえの素晴らしさを早池峰山で実感したので、八幡平はちょっと気になった。
駐車場に戻ったのは16時ちょっと過ぎ。おそらく、これまでの34座で最も楽な日本百目山であった。初めて一日で二つの百名山を登った。

(登山口のそばの駐車場から岩手山を望む。見事な山容である)

(八幡平への登山道はしっかりと整備されている)

(鏡沼は雪解け時にはドラゴンアイと呼ばれる美しい自然現象がみられる)

(めがね沼)

(八幡平の山頂)

(がま沼。後ろに見えるのは岩手山)

(八幡沼)
早池峰山(日本百名山33座登頂) [日本百名山]
盛岡市のホテルに前泊して、レンタカーで早池峰山へと向かう。早池峰山には二つの登山ルートがある。河原坊コースと小田越コースである。ただし、河原坊コースは現在、通行止めであり、小田越コースしかルートはない。駐車場があるのは河原坊コースである。したがって、河原坊コースから小田越コースまでは車道を歩かなくてはならない。登山に来て、興醒めするのは車道歩きである。車道を歩くのであれば都会でもできる。そして、河原坊の登山口から小田越の登山口までは上りで40分、下りで30分もかかる。さて、しかし、である。というか、ここに書くのは相当、躊躇するのだが、小田越コースにも駐車場はあるのだ。ただし、10台ほどしか駐車することはできない。そして駐車できなければ河原坊まで戻らなくてはならない。しかし、ここに駐車できれば往復で1時間以上も節約することができる。ということで、ホテルを早朝4時過ぎにでる。盛岡市から早池峰山の登山口までは意外と時間がかかる。これは、アクセス道路が相当、悪路であるからだ。しかし、個人的にこの悪路は期待感を盛り上げてくれるので嬉しい。舗装がしっかりとされた道路ですいすいと登山口に行くのは楽かもしれないが、登山の楽しみや期待感を大きく萎ませる気がする。やはり、人里離れた大自然に行くにはアプローチがそれなりに遠い方がいい。
さて、河原坊コースに到着すると、まだ駐車場の空きは多い。ここでも駐車できないと、はるか下の岳集落で駐車をしないといけない。しかし、今日は土曜日で晴天好日であったが、まだ6時前ということもあり、小田越の駐車場にて駐車できなくても河原坊の駐車場には駐まれるであろうと判断し、小田越の駐車場に向かう。さて、運良く小田越の駐車場には駐車することができた。朝日が素晴らしく、清々しい凜とした空気が周りを包み込んでいる。そして、南側には薬師岳、北側には早池峰山が屹立している。
早池峰山は環境保全が徹底しており、登山ルートにはトイレがなく、また、そこらへんで用を足すことが禁止されている。そのため、携帯トイレを携行しないといけない。この携帯トイレは登山口で販売されている。ちなみに、私は常に持参しているので買わなくて済んだ。また、登山口にある管理人事務所にはトイレがあり、トイレットペーパーも置かれているので、是非ともここで用を済ましてから登山するといいとお節介ながら助言したい。
登山口を出発したのは6時15分。美しい樹林帯の中を歩いて行く。人工物が一切ない大自然の懐に抱かれているような気分になる。このような気分になるのは、モンタナ州とかイエローストーン、アラスカなどでは感じたことがあるが、日本では強いていえば知床の羅臼岳に登った時ぐらいであろうか。こういうところが本州にあるというのを知っただけでも、今回、ここに来たことがある。私の34回の登山経験の中でも希有の素晴らしい自然体験である。早池峰は環境保全が厳しい理由を分かったような気がする。
さて、樹林帯を抜けると、蛇紋岩の岩道となる。二週間前に登った尾瀬の至仏山も蛇紋岩の山であるが、こちらの蛇紋岩は至仏山より遙かに巨大である。登山路の蛇紋岩もより大きく、滑り具合もより酷い。幸い、晴れていたのでそれほどでもなかったが、雨が降ったりしたらさぞかし、滑って歩きにくいだろうと思う。もくもくと高度を上げていくと、右側には太平洋が見えてくる。樹林限界を超えているのか、高い木がまったくないので、展望は素晴らしいものがある。そして、この山は高山植物が素晴らしい。高山植物の見頃は6月下旬から8月上旬らしく、この時期は週末はマイカーが入れない。我々は、このマイカー規制が終了した翌週ということで、ゴールデンウィークの次の週末のような感じで登山客は少なかったが、まだ高山植物はそこそこ咲いており、それは見事なものであった。一番の目玉はハヤチネウスユキソウというエーデルワイスの近似種であり、小さいながら可憐な花を愛でながらの登山は気持ちを明るくする。ここらへんの地区一帯は国の特別天然記念物に指定されているそうだが、確かに非常に特別な場所であることを感じる。これは、世界遺産クラスだなと思ったが、下手に世界遺産に指定されると逆に多くの観光客が訪れて、環境保護的には本末転倒の事態になるか、白神山地のようにまたぎも入れないほど管理をされて結局、訪問できなくなるかもしれないので、ここは現状のままでいいのかなと思ったりもする。
ハヤチネウスユキソウ以外には、ナンブトウウチソウという赤紫色のねこじゃらしのような花が咲き乱れていた。蛇紋岩の登山道はなかなか傾斜は急であるが、一歩一歩丁寧に歩いて行く。八合目を過ぎると、特に急なところに出て、ここはなかなか長い梯子がかけられている。ただ、梯子で登るほど垂直ではなく、梯子を這って登るような感じだ。梯子に到着した時間は8時30分。ほぼ登山口からは2時間20分、ということでコースタイムよりはゆっくりである。梯子を登り切ると、また岩場が続く。ただ、もう尾根は目の前である。尾根に出た後は、お花畑の中を木道で歩いて行く。山頂に到着したのは9時。出発から2時間50分とゆっくりであったが、ゆっくり登ったおかげで太股も脹ら脛も攣りそうになることもなく、膝も痛くなっていない。
山頂からは東には太平洋、北は八甲田山、西には鳥海山、そして南には薬師岳のその背後にある広大な北上山地を展望することができる。見事な絶景である。二週間前に訪れた至仏山からも360度の絶景を展望できたが、異なるのは早池峰山からの展望は人工物がほとんど見えないことだ。至仏山はダムなどが見れたりしたが、早池峰山からはそのようなものも見えない。僅かに駐車場や管理小屋が薬師岳との間の谷に見え隠れするぐらいだ。この北上山地の素晴らしい大自然に感動すると同時に、こんなところが本州にあったのかと驚きを覚える。大雪山よりも、さらに大自然の中に包まれている感じを受ける。これは見事な山である。ただ、今日のように晴天の日は珍しいということを山頂で一緒になった地元の登山者から聞く。昨日の岩手山、一昨日の八甲田山と天気に祟られたが、その二日間のマイナスを取り返せたほどの見事な登山日和に早池峰山に登ることができた。
山頂ではお湯を沸かして、カップ麺を食べて、ゆっくりと下山する。山頂が平坦で、ゆっくりと座れるところもこの山の素晴らしいところである。これは岩木山や蓼科山のように山頂が岩でごつごつしているところに比べると遙かにいい。下山は蛇紋岩で滑りやすいこともありゆっくりと降りていく。梯子は登りより降りの方が難しい。しっかりと足場を確認しつつ、降りる。帰路は周りをじっくりと観察しながら歩いたのだが、蝉やバッタ、そして苔などがとても綺麗な色をしている。自然の美しさをつくづくと実感することができたが、このような経験はアメリカの国立公園などではしたことがあるが、日本の国立公園だと知床や立山でも経験したことがない。この早池峰山というのは、そういう意味でも、何か特別な場所であるような気がする。なんか生態系が非常に正しい、と実感させるような場所である。
私は緊張していたせいか、便秘気味になっており、かつ発汗もしていたので尿意も催せず、携行トイレのお世話にならず、無事、12時ちょっと前に登山口に到着する。
25年ぐらい前にサラリーマンをしていた時、登山好きの同僚の女性が早池峰山を登ったことを嬉しげに話してくれたことがある。当時、山にまったく関心がなかった私は、そういう山があるのかぐらいに思っていたのだが、今日、早池峰山に登り、いかにこの山が特別であるかを理解することができた。百名山登山を目指すという目標をたてなければ、おそらくこの山に登ることは一生なかったかと思う。早池峰山を登ったという貴重な経験をしただけでも、百名山登山を目指してよかったと思う。

(小田越の駐車場から早池峰山を望む)

(小田越の登山口)

(登山の最初は森の中を歩いて行く。苔が美しい)

(早池峰山の雄姿。貫禄と風格に溢れた素晴らしい山である)

(登山道を振り返ると薬師岳が見られる)

(エーデルワイスの近似種のハヤチネウスユキソウ)

(猫じゃらしのようなナンブトウウチソウ)

(太平洋の方を望む)

(早池峰山は蛇紋岩の総大将のような山でもある)

(太平洋側を望む)

(サインでさえお洒落で洗練されている)

(登山道から山頂の方向を望む)

(長い梯子が我々を待ち構えていた)

(山頂)

(山頂から薬師岳を望む)

(山頂から西を見る。左の方に雲の上から顔を出している岩手山を見ることができる)

(山頂から東を望む)

(小田越から山頂へ行くルートは途中、お花畑を通る)

(蝉でさせ、厳かな気分にさせるほど美しい)

(苔も美しい)
さて、河原坊コースに到着すると、まだ駐車場の空きは多い。ここでも駐車できないと、はるか下の岳集落で駐車をしないといけない。しかし、今日は土曜日で晴天好日であったが、まだ6時前ということもあり、小田越の駐車場にて駐車できなくても河原坊の駐車場には駐まれるであろうと判断し、小田越の駐車場に向かう。さて、運良く小田越の駐車場には駐車することができた。朝日が素晴らしく、清々しい凜とした空気が周りを包み込んでいる。そして、南側には薬師岳、北側には早池峰山が屹立している。
早池峰山は環境保全が徹底しており、登山ルートにはトイレがなく、また、そこらへんで用を足すことが禁止されている。そのため、携帯トイレを携行しないといけない。この携帯トイレは登山口で販売されている。ちなみに、私は常に持参しているので買わなくて済んだ。また、登山口にある管理人事務所にはトイレがあり、トイレットペーパーも置かれているので、是非ともここで用を済ましてから登山するといいとお節介ながら助言したい。
登山口を出発したのは6時15分。美しい樹林帯の中を歩いて行く。人工物が一切ない大自然の懐に抱かれているような気分になる。このような気分になるのは、モンタナ州とかイエローストーン、アラスカなどでは感じたことがあるが、日本では強いていえば知床の羅臼岳に登った時ぐらいであろうか。こういうところが本州にあるというのを知っただけでも、今回、ここに来たことがある。私の34回の登山経験の中でも希有の素晴らしい自然体験である。早池峰は環境保全が厳しい理由を分かったような気がする。
さて、樹林帯を抜けると、蛇紋岩の岩道となる。二週間前に登った尾瀬の至仏山も蛇紋岩の山であるが、こちらの蛇紋岩は至仏山より遙かに巨大である。登山路の蛇紋岩もより大きく、滑り具合もより酷い。幸い、晴れていたのでそれほどでもなかったが、雨が降ったりしたらさぞかし、滑って歩きにくいだろうと思う。もくもくと高度を上げていくと、右側には太平洋が見えてくる。樹林限界を超えているのか、高い木がまったくないので、展望は素晴らしいものがある。そして、この山は高山植物が素晴らしい。高山植物の見頃は6月下旬から8月上旬らしく、この時期は週末はマイカーが入れない。我々は、このマイカー規制が終了した翌週ということで、ゴールデンウィークの次の週末のような感じで登山客は少なかったが、まだ高山植物はそこそこ咲いており、それは見事なものであった。一番の目玉はハヤチネウスユキソウというエーデルワイスの近似種であり、小さいながら可憐な花を愛でながらの登山は気持ちを明るくする。ここらへんの地区一帯は国の特別天然記念物に指定されているそうだが、確かに非常に特別な場所であることを感じる。これは、世界遺産クラスだなと思ったが、下手に世界遺産に指定されると逆に多くの観光客が訪れて、環境保護的には本末転倒の事態になるか、白神山地のようにまたぎも入れないほど管理をされて結局、訪問できなくなるかもしれないので、ここは現状のままでいいのかなと思ったりもする。
ハヤチネウスユキソウ以外には、ナンブトウウチソウという赤紫色のねこじゃらしのような花が咲き乱れていた。蛇紋岩の登山道はなかなか傾斜は急であるが、一歩一歩丁寧に歩いて行く。八合目を過ぎると、特に急なところに出て、ここはなかなか長い梯子がかけられている。ただ、梯子で登るほど垂直ではなく、梯子を這って登るような感じだ。梯子に到着した時間は8時30分。ほぼ登山口からは2時間20分、ということでコースタイムよりはゆっくりである。梯子を登り切ると、また岩場が続く。ただ、もう尾根は目の前である。尾根に出た後は、お花畑の中を木道で歩いて行く。山頂に到着したのは9時。出発から2時間50分とゆっくりであったが、ゆっくり登ったおかげで太股も脹ら脛も攣りそうになることもなく、膝も痛くなっていない。
山頂からは東には太平洋、北は八甲田山、西には鳥海山、そして南には薬師岳のその背後にある広大な北上山地を展望することができる。見事な絶景である。二週間前に訪れた至仏山からも360度の絶景を展望できたが、異なるのは早池峰山からの展望は人工物がほとんど見えないことだ。至仏山はダムなどが見れたりしたが、早池峰山からはそのようなものも見えない。僅かに駐車場や管理小屋が薬師岳との間の谷に見え隠れするぐらいだ。この北上山地の素晴らしい大自然に感動すると同時に、こんなところが本州にあったのかと驚きを覚える。大雪山よりも、さらに大自然の中に包まれている感じを受ける。これは見事な山である。ただ、今日のように晴天の日は珍しいということを山頂で一緒になった地元の登山者から聞く。昨日の岩手山、一昨日の八甲田山と天気に祟られたが、その二日間のマイナスを取り返せたほどの見事な登山日和に早池峰山に登ることができた。
山頂ではお湯を沸かして、カップ麺を食べて、ゆっくりと下山する。山頂が平坦で、ゆっくりと座れるところもこの山の素晴らしいところである。これは岩木山や蓼科山のように山頂が岩でごつごつしているところに比べると遙かにいい。下山は蛇紋岩で滑りやすいこともありゆっくりと降りていく。梯子は登りより降りの方が難しい。しっかりと足場を確認しつつ、降りる。帰路は周りをじっくりと観察しながら歩いたのだが、蝉やバッタ、そして苔などがとても綺麗な色をしている。自然の美しさをつくづくと実感することができたが、このような経験はアメリカの国立公園などではしたことがあるが、日本の国立公園だと知床や立山でも経験したことがない。この早池峰山というのは、そういう意味でも、何か特別な場所であるような気がする。なんか生態系が非常に正しい、と実感させるような場所である。
私は緊張していたせいか、便秘気味になっており、かつ発汗もしていたので尿意も催せず、携行トイレのお世話にならず、無事、12時ちょっと前に登山口に到着する。
25年ぐらい前にサラリーマンをしていた時、登山好きの同僚の女性が早池峰山を登ったことを嬉しげに話してくれたことがある。当時、山にまったく関心がなかった私は、そういう山があるのかぐらいに思っていたのだが、今日、早池峰山に登り、いかにこの山が特別であるかを理解することができた。百名山登山を目指すという目標をたてなければ、おそらくこの山に登ることは一生なかったかと思う。早池峰山を登ったという貴重な経験をしただけでも、百名山登山を目指してよかったと思う。

(小田越の駐車場から早池峰山を望む)

(小田越の登山口)

(登山の最初は森の中を歩いて行く。苔が美しい)

(早池峰山の雄姿。貫禄と風格に溢れた素晴らしい山である)

(登山道を振り返ると薬師岳が見られる)

(エーデルワイスの近似種のハヤチネウスユキソウ)

(猫じゃらしのようなナンブトウウチソウ)

(太平洋の方を望む)

(早池峰山は蛇紋岩の総大将のような山でもある)

(太平洋側を望む)

(サインでさえお洒落で洗練されている)

(登山道から山頂の方向を望む)

(長い梯子が我々を待ち構えていた)

(山頂)

(山頂から薬師岳を望む)

(山頂から西を見る。左の方に雲の上から顔を出している岩手山を見ることができる)

(山頂から東を望む)

(小田越から山頂へ行くルートは途中、お花畑を通る)

(蝉でさせ、厳かな気分にさせるほど美しい)

(苔も美しい)

